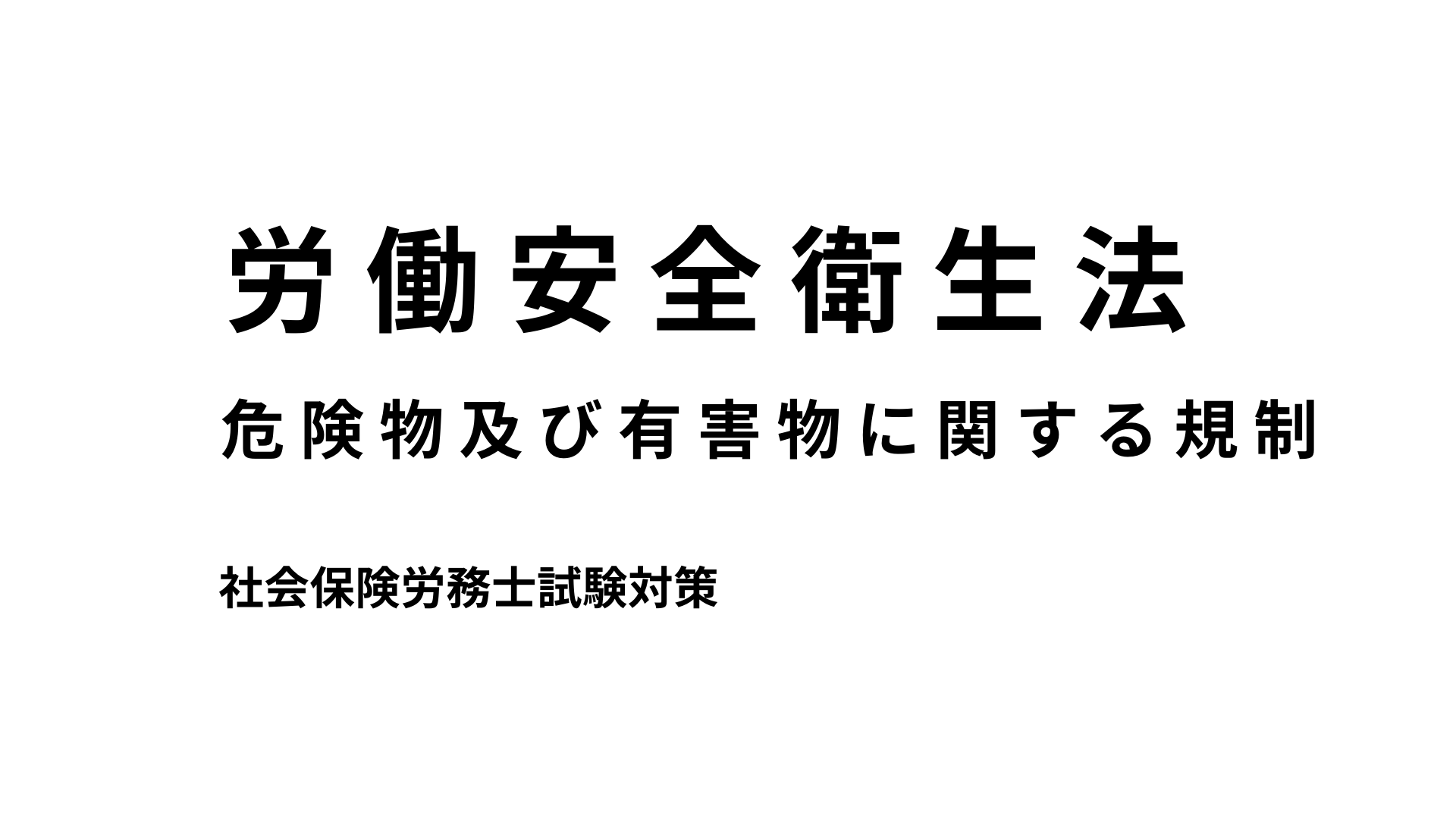労働安全衛生法の機械等並びに危険物及び有害物に関する規制から「機械等に関する規制」について解説します。本章は「機械等」と「危険物・有害物」がセットになっていますが、節として2つに分けられているので、条文構造を把握するためにもここでは2つに分けています。
製造の許可
・特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない(37条1項目)。
・特定機械等は次に掲げる機械等とする(政令12条)。
- ボイラー
- 第一種圧力容器
- つり上げ荷重が3トン以上のクレーン
- つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
- つり上げ荷重が2トン以上のデリツク
- 積載荷重が1トン以上のエレベーター
- ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
- ゴンドラ
→これらが細かく問われることは少ないと思いますが、なんとなくボイラーやクレーンなど危なそうなものが特定機械等に指定されていることをおさえておきましょう。それらを製造するときは許可が必要になります。
製造時等検査等
・特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない(38条1項本文)。
→先ほどは製造しようとするときの事前の許可でした。次は、製造したときの事後の検査です。細かいところまで深追いするとかえって全体像が見えなくなるので、特定機械等を製造したときは、都道府県労働局長の検査を受けなければならないとおさえておきましょう。
・特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない(38条3項)。
→続いて、移動式のものを除く、つまり固定式に限った話です。固定式の特定機械等を設置したときは、労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。移動式は、都道府県労働局長の許可と検査が必要であるのに対し、固定式は、都道府県労働局長の許可と検査、労働基準監督署長の検査が必要であることをおさえておきましょう。
| 移動式 | 固定式 | |
| 都道府県労働局長の許可 | 必要 | 必要 |
| 都道府県労働局長の検査 | 必要 | 必要 |
| 労働基準監督署長の検査 | 不要 | 必要 |
検査証の交付等
・都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した移動式の特定機械等について、検査証を交付する(39条1項)。
・労働基準監督署長は、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、検査証を交付する(39条2項)。
→上記の検査に合格すると検査証が交付されます。
譲渡等の制限等
・特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない(42条、政令13条3項)。
→これまでは、ボイラーやクレーンなど特定機械等の話でした。ここは、特定機械等以外の機械です。具体的にひとつひとつ覚える必要はありませんが、たとえば、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器、研削盤などが政令で指定されています。これらは、特定機械ほどまでではありませんが、危険なので、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置できないとされています。
個別検定
・第42条の機械等(型式検定対象の機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない(44条1項、政令14条)。
→先ほどの42条の機械等のうち、具体的にひとつひとつ覚える必要はありませんが、小型ボイラーや小型圧力容器など政令で定めるものは、個別検定を受ける必要があります。
型式検定
・第42条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない(44条の2第1項本文、政令14条の2)。
→先ほどの42条の機械等のうち、具体的にひとつひとつ覚える必要はありませんが、防じんマスクや防毒マスクなど政令で定めるものは、型式検定を受ける必要があります。ひとつひとつが大きいものは、個別検定を受ける必要があり、ある程度大量に作られるものは型式検定を受けるイメージです。個別検定の条文も、「第42条の機械等(型式検定対象の機械等を除く。)のうち」として、個別検定を受けるものと型式検定を受けるものを振り分けているのがわかります。
定期自主検査
・事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない(45条1項、政令15条)。
→政令で定めるものは、特定機械等などです。これらは危険なので、定期に自主検査を行わなければなりません。ここまでで、特定機械等は、事前に許可を受けて製造し、製造したあとは検査を受け、かつ定期に検査が必要であることがわかります。
・事業者は、自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は登録個別検定機関の登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない(45条2項、規則135条の3第1項、134条の3第1項)。
→特定自主検査とは、動力プレス等について、1年以内ごとに1回、定期に行う自主検査のことをいいます。本試験対策として、特定機械等は定期自主検査が必要ですが、特定自主検査は必要ではありません。特定自主検査はあくまで、動力プレス等について定められたもので、厚生労働省令で定める資格を有するものや検査業者に検査を実施させなければならないというものです。「特定」という言葉に引っ張られないように注意しましょう。
まとめ
機械等に関する規制について整理します。
まず、特定機械等を製造などするときの流れをおさえましょう。
- 製造の許可(37条1項)
- 都道府県労働局長の検査(38条1項)
- 労働基準監督署の検査【固定式のみ】(38条2項)
- 検査証の交付(39条1項、2項)
次に、特定機械等以外の機械等を譲渡などするときの流れをおさえましょう。
- 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備(42条)
- 個別検定(44条)・型式検定(44条の2)
最後に、定期自主検査の流れをおさえましょう。対象は主に特定機械等です。
- 定期自主検査(45条1項)
- 特定自主検査【動力プレス】(45条2項)
繰り返しますが、特定自主検査は、特定機械等について定められたものではありません。