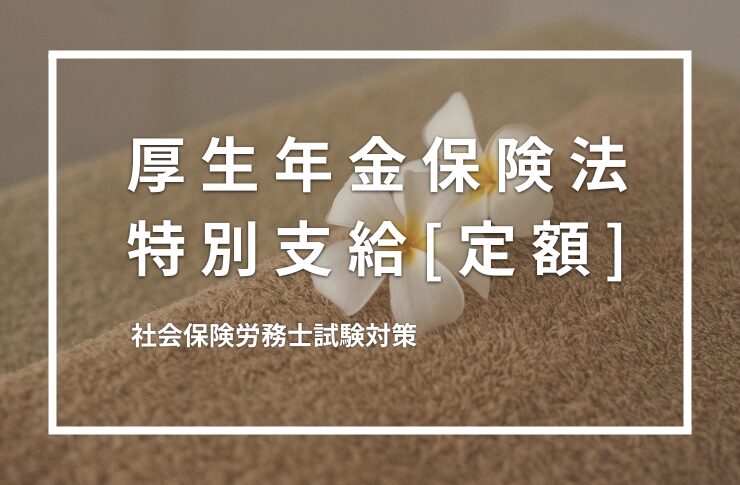厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金について学習します。今回は、特別支給の老齢厚生年金のうち報酬比例部分についてみていきましょう。
老齢厚生年金の特例
① 60歳以上であること。
② 1年以上の被保険者期間を有すること。
③ 第42条第2号[保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上]に該当すること。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳未満の者に老齢厚生年金を支給するというものです。昭和60年の法改正(昭和61年4月施行)により、老齢厚生年金は65歳から支給することとされました。しかし、これまで原則60歳から支給されていた老齢厚生年金を65歳からとするのは既得権の保護に欠けるため、「特別支給の老齢厚生年金」(60歳台前半の老齢厚生年金)の制度がつくられました。
以下、本試験や日本年金機構に合わせて「特別支給の老齢厚生年金」と表記します。
柱書が「65歳未満の者」とあり、1号が「60歳以上」とあることから、特別支給の老齢厚生年金は、60歳から65歳までの年金であることがわかります。65歳以降は、本則で定められている老齢厚生年金が支給されます。
2号について、老齢厚生年金は、1月以上でも支給されることと比較しておきましょう(43条1項)。
3号について、保険料納付済期間等が10年以上必要なのは、老齢厚生年金と同じです。
特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例
特別支給の老齢厚生年金は、原則60歳以上に支給されます。そして、附則8条の2第1項から4項にかけて、読み替えが規定されています。
- 1項:男子、女子(2号、3号、4号)
- 2項:女子(1号)
- 3項:坑内員、船員
- 4項:特定警察職員等
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
男子および2号、3号、4号被保険者の女子について、「昭和28年4月2日」以降に生まれた者については、2年ごとに支給開始年齢が1歳ずつ引き上げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた者は、65歳から支給開始となります。
| 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
1号被保険者の女子について、先ほどの表から5年遅れたものになります。昔は、男子の支給開始年齢が60歳、女子の支給開始年齢が55歳だった時期があり(女子の定年が男子より早いということです)、その名残から、男子よりも5年遅れた形で支給開始年齢が引き上げられることとなりました。「昭和28年4月2日」を基準にして、1号女子はそこから5年遅いと覚えるのをおすすめします。
| 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
坑内員と船員の被保険者期間を合算した期間が15年以上である者について、女子と同じく、5年遅れたものになります。坑内員と船員は、他の職種に比べて過酷な環境で働いていることが多いため、健康への負担が大きく、早期の年金支給が考慮されていたと考えると理解しやすいと思います。
| 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和36年4月2日から昭和38年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和38年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
特定警察職員等について、基本から6年遅れたものになります。特定警察職員等も過酷な勤務が求められることから、基本より引き上げの生年月日を6年遅らせていると考えるとわかりやすいと思います。
特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分については、加給年金額は適用しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる(附則9条の2第1項)。
前項の請求があったときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があった月の翌月から、年金の額を改定する(附則9条の2第2項)。
① 1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
② 被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
障害者の場合、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することによって、①定額部分と②報酬比例部分を受給することができます。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、権利を取得した当時、被保険者期間が44年以上であるもの、坑内員と船員の被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上あるときも、①定額部分と②報酬比例部分を受給することができます。
65歳以降は、老齢厚生年金の支給が開始します。特別支給の老齢厚生年金は、別の制度であるという認識を持っておくようにしましょう。
老齢厚生年金と同様の規定がされています。
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至った月までの各月において、その支給を停止する(附則11条の5,同7条の4)。
① 当該受給資格に係る受給期間が経過したとき。
② 当該受給権者が当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったとき。
特別支給の老齢厚生年金は、受給権者が求職の申込みをしたときは、求職の申込みがあった月の翌月から受給期間を経過したとき、または基本手当の支給を受け終わったときまで、支給を停止します。特別支給の老齢厚生年金は、あくまで特別なので、雇用保険法の方で基本手当がもらえる間は、支給を停止するということです。
特別支給の老齢厚生年金は、支給の繰下げはできません。一方、後述のように、支給の繰上げはすることができます。
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
附則第8条の2各項[特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例]に規定する者であって、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項[任意加入被保険者]の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる(附則13条の4第1項)。
請求は、支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない(附則13条の4第2項)。
請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する(附則13条の4第3項)。
老齢厚生年金の額は、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする(附則13条の4第4項)。
老齢厚生年金の受給権者であって、請求があった日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(附則13条の4第5項)。
老齢厚生年金の受給権者であって、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(附則13条の4第6項)。
受給開始年齢が61歳以降の者は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができます。支給繰上げの請求は同時に行う必要があること、請求があった日の属する月から、老齢厚生年金を支給すること、政令で定める額を減じた額とすることなどは、老齢厚生年金の支給繰上げと同じです。
そして、本来の受給開始年齢に達したときは、年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。また、65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。65歳に達したあとは、通常の老齢厚生年金になる点も注意しましょう。