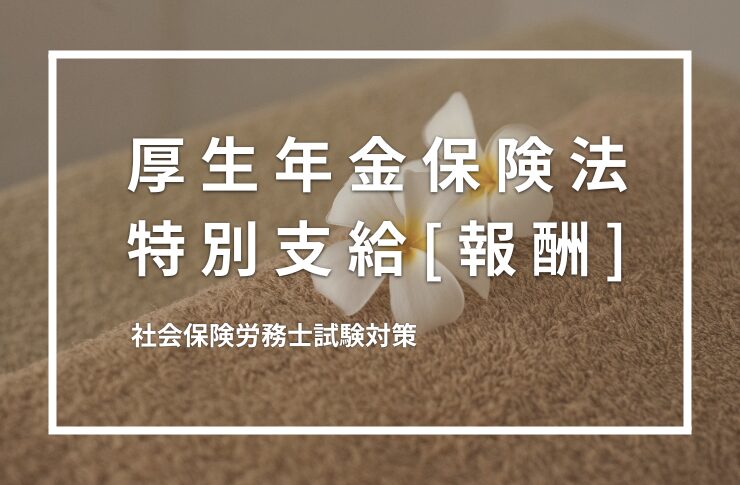厚生年金保険法の特別支給の老齢厚生年金について学習します。今回は、特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分についてみていきましょう。
以前の年金制度:国民年金と厚生年金
これまで学習してきたように、現在の年金制度は、1階部分にあたる「国民年金(基礎年金)」と、2階部分にあたる「厚生年金(報酬比例年金)」の2階建てになっています。なお、厳密には、3階以上もありますが、国民年金法と厚生年金保険法を学習する便宜上、ここでは2階建てとします。
一方、以前の年金制度は、自営業者等が加入する「国民年金」、会社員等が加入する「厚生年金」に分かれていました(わかりやすくするために「共済年金」は省略しています)。
国民年金は、現在でいうところの1階部分に相当します。これに対して、厚生年金は、1階の「定額部分」と2階の「報酬比例部分」に分かれていました。定額部分は、文字通り定額で支給されるものです。報酬比例部分は、老齢厚生年金の額で計算するようにお給料や賞与など報酬によって変わるものです。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分を理解するには、以前、厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれていたという前提をおさえることが重要になります。
現在の年金制度:基礎年金の導入(昭和60年改正)
昭和60年改正(昭和61年4月1日施行)によって、前述のように、現在の年金制度は、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金(報酬比例年金)」の2階建てになりました。この時点では、老齢基礎年金は65歳支給開始、老齢厚生年金は60歳支給開始でした。
しかし、日本は高齢化が進み、公的年金制度の持続性を確保するために、老齢厚生年金の支給開始年齢を65歳に引き上げる必要性が生じました。もっとも、60歳から支給されていた老齢厚生年金をいきなり65歳にすることは既得権の保護に欠けるため、支給開始年齢を段階的に引き上げる「特別支給の老齢厚生年金」の制度が設けられました。
平成6年改正:定額部分の支給開始年齢の引き上げ
まず、平成6年改正では、定額部分の支給開始年齢の引き上げが行われました。定額部分とは、旧法(昭和61年4月1日より前)の1階部分にあたる年金です。
本記事(動画)では、この定額部分を中心に進めます。
男子、女子(2号、3号、4号)
| 昭和16年4月1日以前に生まれた者 | 60歳 |
| 昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
男子および2号、3号、4号被保険者の女子について、「昭和16年4月1日以前に生まれた者」は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳のままとなります。「昭和16年4月2日」以降に生まれた者については、2年ごとに支給開始年齢が1歳ずつ引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者は、65歳から支給開始となります。
女子(1号)
| 昭和21年4月1日以前に生まれた者 | 60歳 |
| 昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
1号被保険者の女子について、先ほどの表から5年遅れたものになります。「昭和16年4月2日」を基準にして、1号女子はそこから5年遅いと覚えるのをおすすめします。
坑内員と船員の被保険者期間が15年以上である者
| 昭和21年4月1日以前に生まれた者 | 60歳 |
| 昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
坑内員と船員の被保険者期間を合算した期間が15年以上である者について、女子と同じく、5年遅れたものになります。
特定警察職員等
| 昭和22年4月1日以前に生まれた者 | 60歳 |
| 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和24年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和26年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
特定警察職員等について、基本から6年遅れたものになります。
特別支給の老齢厚生年金の受給権等
特別支給の老齢厚生年金の受給権等については、基本的に報酬比例部分と考え方は同じです。
以下、定額部分でおさえておきたい部分について解説します。
特別支給の老齢厚生年金の額
特別支給の老齢厚生年金の額は、次のとおりです。
また、定額部分には加給年金額が加算されます。報酬比例部分には加給年金額が加算されない点に注意しましょう。さらに、配偶者にかかる加給年金額には、受給権者の生年月日に応じて、特別加算がされます。特別加算額を覚える必要性は低いですが、受給権者の生年月日が遅いほど(年齢が若いほど)、特別加算額が大きくなるという点をおさえましょう。受給権者の生年月日が遅くなるほど、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられるため、調整措置の一環であると考えることができます。
本試験では、受給権者の生年月日によって、大きくなることを理解しているかが問われています。
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる。
(令5-7-B)
正誤:☓
また、受給権者の生年月日である点も問われています。
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
(平28-5-E)
正誤:☓
平成12年改正:報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ
次に、平成12年改正では、報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げが行われました。報酬比例部分についての詳細は、前回の記事(動画)をご覧ください。報酬比例部分は、(通常の)老齢厚生年金と同じように考えることができるため、比較的理解しやすいと思います。
なお、定額部分の支給開始年齢は、「昭和24年4月2日以降」は65歳です。一方、報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げが最初に行われるのは、「昭和28年4月2日から」です。つまり、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの4年間は、定額部分が65歳、報酬比例部分が60歳が続くことになります。表は、2年ごとになっているので、踊り場が4年あるという点に注意しましょう。