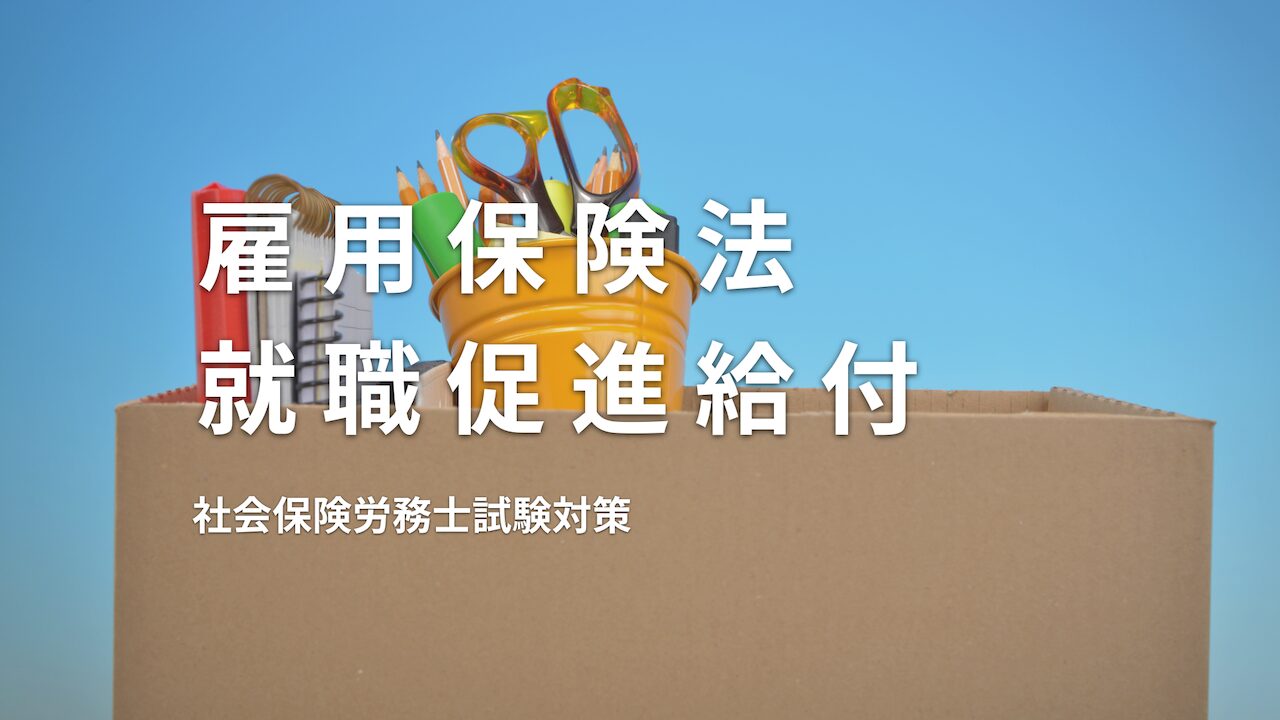雇用保険法の失業等給付から日雇労働被保険者の求職者給付について解説します。日雇労働被保険者の制度は、理解している方が少ないので、この部分で差をつけられるようにしていきましょう。
目次
日雇労働者
・日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者を除く。)をいう(42条各号)。
①日々雇用される者
②30日以内の期間を定めて雇用される者
日雇労働被保険者
・被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する(43条1項各号)。
① 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③ 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
④ 厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者
→条文がややこしく感じると思うので、整理しましょう。まず、日々雇用される者や30日以内の期間を定めて雇用される者を、雇用保険法では「日雇労働者」といいます。そして、1号から4号のいずれかに該当する日雇労働者を日雇労働被保険者といい、日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金が支給されます。日雇労働者だからといって、日雇労働被保険者ではない点をおさえましょう。
それでは、1号から4号について見ていきます。
1号について、特別区というのは、いわゆる東京23区のことです。もしくは、公共職業安定所の所在する市町村の区域、または隣接する市町村など。これらを「適用区域」といいます。公共職業安定所の所在する市町村の区域や隣接する市町村が含まれるので、かなり広範囲であることがわかります。そして、適用区域に居住し、適用事業に雇用される者。適用事業は、雇用保険の適用事業です。
2号について、適用区域外の地域に居住して、適用区域内にある適用事業に雇用される者。住んでいるのは、適用区域外だけれど、適用区域で働いている者ということです。
3号について、適用区域外の地域に居住して、適用区域外の地域にある適用事業であっても、厚生労働大臣が指定したものに雇用される者は、日雇労働被保険者になります。「厚生労働大臣が指定したものに雇用される者」については、本試験対策として割愛します。
4号について、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者。これは、次項の日雇労働被保険者に任意加入の申請をしたものです。
・日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる(43条2項)。
→読みにくいので補足します。日雇労働者の定義として、「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者を除く。」と定められています(42条括弧書)。そして、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者と同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者は、一般被保険者等になります。ただ、これらの場合でも、公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができます。
日雇労働被保険者手帳
・日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない(44条)。
日雇労働求職者給付金の受給資格
・日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給する(45条)。
→日雇労働被保険者は、働いた日ごとに日雇労働被保険者手帳に印紙を貼ってもらいます。適用事業者は、この印紙によって印紙保険料を納付していることになります。この印紙保険料が通算して26日分以上納付されているとき、つまり26枚以上印紙が貼られているときに、日雇労働求職者給付金が支給されます。
日雇労働被保険者に係る失業の認定
・日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日について支給する(47条1項)。
・失業の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない(47条2項)。
日雇労働求職者給付金の日額
・日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする(48条1項)。
→日雇労働求職者給付金の日額が細かく規定されていますが、本試験対策としては、等級ごとに給付金が異なっているということを押さえておきましょう。
①第1級給付金 7,500円
②第2級給付金 6,200円
③第3級給付金 4,100円
なお、等級については、印紙ごとに「第1級印紙保険料」「第2級印紙保険料」「第3級印紙保険料」のように決められており、これらの印紙の枚数によって給付金の等級が定められています。賃金が高い仕事であれば「第1級印紙保険料」が納付され、それに伴い、給付金が高くなるという仕組みです。
日雇労働求職者給付金の支給日数等
・日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない(50条1項)。
→日雇労働のところでわかりにくいところなので、補足します。まず、日雇労働求職者給付金は、失業の日の属する月の前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給されます(45条)。2箇月の間に26日ということは、1箇月で13日、週3日ほど働いている計算になります。
ここから、支給日数を考えてみましょう。基本的には通算して13日分を限度として支給します。ただ、それ以上働いている方もいる場合があるので、そのときは、28日を超える4日分ごとに1日を加えていきます。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給されません。週4日より多く働いている分は支給されないイメージを持っておくとわかりやすいと思います。
雇用保険は、労働者の生活の安定を図ることが目的のひとつですが、必要分以上の給付金を支給をすると、労働する意欲が低下してしまう危険性があります。そのため、ある程度の制限がされています。
・日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、支給しない(50条2項)。
→日雇労働求職者給付金も待機の概念があります。ただ、一般被保険者に支給される基本手当が通算して7日間であったのに対して、日雇労働求職者給付金は、各週につき、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日に支給されないとされています。たとえば、その週の火、木、金、土で職業に就かなかった場合、火曜日は支給されないということです。次は、木曜日に公共職業安定所に出頭して、支給を受けることになります。
日雇労働求職者給付金の支給方法等
・日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行った日に支給するものとする(51条1項)。
給付制限
・日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない(52条1項)。
① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
③ 同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に紹介されたとき(職業安定法20条)。
④ その他正当な理由があるとき。
→日雇労働求職者給付金の支給においても、給付制限について規定されています。ただ、一般被保険者の基本手当が1箇月間の給付制限であるのに対して、日雇労働求職者給付金は7日間と短くなっているのが特徴です。これは、日雇労働被保険者は蓄えが少ないことが予想されるため、1箇月も給付制限をされると生活できなくなってしまうからです。
・日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる(52条3項)。
→こちらも同様に、一般被保険者の基本手当は、「以後、支給しない」のに対して、日雇労働求職者給付金は3箇月間と短くなっています。また、給付制限は、その月と翌月から3箇月間なので、合計で4箇月間となります。
日雇労働求職者給付金の特例
・日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる(53条1項)。
① 継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。
② 継続する6月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
③ 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
→日雇労働求職者給付金の特例は、普通給付、特例給付のように書かれていたり、表を丸暗記させられてしまう部分のひとつです。日雇労働求職者給付金は、前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されます。ただ、さまざまな事情があり、条件を満たすことができなかったという方もいらっしゃると思います。そこで、各月11日分以上、かつ通算して78日分以上納付されていれば、特例として日雇労働求職者給付金が支給されるようになっています。6月間に78日分以上なので、1箇月あたりにすると13日分以上で同じであることがわかります。
他の条件として、継続する6月間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金の支給を受けていないことがあります。おそらく、多くの基本書は、ここに特例が混ざって書かれており、「どっちだっけ」となってしまう方が多いと思います。条文は、特例については、ここでは一切触れていません。「6月間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金の支給を受けていない」という表現が難しく感じると思いますが、日雇労働求職者給付金は前2月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されるので、最初の1月だけでは成立することはそもそも不可能です。そのため、成立し得る後の5月間について、日雇労働求職者給付金の支給を受けていないという条件を定めています。
さらに、最後の月の翌月以後2月間に日雇労働求職者給付金の支給を受けていないことも必要です。
・申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない(53条2項)。
→先ほど、「最後の月の翌月以後2月間に日雇労働求職者給付金の支給を受けていない」とありましたが、申出は基礎期間の最後の月の翌月以後であればすることはできます。たとえば、3月から8月までの6月間を基礎期間とすると、9月から12月まで申出ができるということです。
・前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる(54条)。
① 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。
② 日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
※省略(48条1項参照)
→日額については、前述の日雇労働求職者給付金と同じです。同じものを特例として支給するので、まったく別のものであると考えないようにしましょう。
・基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に日雇労働求職者給付金の特例の申出をした者については、当該2月を経過する日までは、日雇労働求職者給付金は、支給しない(55条1項)。
→日雇労働求職者給付金の特例の申出をした者は、二重で日雇労働求職者給付金を受給できないように制限されています。たとえば、3月から8月までの6月間を基礎期間とした場合、9月、10月の2月の期間内に日雇労働求職者給付金の特例の申出をした者については、この2月を経過する日までは、日雇労働求職者給付金は、支給しないということです。
・前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項[日雇労働求職者給付金の特例]の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については、その者は、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす(55条3項)。
→多くの基本書は、53条1項と55条3項を合わせて図表などで表しているため、初学の方は言っている意味がわからなくなってしまいます。整理すると、特例による日雇労働求職者給付金を受けた者が、日雇労働求職者給付金の特例の申出をする場合、「後の5月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。」の適用については、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなされます。ここは、通常や特例など考えるのではなく、後の5月間や基礎期間の翌月後2月間に日雇労働求職者給付金を受けた方は重複して受けられないと押さえるようにしましょう。
そして、繰り返しますが、日雇労働求職者給付金の特例は、別のボーナスのようなものが支給されるといったものではなく、あくまで日雇労働求職者給付金の支給が受けられなかった方が、特例として支給を受けることができる制度であると捉えましょう。