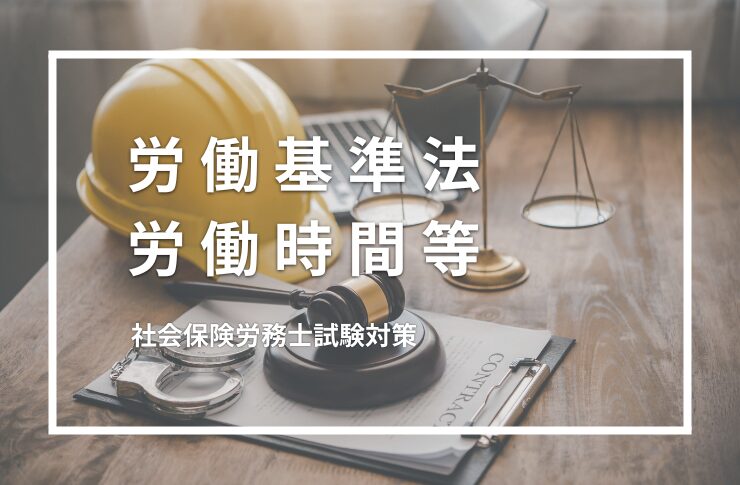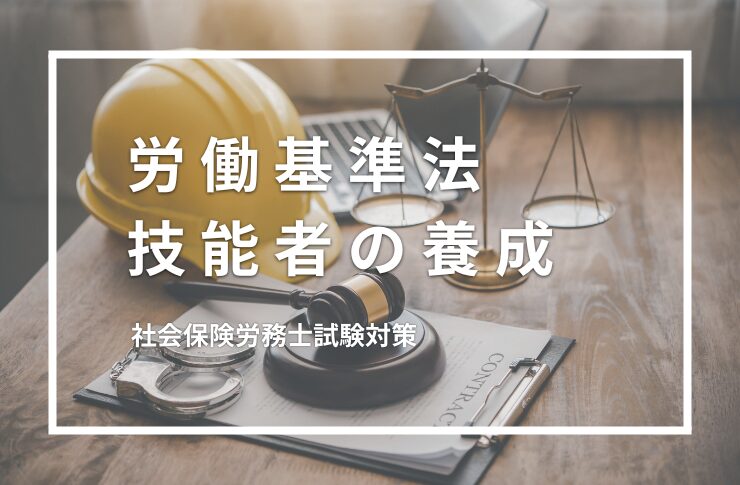労働基準法の妊産婦等について学習します。妊産婦「等」となっているのは、本章において、妊産婦だけでなく、妊産婦でない女性の「就業制限」や「生理休暇」についても規定しているからです。
妊産婦等の就業制限は、妊婦と産婦を逆に覚えてしまうなど、暗記要素で乗り切ろうとすると疲弊してしまいます。ここでは、できるだけ価値判断を持って対応できるように努めます。
坑内業務の就業制限
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない(64条の2)。
①妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
②満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
原則として、女性の坑内労働は禁止されています。それは、坑内労働の多くは、筋肉労働であるからです。ここで、坑内労働についてみてみましょう。坑内労働には、大きく「鉱山における坑内労働」と「鉱山以外における坑内労働」があります。現在、坑内労働の大半は鉱山以外のものです。また、技術の向上や機械化の進展等により筋肉労働の比率は低下してきています。
そこで、女性技術者が増加してきていること、筋肉労働が減少してきている背景から、坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務に限り、18歳以上の女性は業務が禁止されています。
もっとも、妊産婦については、母性保護の観点から、十分な配慮が必要だと考えられています。そこで、妊娠中の女性は坑内労働が禁止されています。そして、産後1年を経過しない女性は業務に従事しない旨を使用者に申し出たときは坑内労働が禁止されます。
なお、「18歳以上の女性」とされていることから、18歳未満の女性の坑内労働について疑問に感じる方もいるかもしれません。年少者については、「使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない」(63条)として、保護しています。
危険有害業務の就業制限
妊産婦とは、妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性のことをいいます。
坑内労働は、ガスや地下水の流出、落石、落盤等の労働災害の可能性があります。しかし、これは女性に限ったことではなく、男女双方に共通した危険性です。また、労働安全衛生法によって高い安全衛生の確保が図れるようになったため、女性の坑内労働を一律に禁止する事情は乏しくなってきています。
もっとも、妊産婦については、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散するなど、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就くことは禁止されています。先ほどの坑内労働は、筋肉労働が多いことが理由だったため、妊婦、そして申し出た産婦が対象でした。危険有害業務は、妊娠、出産、哺育等に有害なため、妊婦も産婦も就業が禁止されています。この背景をおさえておくことが大切になります。
参考「厚生労働省:女性の坑内労働に係る専門家会合第4回資料」
産前産後
出産が近づいている女性のための規定です。
通達を確認しましょう。
・出産とは妊娠4か月(1か月は28日として計算する。したがって4か月以上というのは85日以上のことである。)の分娩とする(昭23.12.23基発1885号)。
・生産のみならず死産(人口妊娠中絶は含まれる。)も含む(昭26.4.2婦発113号)。
・出産当日は産前6か月に含まれる(昭25.3.31基収4057号)。
・6週間以内に出産する予定の女性労動者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、法第19条の解雇制限期間にならない(昭25.6.16基収1526号)。
母体保護のため、産後8週間は就業してはいけないことになっています。ただし、6週間を経過した女性については、医師が支障がないと認めたときは働けるようになっています。
産前と産後は、産前が請求で、産後が絶対禁止です。先ほどの坑内業務は、産前が絶対で産後が請求で逆になっています。暗記をしようとすると混乱してしまうので、背景から理解するようにしましょう。
・新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない(昭61.3.20基発151号ほか)。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない(66条1項)。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等並びに三六協定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない(66条2項)。
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(66条3項)。
妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間制、臨時の必要がある場合の時間外労働等、三六協定、深夜業などをしてはならないということです。
なお、応用論点ですが、「労働時間等に関する規定の適用除外」(41条)と「高度プロフェッショナル制度」(41条の2)は、適用されます。41条は、農業、水産、養蚕、畜産業に掲げる事業に従事する者、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者などの労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないというものです。これらと高プロについては、妊産婦であっても、労働時間が長くなったり、休日でも働く可能性ががあるということです。
育児時間
授乳の時間と考えるとわかりやすいと思います。
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
・生理日の就業が著しく困難かどうかについては、生理休暇の実質的確保のため、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば充分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるようにすること(昭23.5.5基発682号)。
いわゆる生理休暇です。休暇の請求は、時間単位での請求もできます。生理による苦痛の程度等は個人によって異なるものであるため、就業規則その他により生理休暇の日数を限定することは許されていません。