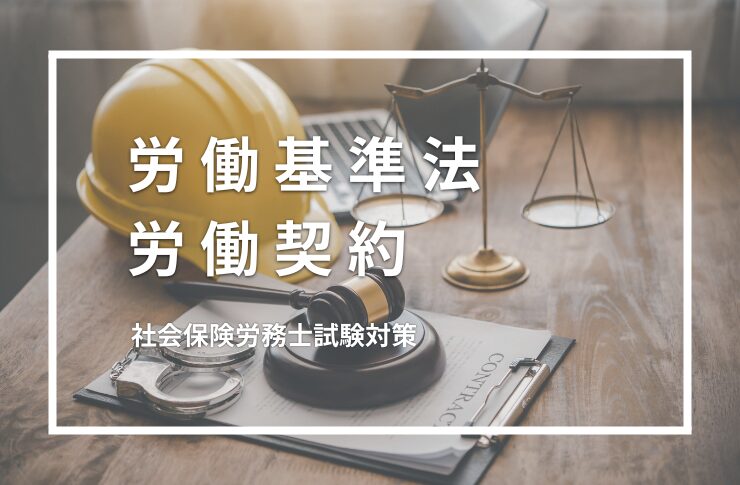ここでは、労働基準法の総則について学習します。労働基準法は、条文だけでなく、判例や通達からも多く出題されるため、これらもおさえておく必要があります。
また、社会保険労務士の試験は選択式があり、条文や判例の文言がそのまま出題されるので、できるだけ条文や判例の言い回しに慣れておくようにしましょう。そのため、ここでは、条文や判例などについては常体で進めます(補足の部分は敬体で掲載しています)。
労働条件の原則
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない(1条1項)。
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない(1条2項)。
「人たるに値する生活」とは、その標準家族の生活をも含めて考えること(昭22.9.13発基17号、昭22.11.27基発401号)。
「労働条件を低下」とは、この法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて認定し、経済諸条件の変動に伴うものは本条に抵触するものではない(昭63.3.14基発150号)。
ここで、「発基」や「基発」について解説します。上位の行政機関が下位の行政機関に対して出す通知を「通達」といいます。そして、通達のうち、事務次官による通達を「発基」、労働基準局長による通達を「基発」といいます。通達は、条文を解釈する上で重要であり、本試験では頻出のため、理解記憶するようにしましょう。
労働条件の決定
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである(2条1項)。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない(2条2項)。
ここで、労働協約等について、補足します。
- 労働協約:労働組合と使用者またはその団体との間に結ばれる協定
- 就業規則:労働条件に関することなどについて定めた職場における規則集
- 労働契約:個々の労働者と使用者が結んだ契約
それぞれの上下関係を表すと、「法令(強行法規)>労働協約>就業規則>労働契約」の順番になります。
均等待遇
「信条」とは、特定の宗教的もしくは政治的信念をいい、「社会的身分」とは生来の身分をいう(昭22.9.13発基17号)。
ここで、判例をみてみましょう。「判例」とは、一般的に最高裁判所の示した判断のことをいいます(下級審の場合は「裁判例」と表記されることが多いです)。
学生運動に参加していたことを隠して採用された新卒の労働者が、試用期間満了後に本採用を拒否された事案について、判例は、次のように述べました。
憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。憲法14条の規定が私人のこのような行為を直接禁止するものでないことは前記のとおりであり、また、労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない(最判昭48.12.12 三菱樹脂事件)。
本試験において、労働基準法からは判例問題が出題されることがあります。裁判というと勝った負けたということに意識が向いてしまいそうですが、法律学の試験では事件そのものの結果ではなく、その論点について、どのような理由でどのような結果になったのかが問われます。たとえば、今回の判例は、「労働基準法3条は、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない」という点をおさえます。
本試験ではこの点について、出題されています。
「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。(令6-1-B)
正誤:☓
男女同一賃金の原則
差別的取扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず、有利に取扱う場合も含む(平9.9.25基発648号)。
就業規則に差別待遇の規定あるのみで、差別の事実なきときは違反とならぬが、その就業規則の規定は無効(平9.9.25基発648号)。
強制労働の禁止
強制労働の禁止は、あとで学習しますが、労働基準法でもっとも重い罰則が科せられます。
中間搾取の排除
労働者派遣は、該当しない(平11.3.31基発168号)。
公民権行使の保障
有給たると無給たるとは当事者の自由(昭22.11.27基発399号)。
公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めたことにより、労動者の就業時間中の選挙権行使請求を拒否すれば違法(昭23.10.30基発1575号)。
公民権行使の保障は、公民権、つまり選挙権や被選挙権を行使することを保障するものなので、働いていない時間について、有給にするか無給にするかは当事者の自由となります。
定義
労働者
用語の定義について、さまざまな通達が出ているのでみていきましょう。
法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて本条の労働者である(昭23.3.17基発461号)。
一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労動者に該当しない。直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、労動者に該当する(平9.9.18基発636号)。
いわゆる芸能タレントの労動者性については、次のいずれにも該当する場合は、本条の労動者ではない。
①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
④契約形態が雇用契約ではないこと。(昭63.7.30基収355)。
※基収:各都道府県労働局長からの問い合わせに対する労働基準局長による回答。
労動者について、選択式で出題された判例を確認しましょう。
最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。
そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」
※太字になっている部分が、選択式で問われた部分です。
使用者
「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる権限なく単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とはみなされない(昭22.9.13発基17号)。
出向とは、出向元と何らかの労働関係を保ちながら、出向先との間において新たな労働契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であり、在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で本法等の適用がある。また、移籍型出向の出向労動者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ本法等の適用がある(昭61.6.6基発333号)。
賃金
賃金について、通達を確認しましょう。
労動者に支給される物又は利益にして以下の各号の一に該当するものは賃金とみなす。
① 所定貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ちその支給により貨幣賃金の減額を伴うもの
② 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されているもの。
右に掲げるものであっても以下の各号の一に該当するものは賃金とみなさない。
① 代金を徴収するもの、但しその代金がはなはだしく低額なものはこのかぎりでない。
② 労動者の福利厚生施設とみなされるもの。
労働協約、就業規則、労働契約等により、予め支給条件が明確である場合の退職手当は本条の賃金である。
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさない。但し結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金である(昭22.9.13発基17号)。
ストックオプションとは、かんたんにいうと、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利のことをいいます。
平均賃金
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(12条1項本文)。
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する(12条2項)。
ここでは、平均賃金の算定方法を確認しておきましょう。
前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する(12条3項)。
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④ 育児休業、介護休業をした期間
⑤ 試みの使用期間
平均賃金の額は、解雇予告手当などに使われます。このとき、労働災害や産休などによって休業した期間と賃金を計算に入れると、不当に平均賃金が低くなってしまうため、これらの期間と賃金は控除することになっています。私は、「ぎょう・さん・し・いく(を)・こころみろ」というゴロを教えてもらいました(LECの澤井先生です)。
賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない(12条4項)。
今度は反対に、賞与などを含めると、平均賃金が不当に高くなってしまうため、これらは賃金の総額に算入しないことになっています。減るものも増えるものも平均から乖離するようなものは除外されると考えると、全体像がつかみやすいと思います。