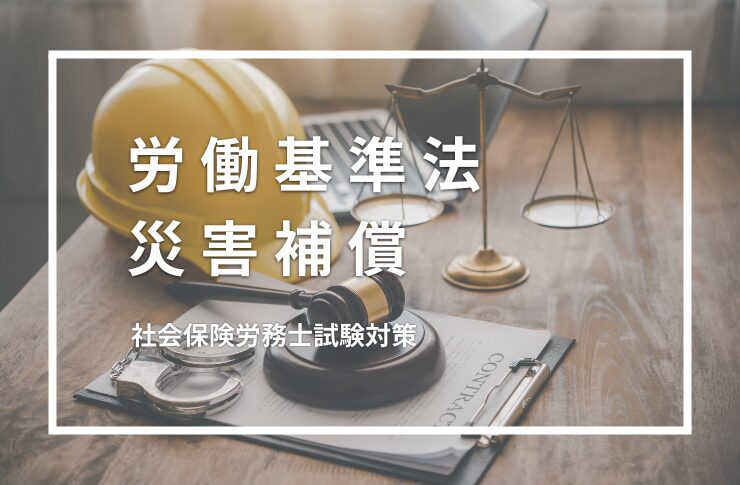ここでは、労働基準法の労働契約について学習します。
この法律違反の契約
労働基準法で定める基準に達しない労働条件は無効となり、無効となった部分は、労働基準法で定める基準になります。すべてが無効になるわけではないので注意しましょう。
契約期間等
① 専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
期間の定めのないもの、いわゆる会社員やパート・アルバイトとして働く場合を除いて、辞めたいのに辞められない状況をなくすために、建設工事など一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、労働契約は、原則3年までとされています。
1号について、社会保険労務士など専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約は、5年までとされています。カッコ書きにあるように、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。社労士であっても別の業務に就く場合は3年までとなります。
2号について、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、5年までとされています。高齢になると仕事を探すのも大変と考えると、納得しやすいと思います。
厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる(14条2項)。
行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる(14条3項)。
厚生労働大臣は、雇止めについての紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項等についての基準を定めることができます。
労働条件の明示
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない(15条1項)。
これを「絶対的明示事項」といいます。絶対的明示事項は本試験で頻出のため、規則を確認しましょう。
① 労働契約の期間に関する事項
①の② 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
①の③ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
② 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
③ 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
④ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる(15条2項)。
就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない(15条3項)。
14日以内に帰郷ということは、その就業のためにわざわざ引っ越してきたということです。労働条件が違うから帰郷する(故郷に帰る)ときは、労働者に帰責事由がないので、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
賠償予定の禁止
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定するのは禁止されています。もっとも、実際に生じた損害について損害賠償を請求することは禁止されていません。
前借金相殺の禁止
前借金でも貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、本条の規定は適用されない(昭63.3.14基発150号)。
前借金とは、労働することを条件として、労働者に前渡ししておく金銭で、労働者の賃金から差し引かれるものをいいます。辞められない状況をなくすために、使用者からの前借金や前貸の債権と賃金の相殺が禁止されています。労働者側から信用に基づいてお金を借りることは禁止されていません。「労働すること」が条件となっているかで判断するようにしましょう。
強制貯金
いわゆる強制貯蓄は禁止されています。
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁[所轄労働基準監督署長]に届け出なければならない(18条2項、規則6条)。
労働基準法において、「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」という表現が出てきます。これが労使協定です。
任意貯蓄をする場合は、労使協定を締結し、行政官庁に届け出る等の措置をとる必要があります。
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない(18条3項)。
使用者は、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす(18条4項)。
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない(18条5項)。
解雇制限
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない(19条1項)。
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁[所轄労働基準監督署長]の認定を受けなければならない。(19条2項、規則7条)。
解雇制限について整理しましょう。
原則、以下の期間は解雇制限があります。
- 業務上傷病の療養休業期間+30日間
- 産前産後の休業期間+30日間
ただし、例外が規定されています。
- 打切補償を支払う場合
- 事業の継続が不可能となった場合
もっとも、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」というのは幅広いため、どのような状況なのか行政官庁の認定を受けなければなりません。
解雇制限について、選択式で出題された判例を確認しましょう。
最高裁判所は、労働基準法第19条第1項の解雇制限が解除されるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法〔労働基準法〕において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法〔労災保険法〕に基づく保険給付が行われている場合とで、同項〔労働基準法第19条第1項〕ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には打切補償として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」
(最判平27.6.8 専修大学事件)
解雇の予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない(20条1項)。
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる(20条2項)。
前条第2項(行政官庁の認定)の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する(20条3項)。
「事業の継続が不可能となった場合」とは事業の全部又は大部分の継続が不可能となった場合をいう。一般に事業経営上の見通しの齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由は「やむを得ない事由」に該当しない(昭63.3.14基発150号)。
労働者が次の仕事を見つけられるように、使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならないことになっています。もし、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払います。こうすることで、労働者の生活の安全が保障されます。
ただし、例外が規定されています。
- 事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
これらの場合は、解雇の予告をしなくてもよいことになります。もっとも、これらの場合、どの程度であるか行政官庁の認定を受ける必要があります。
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。たとえば、10日分の平均賃金を支払った場合は、10日分を短縮することができ、20日前までに予告すればよいことになります。つまり、予告の日数と平均賃金を支払った日数を合計して30日分以上あればよいということです。労働者が次の仕事を見つける期間を保障するというのを意識しましょう。
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない(21条)。
① 日日雇い入れられる者
② 2箇月以内の期間を定めて使用される者
③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④ 試の使用期間中の者
短期間働く労動者に対しては、解雇予告が必要ではないとされています。ただし、一定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、この限りでない、つまり解雇予告が必要になります。
- 日日雇い入れられる者(1か月)
- 2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間)
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間)
- 試の使用期間中の者(14日)
退職時等の証明
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない(22条1項)。
証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない(22条3項)。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は証明書に秘密の記号を記入してはならない(22条4項)。
「国籍、信条、社会的身分、労働組合運動」は制限的列挙であって、例示でない(昭22.12.15基発502号)。
3項、4項について、労働者が次の仕事を探すのに不利益になるようなことをしてはならないということを考えるとわかりやすいと思います。
金品の返還
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない(23条1項)。
賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない(23条2項)。
原則として賃金や金品等は、権利者の請求があった場合は、7日以内に支払い、又は返還しなければならず、争いがある場合も異議のない部分を7日以内に支払い、または返還しなければならないということです。なお、賃金については「支払」、金品等は「返還」という言葉が使われています。