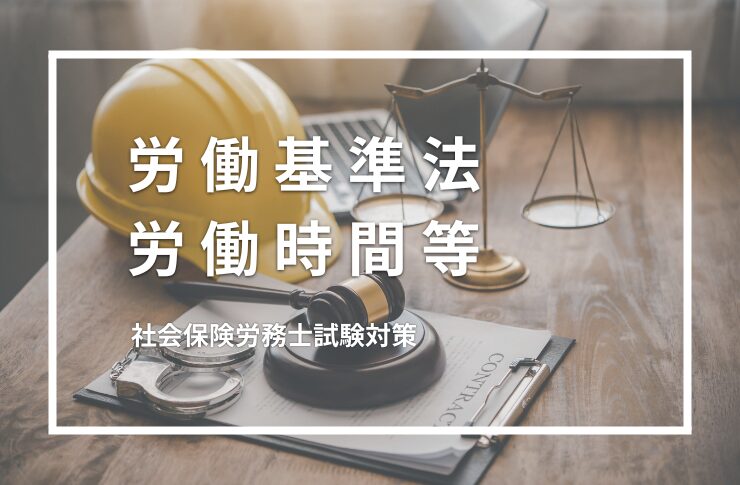ここでは、労働基準法の賃金について学習します。賃金の定義については、「総則」をご参照ください。
賃金の支払
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる(24条1項)。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時の賃金等については、この限りでない(24条2項)。
①通貨で、②直接、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払うことを「賃金の支払の5原則」といいます。もっとも、重要なのは用語ではなく内容なので、みていきましょう。
まず、賃金は、通貨で支払わなければなりません。お米などの現物で支給されても困ることを考えるとわかりやすいと思います。
ただし、通貨以外のもので支払うことができる例外が規定されています。
- 法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合
- 確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
法令について、現在のところはありません。労働協約について、通勤定期券などを想像するとわかりやすいと思います。
「確実な支払の方法」というのは、預貯金への振込み、デジタル払いです。
次に、直接労動者に支払う必要があります。
「使者」というのは、他人が決定した意思表示を伝達する者、又は他人が決定した意思を相手方に表示する者のことをいいます。お金を届ける者であれば差し支えないということです。一方、自ら独立の意思表示をする代理人に支払うことは無効とされています。
直接払いには判例があるのでみておきましょう。
国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第11条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第24条第1項本文の規定が適用または準用される。
右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない(最判昭43.3.12)。
賃金は、全額を支払わなければなりません。
ただし、賃金の一部を控除して支払うことができる例外があります。
- 法令に別段の定めがある場合
- 労使協定がある場合
全額払いは、通貨で支払うより一段階下がり、法令または労使協定となっています。通貨で支払うことについては「法令若しくは労働協約」となっていたことと比較しましょう。
法令では、所得税などの源泉徴収、社会保険料などの源泉控除、労使協定では労働組合費等が定められています。
本試験では、通貨払いと全額払いの条件を入れ替えて問われています。
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。(令元-5-A)
正誤:☓
賃金計算の端数の取扱いについて、通達を確認しましょう。
賃金の過払調整や賃金の放棄の意思表示等について、判例を確認しましょう。
賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない(最判昭44.12.18)。
ストライキの場合における家族手当の削減が昭和23年ころから昭和44年までは就業規則の規定に基づいて実施されており、その後右規定が削除され同様の規定が社員賃金規則細部取扱のうちに定められてからも従前の取扱が引続き異議なく行われてきたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、ストライキの場合における家族手当の削減は労使間の労働慣行として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえない(最判昭56.9.18)。
また、賃金について、選択式でも出題されています。
最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
(最判昭48.1.19 シンガー・ソーイング・メシーン事件)
非常時払
お給料日前でも非常の場合は、賃金を支払う必要があるということです。なお、既往の労働に対する賃金なので、労務の提供のない部分については、支払う必要はありません。
休業手当
使用者の責に帰すべき事由による休業には、経営障害などがあります。一方、使用者の責に帰すべき事由によらない休業には、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)による休業などがあります。
本試験では、「使用者の責に帰すべき事由」かが問われるので、判例や通達を確認しておきましょう。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
定期航空運輸事業を営む会社に職業安定法44条違反の疑いがあったことから、労働組合がその改善を要求して部分ストライキを行った場合であっても、同社がストライキに先立ち、労働組合の要求を一部受け入れ、一応首肯しうる改善案を発表したのに対し、労働組合がもっぱら自らの判断によって当初からの要求の貫徹を目指してストライキを決行したなど判示の事情があるときは、右ストライキにより労働組合所属のストライキ不参加労働者の労働が社会観念上無価値となったため同社が右不参加労働者に対して命じた休業は、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものということができない(最判昭62.7.17 ノースウェスト航空事件)。
出来高払制の保障給
最低賃金
参考:賃金関係|厚生労働省