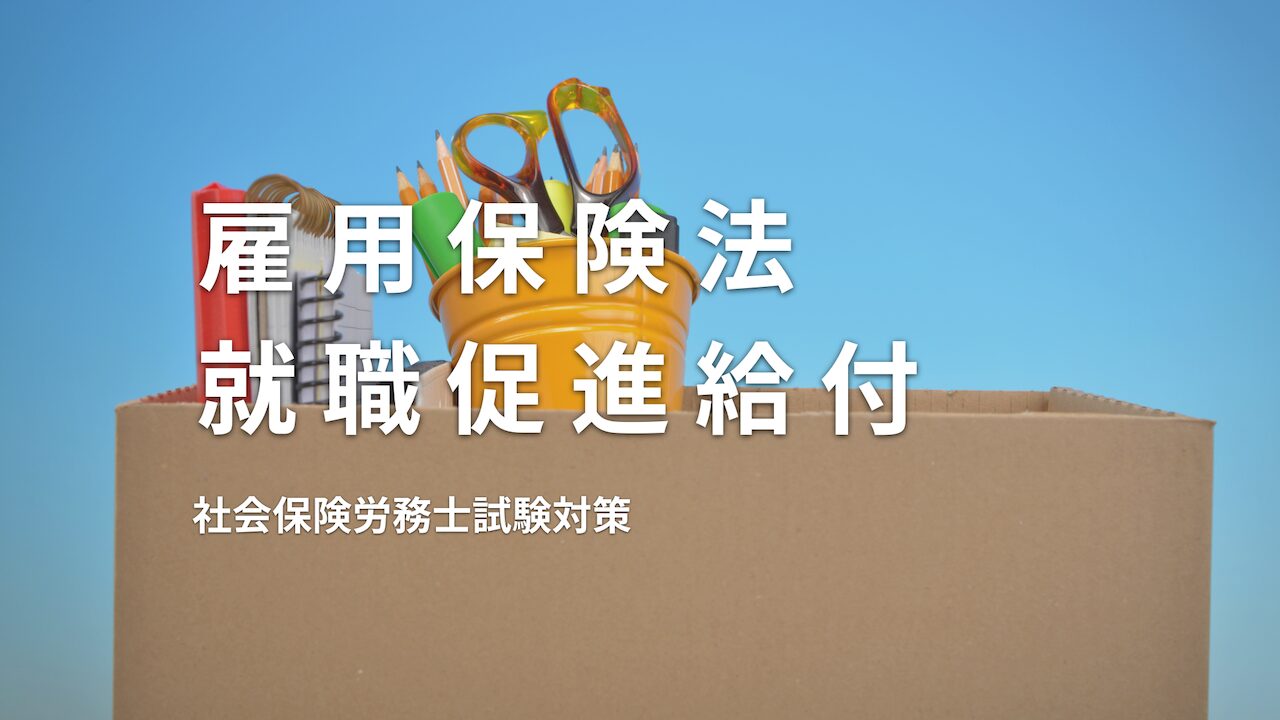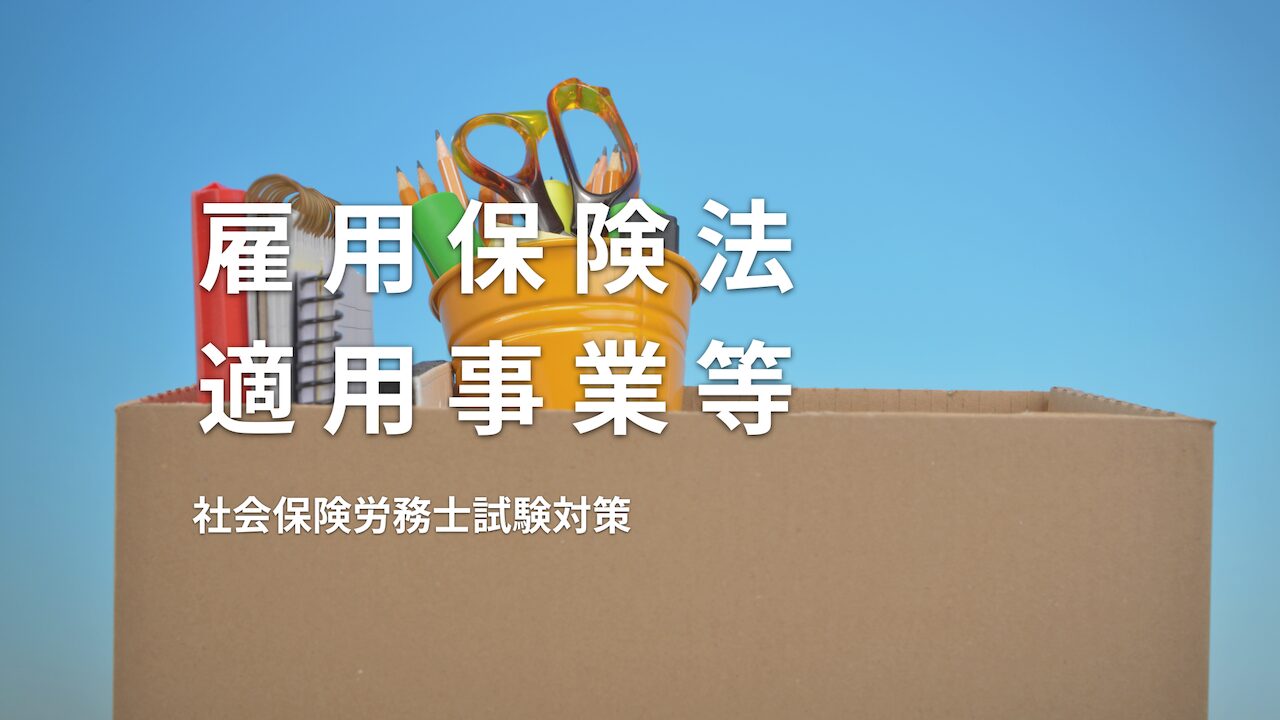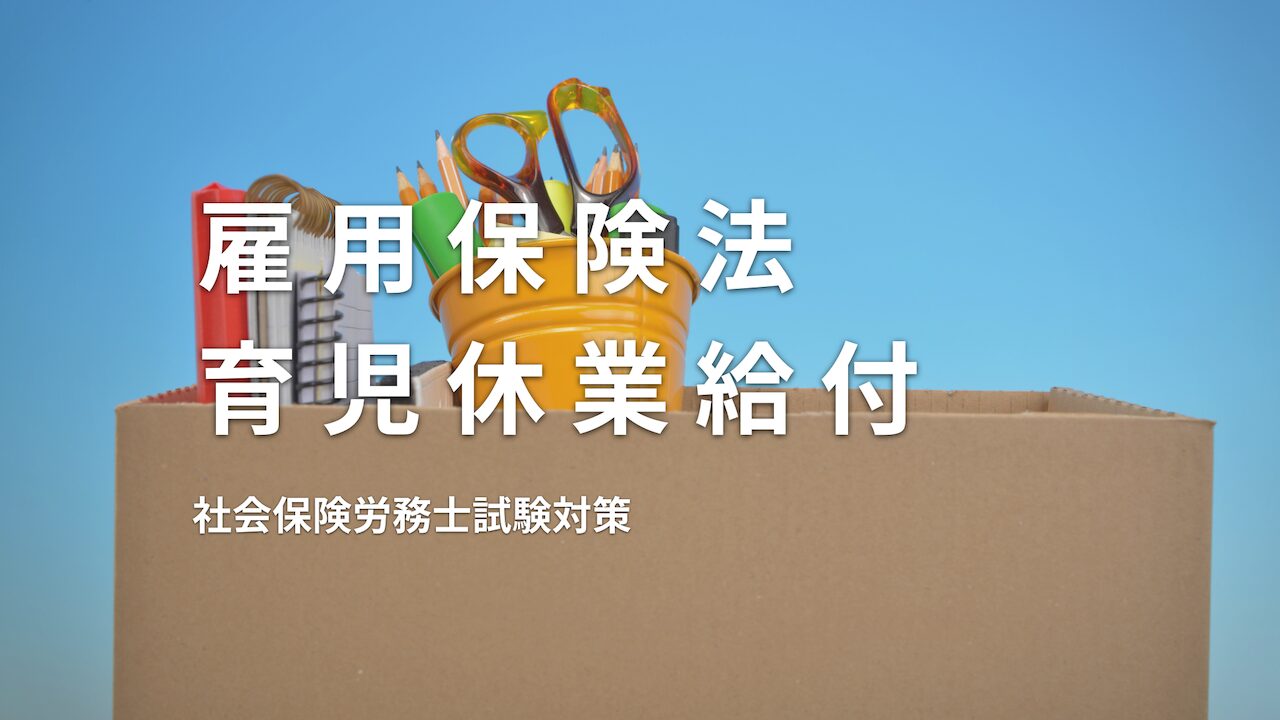※現在リライト中です。
雇用保険法の失業等給付から雇用継続給付について解説します。雇用継続給付は、失業等給付のひとつです。そして、雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付と介護休業給付の2つに分けられます。さらに、高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金に分けられます。それぞれ見ていきましょう。
第1款 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない(61条1項)。
① 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日を基準日とみなして算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
② 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、356,400円(以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう(61条2項)。
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、支給されます。
かんたんに言うと、高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支払われた月のお給料が、75%未満になった場合に、支給されます。これが1項の部分です。
そして、支給されるのは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月です。これが2項の部分です。
つまり、高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から65歳までの間にお給料が下がってしまったときに支給されるものです。
ここまで見るとわかるように、高年齢雇用継続基本給付金は、一般的にお給料が下がりやすい60歳から老齢年金が支給される65歳までの間の労働者の生活の安定を図るためのものといえます。
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる(行政手引20555)。
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない(行政手引59301)。
受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる(行政手引59021)。
ここから、もう少し詳しく条文を見ていきましょう。
みなし賃金日額とは、被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいいます。
ここで、なぜ「みなし」という言葉が入っているか疑問に感じる方がいると思うので補則します。
「賃金日額は、算定対象期間(離職の日以前2年間)において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。」(17条1項)
高年齢雇用継続基本給付金に出てくる被保険者は、離職はしてません。離職をしているわけではないので、「離職の日以前2年間」という概念がありません。よって賃金日額が算定できないことになります。そこで、60歳に達した日を離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額を「みなし賃金日額」としています。
そして、このみなし賃金日額に30を乗じて得た額(これが1箇月分のお給料に相当します)の100分の75に相当する額を下るに至った場合、つまり、1箇月分のお給料の100分の75未満になったときに、支給されます。
ただし、これには例外が定められています。
① 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日を基準日とみなして算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないとき。
被保険者を受給資格者と(これも被保険者は離職したわけではないので、受給資格者となるわけではないのでみなしています)、被保険者が60歳に達した日を基準日(離職日)とみなして算定されることとなる期間に相当する期間が、5年に満たないときは、支給されません。
かんたんに言うと、被保険者になってから、60歳に達した日まで5年必要であるということです。具体的には、最短で56歳から60歳まで働いていると対象になるということです。
「又は」のあとが読みにくいと思いますが、支給対象月は、「被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月」のことをいいます(61条2項)。この支給対象月において、その日(基準日)に応答する(該当する)日、たとえば4月15日に60歳になったのなら、それより後の各月の15日を基準日とします。
条文だと難しく感じますが、各月の基準日において5年に満たないときは支給されないということです。反対にいうと、各月の基準日において、5年になったらその月から支給されるということです。具体的には、58歳3か月のときに被保険者になった方は、62歳3か月のときから65歳になるまで高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
そして、みなし賃金日額の括弧書きにあった「(当該被保険者が第1号に該当しなくなったときは、同号に該当しなくなった日)」は、1号に該当しなくなった(「5年に満たないとき」に該当しなくなった)、つまり、5年以上になったときは、該当しなくなった日を離職の日とみなします。
② 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、356,400円(支給限度額)以上であるとき。
十分なお給料をもらっているのであれば、75%未満になっても生活できるということです。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする(61条5項)。
① 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき。 100分の10
② 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が賃金日額の下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない(61条6項)。
みなし賃金額(行政手引59143)
イ 賃金の範囲については、賃金証明書に記載する賃金の範囲と同様であるが、雇用月において、ロに掲げる理由により賃金の減額の対象となった日がある場合は、実際に支給された賃金額に、当該減額の対象となった日について賃金の減額が行われなかったものとみなして割戻しにより算定した賃金額をあわせたものを、当該雇用月のみなし賃金額とすること。
ロ この場合のみなし賃金額の算定における割戻しの対象となるのは、以下に掲げる理由により賃
金の減額を受けた日をいう。
(イ) 受給資格者の非行等
受給資格者の責めに帰すべき理由により賃金の減額が行われた日がある場合である。すなわち、受給資格者の非行により事業主から懲戒を受け賃金が減額された場合及び受給資格者が無断欠勤したことにより賃金が減額された場合のみならず、冠婚葬祭等受給資格者の私事により1 日あるいは一定時間について欠勤した場合も含む。
高年齢雇用継続基本給付金については、支給申請手続が問われるのでおさえておきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金については、被保険者は働いているため、公共職業安定所の長は、被保険者の賃金については把握していません。そのため、「60歳到達時等賃金証明書」が必要になります。
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない(61条の2第1項)。
① 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
② 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である同項の被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう(61条の2第2項)。
前条第5項及び第6項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する(61条の2第3項)。
先ほどの高年齢雇用継続基本給付金は、働いていて60歳以上になって、お給料が下がったときに支給されるものでした。一方、高年齢再就職給付金は、受給資格者(つまり離職している方です)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、お給料が以前と比較して100分の75に相当する額を下回ったときに、支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金は60歳以降も継続して働いている方、高年齢再就職給付金は離職して60歳以後に再就職した方が対象です。
- 高年齢雇用継続基本給付金:継続して働いている
- 高年齢再就職給付金:離職して再就職した
どちらもお給料が以前と比較して100分の75を下回ったときに支給される点は共通しています。この2つのシチュエーションの違いはおさえておきましょう。
高年齢再就職給付金の対象となる方は、離職しているので、「みなす」といったことまわりくどいことはせず、「受給資格者」となります。
ただ、以下の方はこの限りでない、つまり支給されません。
① 就職日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。
1号について、高年齢再就職給付金は、支給残日数が100日以上ある方が対象です。
② 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
2号について、十分生活できる方も対象外となります。
再就職後の支給対象月は、就職日の前日における支給残日数によって分けられています。
- 200日未満:1年を経過する日の属する月
- 200日以上:2年を経過する日の属する月
これらの月が、65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までとなります。たとえば、63歳6か月のときに支給残日数を200日以上残して再就職した場合、2年を経過する日の属する月は65歳6か月ですが、65歳に達する日の属する月までとなります。高年齢雇用継続給付は、老齢年金が支給される65歳までの間の労働者の生活の安定を図るものと考えると理解しやすいと思います。65歳以降は、老齢年金にバトンタッチされるイメージです。
また、括弧書きとして、「(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)」があります。介護休業給付金や育児休業給付金が支給されるならそれでカバーしましょうということです。生活の安定を図るにはひとつの給付金があれば足りるので、基本的に二重でもらえないような仕組みになっています。
就業促進手当と高年齢再就職給付金もどちらかが支給されます。
なお、少し細かいですが、復習もかねて、就業促進手当は、56条の3第1項第1号ロなので、「安定した職業に就いた者」のみが対象となります。
高年齢再就職給付金についても、支給申請手続をおさえておきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者は働いており、公共職業安定所の長は被保険者の賃金を知ることができないため、「60歳到達時等賃金証明書」が必要になるのでした。
一方、高年齢再就職給付金は、被保険者は一度離職しており、基本手当の支給を受けたことがある、つまり、公共職業安定所で失業の認定を受けたことがあります。公共職業安定所の長は、被保険者の賃金の状況を把握しているので、「60歳到達時等賃金証明書」は不要となります。
ここで届出について復習します。
59歳以上である被保険者については、この限りでない、つまり離職証明書を添える必要があるのは、この時点で、高年齢再就職給付金を受給するにあたり必要となる賃金についての情報を把握しておきたいのが理由です。こうすることによって、公共職業安定所の長は、被保険者の60歳到達時等の賃金を把握でき、被保険者は、高年齢再就職給付金の申請をするときに、改めて「60歳到達時等賃金証明書」を提出する必要がなくなるのです。ここまで学習すると、届出の部分が理解できるようになります。
給付制限
偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる(61条の3)。
① 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
② 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
給付制限はいつもと同じものが規定されています。
第2款 介護休業給付
介護休業給付金
介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する(61条の4第1項)。
前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする(61条の4第2項)。
この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあっては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう(61条の4第3項)。
介護休業給付金は、被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合において、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給します。算定の対象となる期間が最大で4年間になるところは、一般被保険者の基本手当と同じであることがわかります。
対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母です。配偶者の父母も対象になる点に注意しましょう。
「みなし」の意味については、高年齢雇用継続給付と同じなので割愛します。
「支給単位期間」は、かんたんにいうと、介護休業をした期間を1か月単位で区切った期間です。「応答」についてもこれまで何度か出てきているので、詳細は割愛します。介護休業給付金は、この支給単位期間ごとに支給されます。
介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の67に相当する額とする(61条の4第4項前段、法附則12条)。
① 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
② 当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数
介護休業給付金は、原則100分の67が支給単位期間(1か月)に30日分支給されます。最後の支給単位期間(最終月)は、終了した日までの日数が支給されます。
条文が読みにくいので補則します。これは、介護休業をしたときに、事業主から賃金が支払われた場合に介護休業給付金を調整するための規定です。
賃金の額に介護休業給付金の額を加えた額が、お給料の100分の80に相当する額以上であるときは、100分の80になるように介護休業給付金の額を減らします。
賃金の額が、お給料の100分の80に相当する額以上であるときは、介護休業給付金は、支給しません。
第1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない(61条の4第6項)。
①同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
②同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業
介護休業給付金は、同一の対象家族について、4回目以後はされません。反対にいうと、3回までは支給されるということです。また、93日に達した日後も支給されません。最大で93日まで支給されるということです。
介護休業給付金についても、支給申請手続をおさえておきましょう。
介護休業給付金は、高年齢雇用継続給付の2つと異なり、2か月と短くなっている点を比較しておきましょう。
給付制限
偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる(61条の5第1項)。
前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付金を支給する(61条の5第2項)。
給付制限については、同様です。また、新たに介護休業給付金の支給を受けることができる者となった場合は、介護休業給付金を支給する点も同じです。