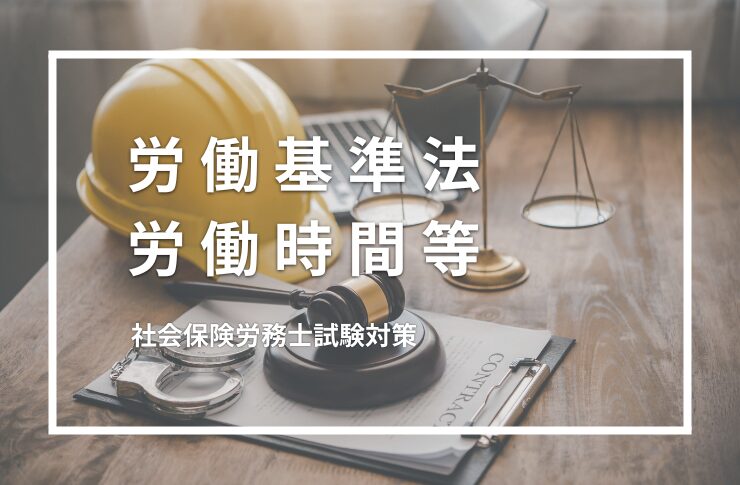ここでは、労働基準法の変形労働時間制について学習します。
変形労働時間制は、「1箇月単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の4つがあります。これらがどのようなものかを整理しておさえていきましょう。
なお、条文は、「1箇月→フレックスタイム→1年→1週間」になっており、ここでも条文の順番に進めますが、短い順または長い順の方が覚えやすいという方は、並び替えてもかまいません。
1箇月単位の変形労働時間制(32条の2)
使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間(特例の場合は44時間)又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる(32条の2第1項)。
使用者は、前項の協定を行政官庁[所轄労働基準監督署長]に届け出なければならない(32条の2第2項、規則12条の2の2第2項)。
1箇月単位の変形労働時間制は、月の中で忙しい時期とそうでない時期がある業種を思い浮かべると理解しやすくなります。たとえば、月初はそれほど忙しくないけれど、月末になると納期の関係で忙しくなる、そんな仕事を想像してみましょう。
1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則で定めます。
1箇月単位の変形労働時間制は、月の中で忙しい時期とそうでない時期があり、トータルで見るとトントンになるイメージです。特定された週で40時間(特例の場合は44時間)、特定された日で8時間を超えることはできても、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例の場合は44時間)を超えることはできません。
たとえば、4週間で60時間、50時間、20時間、30時間とするのは、平均40時間なので問題ありませんが、80時間、50時間、40時間、30時間とするのは、平均50時間になってしまうので、(たとえ特例の場合であっても)許されません。
なお、特例というのは、商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するものが対象です。
1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間である。
① 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く)(昭63.1.1基発1号)。
問題を確認しておきましょう。
1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。(令元-2-C)
正誤:◯
1日の所定労働時間が6時間とされていた日の労働時間を8時間まで延長しましたが、1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、1日については、「8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間」です。本問では、8時間を超える時間が定められていないので、8時間までは時間外労働にはなりません。
1箇月単位の変形労働時間制について、判例を確認しましょう。
労基法32条の2の定める1箇月単位の変形労働時間制は,使用者が,就業規則その他これに準ずるものにより,1箇月以内の一定の期間(単位期間)を平均し,1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをした場合においては,法定労働時間の規定にかかわらず,その定めにより,特定された週において1週の法定労働時間を,又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというものであり,この規定が適用されるためには,単位期間内の各週,各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があるものと解される。原審は,労働協約又は改正就業規則において,業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ,1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって,上告人らについて変形労働時間制が適用されていたとするが,そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではない(最判平14.2.28 大星ビル管理事件)。
フレックスタイム制(32条の3)
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例の場合は44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間(特例の場合は44時間)又は1日において8時間を超えて、労働させることができる(第32条の3第1項)。
① 労働させることができることとされる労働者の範囲
② 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間[1週間40時間、1日8時間]を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。)
③ 清算期間における総労働時間
④ その他厚生労働省令で定める事項
フレックスタイム制は、労働者が働く時間を調整できることから、ベンチャー企業を中心に導入されています。大切なのは、始業及び終業の時刻を労働者に委ねるという点です。
また、①就業規則等により始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることとした労働者について、②労使協定により所定の事項を定めるという流れになっています。よく、基本書では、「1箇月は労使協定または就業規則、フレックスは労使協定かつ就業規則」のように意味もわからず丸暗記をさせられてしまいますが、このような手続の流れをおさえると記憶が定着しやすくなります。
フレックスタイム制は、労働者が始業及び終業時刻を決めるため、労働時間が短い時期もあれば、長い時期も生じます。そこで、区切りとして清算期間が必要になります。たとえば、清算期間が1箇月の場合、1箇月の中で清算期間における総労働時間を満たせばよいことになります。
読みにくいので補足します。まず、これは清算期間が1箇月を超えるものである場合についてです。この場合、1箇月ごとに各期間を平均して、1週間当たりの労働時間が50時間を超えないようにします。たとえば、ある1箇月の1週間当たりの労働時間が40時間、またある月の1週間あたりの労働時間が60時間になってはいけないということです。ある月の労働時間が過度になりすぎないために定められています。
整理しておきましょう。
- 清算期間が1箇月以内:届出不要
- 清算期間が1箇月超え:届出が必要
フレックスタイム制について、通達を確認しましょう。
フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労動者の決定に委ねる必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労動者の決定にゆだねるのでは足りないものである(平11.31基発168号)。
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。したがって、法第36条第1項の規定による協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものである(平11.3.31基発168号)。
清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものである(昭63.1.1基発1号)。
1年単位の変形労働時間制(32条の4)
使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる(32条の4第1項)。
① この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
② 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。)
③ 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)
④ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(最初の期間)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
⑤ その他厚生労働省令で定める事項
1年単位の変形労働時間制は、1年間に忙しい時期とそうでない時期がある業種を思い浮かべると理解しやすくなります。たとえば、平時はそれほど忙しくないけれど、お中元やお歳暮の季節は注文や発送で忙しくなる、そんな仕事を想像してみましょう。
読みにくいので補足します。他の変形労働時間制と違い、1年単位の変形労働時間制は、先の予定が読みにくいという特徴があります。そこで、まず最初の期間については、労働日と労働時間を定めておく必要があります(32条の4第1項4号)。そのため、「最初の期間を除く」となっています。次に、最初の期間を除く各期間の労働日と労働時間については、各期間の初日の30日前までに労働組合等の同意を得て、定めればよいことになっています。かんたんにいうと、次の期間の初日の30日前までに次の期間の労働日と労働時間を決めてくださいということです。
1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
1週間単位の非定型的変形労働時間制は、1週間の中で忙しい時期とそうでない時期がある業種を思い浮かべると理解しやすくなります。たとえば、平日はそれほど忙しくないけれど、週末は忙しくなるサービス業(小売業、旅館、料理店及び飲食店)を想像してみましょう。
労働時間及び休憩の特例として、商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間まで労働させることができます(40条、規則25条の2)。しかし、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用している場合、労働時間及び休憩の特例は適用されず、1週間40時間までとなります(規則25条の2第4項)。1日10時間まで労働させることができるように調整しているため、週あたりでは40時間を守ろうということです。
労働者側からすると、前触れもなく突然「明日10時間働いてほしい」と言われたら困ってしまいます。そのため、1週間が始まる前までに労働させる1週間の各日の労働時間を書面により通知しなければならないとされています。ただし、例外として、緊急でやむを得ない事由がある場合には、変更しようとする日の前日までに書面により通知することができるとされています。
まとめ
変形労働時間制は、「1箇月単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の4つがあります。それぞれ細かい数字が出てくることもありますが、各制度がどのような業種を対象としているのか趣旨を考えるようにしましょう。
まず、変形労働時間制は、原則として労使協定で定めます。もっとも、1箇月以内で調整できる1箇月単位の変形労働時間制は、労動者にとって不利益が小さいので、就業規則でも定めることができます。また、フレックスタイム制は、就業規則で始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、労使協定で定めます。
そして、使用者は、労使協定を行政官庁に届け出ます。もっとも、清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制については労動者の不利益が小さいので、届出が不要とされています。