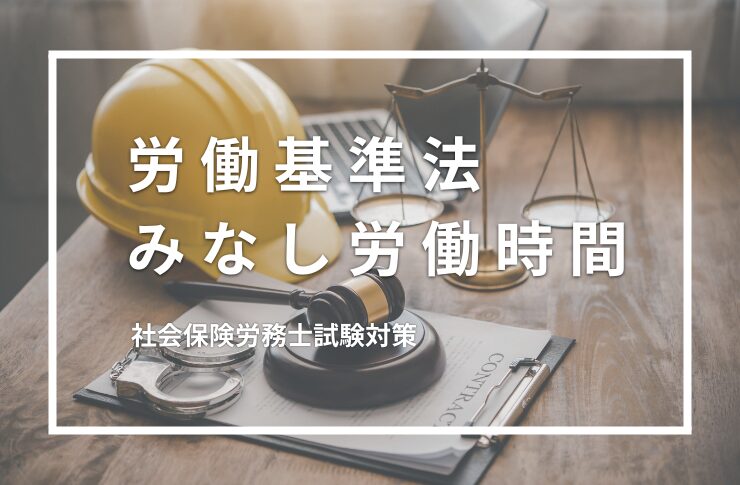ここでは、労働基準法の時間外及び休日の労働について学習します。
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
原則として事前の許可、例外は事後に届出となります。
時間外及び休日の労働
いわゆる「三六協定」と呼ばれるものです。三六協定は、労使協定をし、行政官庁に届け出ることによって効力を生じます。
労使協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする(同条2項)。
① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
② 対象期間(1年間に限るものとする)
③ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
④ 労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
⑤ 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る(同条3項)。
前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3箇月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1箇月について42時間及び1年について320時間)を超えない時間とする(同条4項)。
三六協定は、延長して労働させることができる限度時間が定められています。原則は、1箇月45時間、1年360時間です。1年で考えた場合、1箇月あたり30時間を超えないようになっているという価値判断を持っておくとよいでしょう。また、1年単位の変形労働時間制の対象期間として3箇月を超える期間を定めて労働させる場合は、ブレが大きくなりやすいので、つまり、特定の期間に労働時間が集中する可能性が高いので、1箇月42時間、1年320時間と短く規定されています。
読みにくいので補足します。先ほどの3項、4項は「通常予見される時間外労働の範囲内」において定められたものでした。5項は、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」において定められたものです。いわゆる「特別条項」と呼ばれるものです。1箇月が100時間、1年が720時間まで定めることができます。特別条項は労働者の負担が大きいので、1年について6箇月以内が限度となります。
使用者は、三六協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない(同条6項)。
① 坑内労働その他健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
② 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
③ 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。
三六協定の上限が3つ定められています。
1号は、坑内労働についてです。延長して労働させた時間が2時間を超えないとは、たとえば、8時間の通常労働時間に加えて延長して2時間、合計10時間ということです。
1号についての通達を確認しましょう。
坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務とその他の労働が同一日中に行われ、かつ、これら2種の労働の労働時間の合計が1日についての労働時間数をこえた場合においても、その日における坑内労働等の労働時間数が1日についての法定労働時間数に2時間を加えて得た時間数を超えないときは、本条第1項本文の手続がとられている限り適法である(平11.3.31基発168号)。
2号は、1箇月の時間外労働と休日労働が100時間未満であることです。これも特定の月に労働時間が偏らないようにするための規定です。
3号が少し読みにくいですが、「直前の1箇月の期間を加えた期間」というのは2箇月間ということです。同じように「直前の2箇月の期間を加えた期間」というのは3箇月間ということです。そして、「直前の5箇月の期間を加えた期間」は6箇月間ということになります。つまり、2〜6箇月のそれぞれの期間における1箇月あたりの平均時間が80時間を超えないこととされています。
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、適用除外とされています。たとえば、短期間で感染症のワクチンを開発しなければならない業務などを想像するとわかりやすいと思います。ちょっとかわいそうな気もしますが、これらの業務については、業務内容が優先され、限度時間等が適用除外になります。
括弧書きについて、「2号及び3号に係る部分に限る。」ので1号は適用除外から除かれています。坑内労働はその他健康上特に有害な業務については、有害のため、適用除外に含まれません。もっとも、適用除外の対象となる新たな技術等の研究開発に係る業務が坑内労働というのは考えにくいので、それほど気にする必要はないでしょう。
三六協定について、判例を確認しておきましょう。
使用者が三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由であれば労働契約に定める労働時間を延長して労動者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労動者は、その定めるところに従い、労働契約に定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負う(最判平3.11.28)。
時間外、休日及び深夜の割増賃金
労働日の割増賃金は2割5分以上、休日の割増賃金は3割5分以上、1箇月60時間を超えた場合は5割以上となります。
読みにくいので補足します。まず、60時間を超えた場合、その部分は5割以上の割増賃金が必要になります。このとき、労使協定により、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(代替休暇)を与えることを定めることができます。この場合、60時間を超えて取得した休暇に対応する時間については、5割以上の割増賃金を支払う必要はないということです。
深夜の時間帯は、2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
通達と判例を確認しましょう。
労動者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法第32条[1週間、1日の労働時間]又は第40条[労働時間及び休日の特例]の労働時間を超えないときは本条第1項に基く割増賃金支払の必要はない(昭63.3.14基発150号)。
協定において休日の労働時間を8時間と定めた場合割増賃金については8時間を超えても深夜業に該当しない限り3割5分増で差支ない(平11.3.31基発168号)。
本条1項は、33条又は36条所定の条件が充足された場合と否とにかかわらず、時間外労働等に対し、割増賃金支払義務を認めた趣旨と解するを相当とする(最判昭35.7.14)。
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても、当該年俸の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない(最判平29.7.7)。
選択式で出題された判例をみておきましょう。
最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。
そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
(最判令2.3.30 国際自動車事件)
賃金の算入
休日及び深夜の割増賃金の基礎となる賃金には、次の賃金は算入しない(37条5項、規則21条)。
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
一見、労働者が損をしているように感じますが、これらは労働時間に応じたものではないので、割増賃金には算入しないこととされています。なお、本試験対策としては、上記のうち、家族手当と通勤手当を優先的におさえておくようにしましょう。労働基準法ではこれら2つをあげ、あとの項目は「その他厚生労働省令で定める賃金」として省令で定めているからです。
時間計算
本店で6時間、支店で3時間勤務した場合は、1時間分の割増賃金が発生するということです。
少し細かいところですが、坑内労働は、健康上特に有害な業務という価値判断を持つと、中に入っている時間は労働時間としてみなされるということが理解しやすいと思います。