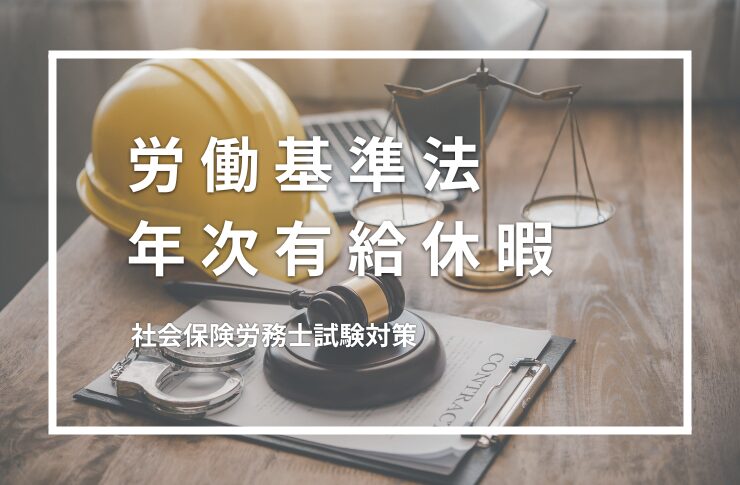労働基準法のみなし労働時間制について学習します。
みなし労働時間制には、①事業場外労働のみなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制があります。これらを整理しておさえるようにしましょう。
事業場外労働のみなし労働時間制
事業場外労働のみなし労働時間制は、あくまで労働時間を算定し難いときに適用されるものです。事業場外で業務に従事した場合でも、従事者の中に労働時間を管理する者がいる場合や、携帯電話等によっていつでも連絡がとれる状態にあり、使用者の指示を受けながら労働している場合、業務の具体的指示を受けており、帰社する場合などは適用されません。
ただし書について補足します。ある業務について、通常所定の労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、そのある業務は、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます。労働者にとって有利な方に規定されているということです。
先ほどのように、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合、労使協定であらかじめ当該業務の遂行に通常必要とされる時間を定めておくことができます。
行政官庁に届け出ることによって、使用者が好き勝手にみなし労働時間を決めることができないようになっている、つまり、公正さが担保されるようになっています。
ここで、選択式で出題された判例をみておきましょう。
最高裁判所は、海外旅行の添乗業務に従事する添乗員に労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるかが争点とされた事件において、次のように判示した。
「本件添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、本件会社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、添乗員は、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められている。
そうすると、本件添乗業務は、旅行日程が上記のとおりその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られているものということができる。
また、ツアーの開始前には、本件会社は、添乗員に対し、本件会社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示したアイテナリーにより具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じている。
そして、ツアーの実施中においても、本件会社は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、本件会社に報告して指示を受けることを求めている。
さらに、ツアーの終了後においては、本件会社は、添乗員に対し、前記のとおり旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっている。
これらによれば、本件添乗業務について、本件会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているということができる。
以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。」
(最判平26.1.24 阪急トラベルサポート事件)
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制の対象業務については、新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務、情報処理システムの分析又は設計の業務、新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務などが規則で定められています(規則第24条の2の2第2項各号)。
労使協定により定める事項は、対象業務や労働時間として算定される時間、対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないことなどがあります。
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制の対象業務は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務とされています(38条の4第1項1号)。
労使委員会の決議により定める事項は、対象業務や対象者、労働時間として算定される時間などがあります。先ほどの専門業務型は労使協定でしたが、企画業務型は労使委員会の決議といったように、導入要件が重くなっているのが特徴です。
企画業務型は、先ほどの専門業務型と同じように、使用者が具体的な指示をしないことがポイントです。つまり、労働者側に裁量があることが前提となっているということです。これは「裁量労働制」という名前からもわかります。
まとめ
みなし労働時間制には、①事業場外労働のみなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制があります。
①事業場外労働のみなし労働時間制は、労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときに所定労働時間労働したものとみなすもの。
②専門業務型裁量労働制は、労使協定により、対象業務に就かせたときに、労使協定で定めた時間労働したものとみなすもの。
③企画業務型裁量労働制は、労使委員会の決議により、対象業務に就かせたときに、決議で定めた時間労働したものとみなすもの。
労使協定や労使委員会の決議によって定める事項については、細かく規定されていますが、それらについて問われることは今のところほとんどありません。本試験対策としては、現時点では出題されることが少ない、つまり、優先度が低めなので、まずは概要をおさえておき、試験範囲全体が見えてきたところで、少しずつ理解を深めていくようにしましょう。