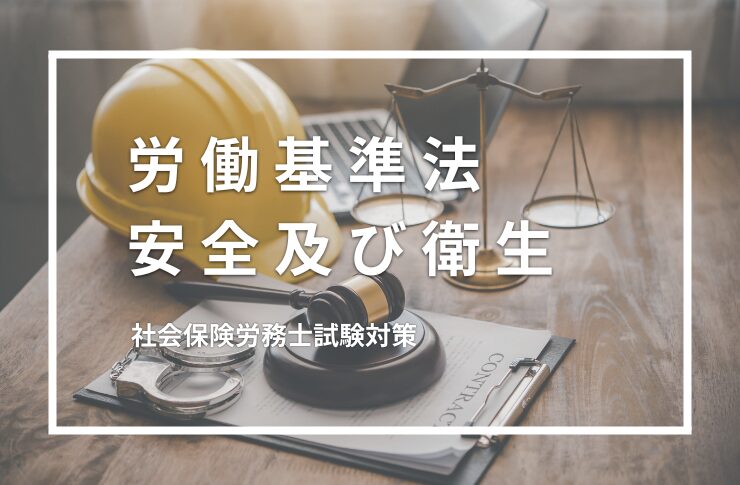労働基準法の年次有給休暇について学習します。
ます、年次有給休暇について、判例と通達を確認しておきましょう。
・年次有給休暇の権利は、労働基準法の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではない(最判昭48.3.2)。
・年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はない。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じる(平3.12.20基発17号)。
・年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままである(昭63.3.14基発150号)。
| 勤続年数 | 付与日数 |
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年 | 20日 |
表を見ると、どうして1.5年、2.5年と半端なのかと思いますが、条文を見ると「6箇月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとに」加算することになっているのがわかります。つまり、6箇月経過日から起算して、1年、2年、3年ごとに加算されるということです。また、1年、2年までは1年につき1日ずつ加算され、3年以降は1年につき2日ずつ加算される点は注意しておきましょう。
使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、労使協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる(39条4項)。
① 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
② 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
③ その他厚生労働省令で定める事項
時間を単位として有給休暇を与えることができるのは、5日以内までの日数です。
労働基準法は、季節を含めた時期という意味で「時季」という言葉を用いています(水町・労働法)。
時季変更権について、選択式で出題された判例をみておきましょう。
最高裁判所は、労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過した後にされた使用者の時季変更権行使の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であつても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、それが事前にされなかつたことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。」
(最判昭57.3.18)
最高裁判所は、労働基準法第39条第5項(当時は第3項)に定める使用者による時季変更権の行使の有効性が争われた事件において、次のように判示した。「労基法39条3項〔現行5項〕ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たつて、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがつて、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところである〔……〕から、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによつてそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。」
(最判昭62.7.10 弘前電報電話局事件)
最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[・・・(略)・・・]労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[・・・(略)・・・]使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右裁量的判断は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右裁量的判断が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項〔現5項〕ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」
(最判平4.6.23 時事通信社事件)
5日を超える部分については、労使協定により有給休暇を与える時季を定めることができます。反対に言うと、5日分については、必ず労働者が決められるようにしておく必要があるということです。
使用者は、労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない(規則24条の6第1項)。
使用者は、聴取した意見を尊重するよう努めなければならない(規則24条の6第2項)。
有給休暇が10日以上ある労働者については、5日については、1年以内の期間に、年次有給休暇を与えなければならないというものです。つまり、10日以上有給休暇がある労働者は、最低でも1年に5日は有給休暇を取らないといけないということです。
読みにくいので補足します。もし、有給休暇を与えた場合、つまり、労働者が有給休暇を使った場合は、その日数については時季を定めて与える必要はないということです。たとえば、10日有給休暇がある労働者の場合、自分で3日有給休暇を使った場合は、その日数(3日)については時季を定めて与える必要はありません。あとの2日分だけ時季を定めて与える必要があります。
有給休暇中の賃金について定められています。ここもただ暗記させられてしまうところですが、条文構造が違うところを意識しましょう。まず、原則として就業規則で定めるところにより、平均賃金、もしくは通常の賃金になります。そして、例外として、労使協定がある場合は、健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額となっています。社労士試験は、表で暗記をする方も多いと思いますが、条文に立ち返って、原則と例外がどのような位置関係になっているのかをおさえることも大切です。
いわゆる労働災害や育児休業、介護休業、産前産後の休業は、労働者に帰責事由がないため、出勤したものとみなします。