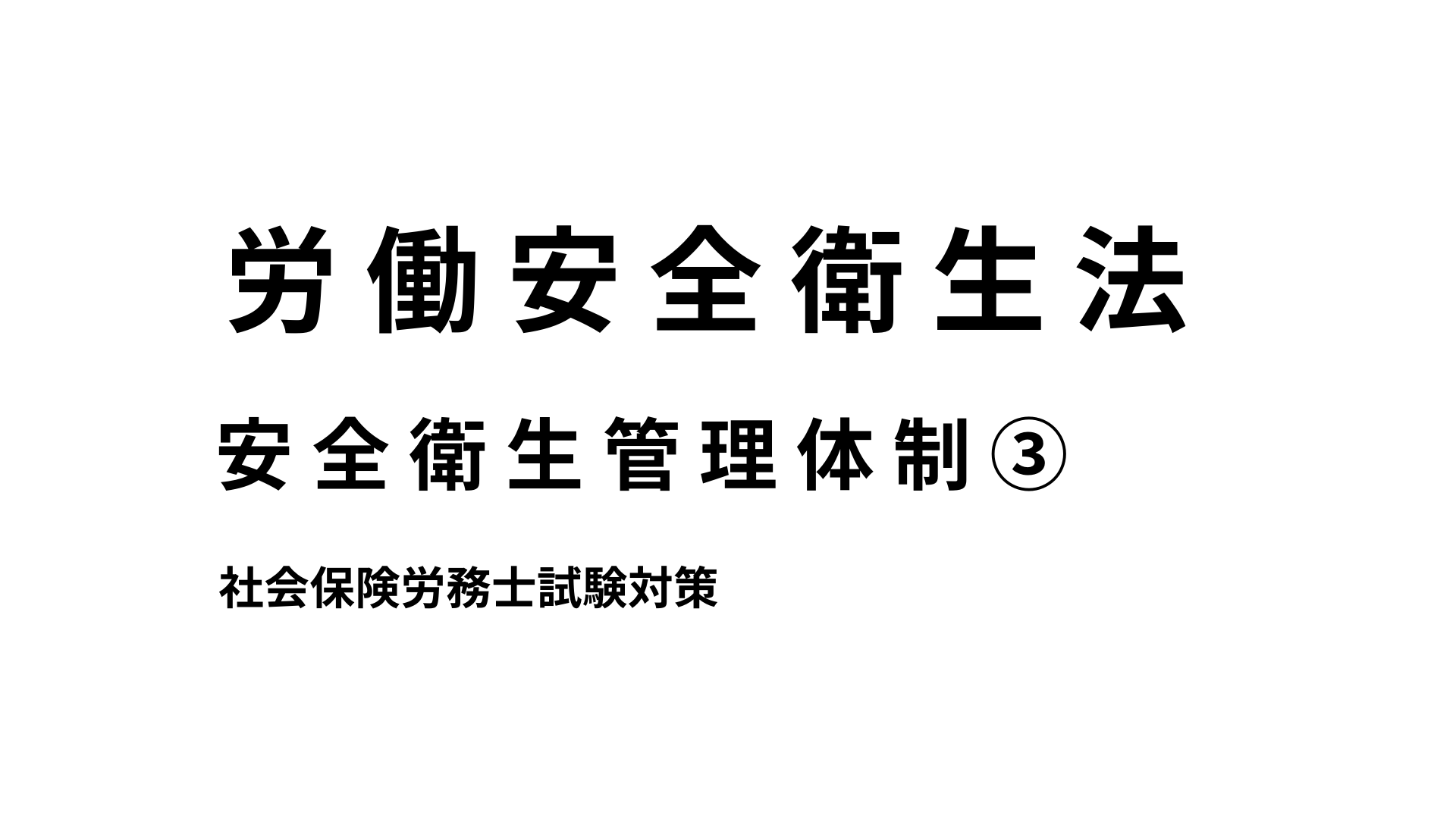労働安全衛生法の安全衛生管理体制から建設業等におけるものについて解説します。どの事業者で選任する必要があるのかをおさえながら整理していきましょう。
統括安全衛生責任者【元方事業者】
・事業者で、元方事業者のうち、建設業・造船業を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、特定元方事業者等の講ずべき措置を統括管理させなければならない(15条1項本文、政令7条1項)。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない(15条1項但書)。
→元方事業者とは、仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるとき、請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者のことをいいます。条文の表現だとわかりづらくなってしまいますが、下請け、孫請け、ひ孫請けなど2以上の者があった場合、もっとも先次(この場合下請け)の請負契約における注文者、つまり元の注文者が元方事業者です。
→統括安全衛生責任者を選任する必要があるのは、労働者の数が次の数以上の場合です。
| 仕事の区分 | 労働者の数 |
| ①ずい道等の建設の仕事 ②橋梁の建設の仕事 ③圧気工法による作業を行う仕事 |
常時30人 |
| 前号に掲げる仕事以外の仕事 | 常時50人 |
・統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない(15条2項)。
元方安全衛生管理者【元方事業者】
・統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任し、その者に特定元方事業者等の講ずべき措置のうち技術的事項を管理させなければならない(15条の2第1項)。
→元方安全衛生管理者を選任するのは、建設業のみです。造船業が含まれない点に注意しましょう。
→元方安全衛生管理者は、建設業の元方事業者における安全管理者、衛生管理者のような立ち位置だと考えると、理解しやすいと思います。
店社安全衛生管理者【元方事業者】
・建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における特定元方事業者等の講ずべき措置を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない(15条の3第1項)。
→読みにくいので補足します。労働者が作業を行うときは、事業場ごとに、店社安全衛生管理者を選任する必要があります。このとき、以下は除かれます。
- 厚生労働省令で定める数未満である場所
- 統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所
厚生労働省令で定める数未満である場所は、以下のとおりです(規則18条の6第1項)。
| 仕事の区分 | 労働者の数 |
| ①ずい道等の建設の仕事 ②橋梁の建設の仕事 ③圧気工法による作業を行う仕事 ④主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 |
常時20人 |
| 前号に掲げる仕事以外の仕事 | 常時50人 |
これらの労働者の数未満である場所は、規模が小さいので、店社安全衛生管理者を選任する必要はありません。
そして、統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所は、統括安全衛生責任者がいるので、店社安全衛生管理者を選任する必要はありません。店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任しない比較的小規模のときに選任する必要があるということです。
上記①〜③の事業は、労働者の数が1人〜19人の場合は、どちらも選任する必要はありません。20人以上になると、店社安全衛生管理者を選任する必要があります。そして、30人以上になったら、統括安全衛生責任者を選任する必要があります。なお、前述のとおり、統括安全衛生責任者を選任したら、店社安全衛生管理者を選任する必要はありません。
④の事業は、20人以上になると、店社安全衛生管理者を選任する必要があります。そして、④は、統括安全衛生責任者を選任する必要がある仕事の区分が「前号に掲げる仕事以外の仕事」に分類されるので、50人以上になったら、統括安全衛生責任者を選任する必要があります。
政令は、「統括安全衛生責任者を選任すべき業種等」として、7条2項1号で「ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事」を定めています。これが表の①〜③にあたるものです。そして、規則は「店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数」として、18条の6第1項1号で「令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事」を定めています。つまり、表の①〜③及び④ということです。
④主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事は、①〜③と比べて選任要件が少し緩和されていると考えることができます。または、④は統括安全衛生責任者を選任する場面では「前号に掲げる仕事以外の仕事」だけれど、「店社安全衛生管理者」を選任する場面では要件が少し厳しくなっていると考えることができます。
いずれにせよ、本試験対策の点から深追いするところではないので、統括安全衛生責任者を選任しないような比較的規模が小さいときに店社安全衛生管理者を選任するのだとおさえておきましょう。
安全衛生責任者【元方事業者以外の請負人】
・統括安全衛生責任者が選任された場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない(16条1項)。
→整理しましょう。安全衛生責任者を選任するのは、統括安全衛生責任者が選任された場合で、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものです。たとえば、下請けや孫請けがこれに該当します。一応、「当該仕事を自ら行うもの」なので、丸投げしているだけの事業者は該当しないことになります。安全衛生責任者は、注文者が選任した統括安全衛生責任者との連絡をする、つまり架け橋になる存在だと考えるとよいでしょう。
・安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない(16条2項)。
→安全衛生責任者を選任したら、統括安全衛生責任者との連絡をする必要があるので、「うちは安全衛生責任者を選任しました」と通報する必要があるということです。通報というと、何やら不穏ですが、行政では、 をいいます。「今後よろしくお願いします」とあいさつするようなものだと考えるとよいでしょう。
まとめ
安全衛生管理体制で覚えにくいことのひとつは、「責任者」と「管理者」が混在していることです。これらを直接問われることは少ないですが、整理しておきましょう。
まず、現場に出ているトップは、「責任者」です。元請事業者は「統括安全衛生責任者」を選任します。統括安全衛生責任者を選任した事業所では、「元方安全衛生管理者」を選任します。ナンバー2なので、管理者という名前です。
次に、統括安全衛生責任者がいない現場で作業を行うときは、「店社安全衛生管理者」を選任します。統括安全衛生責任者がいないことについて、規模が小さい場合は管理者でよいと考え、また規模が大きい場合は統括安全衛生責任者が違う事業場で選任されているので、管理者と考えます。
最後に、元方事業者以外の請負人は「安全衛生責任者」を選任します。下請けですが、その事業者にとっては現場に出てトップとして働いています。
そう考えると、全産業に共通する「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」は、建設業などの現場にいるわけではないので、管理者と考えることができます。
すべてのうち、元請事業者のトップは「統括安全衛生責任者」、下請け事業者のトップは「安全衛生責任者」、それ以外は「管理者」と考えてしまってもかまいません。
多少、強引かもしれませんが、自分なりにどういうときに「責任者」になり、どういうときに「管理者」になるのかを関連付けておさえてみましょう。