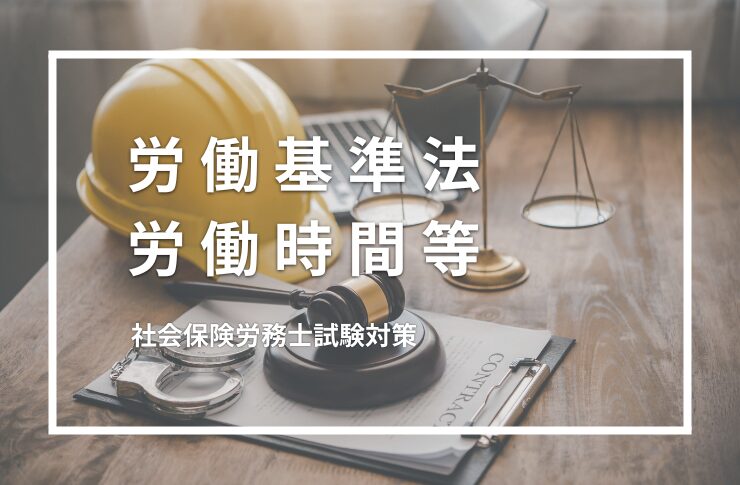労務管理その他の労働に関する一般常識から労働組合法について学習します。労働組合法は全5章で構成されている法律です。さっそく、内容を見ていきましょう。
目次
第1章 総則
目的
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする(1条1項)。
刑法第35条(正当行為)の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない(1条2項)。
労働組合法は、労働者の地位を向上させることなどについて定めています。労働組合法ができた昭和20年(1945年)という時代背景なども考えると、より理解しやすいと思います。
刑法35条は正当行為について定めています。
労働組合の団体交渉などは、正当な業務に該当し、罰しないとされています。ただし、いかなる場合においても、暴力の行使は認められません。
労働組合
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない(2条各号)。
① 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
② 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
③ 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
④ 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
労働組合は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体等をいいます。ただし、監督的地位にある労働者や使用者の経理上の援助を受けるものなどについては労働組合とされません。経理上の援助を受けると、使用者側に気を遣ってしまうというのを考えると、わかりやすいと思います。
労働者
労働者の定義が、労働基準法と異なるので注意しましょう。
よく例に出されるのは、たとえばプロスポーツ選手は事業に使用される者ではないので、労働基準法の労働者には該当しませんが、賃金等の収入によって生活する者なので労組法上の労働者にあたります。
第2章 労働組合
労働組合として設立されたものの取扱
労働組合は、労働組合の規定に適合することを立証しなければ、労組法に規定する救済を与えられません。ただし、次の不当労働行為のうち、不利益取扱いの規定に基づく個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない、つまり、労組法にあたらないから不利益取扱いをしてよいというように解釈されるべきではないということです。不当労働行為の救済については、後述します。なお、労働組合の規約の詳細は割愛します。
組合費について、判例は次のように述べています。
労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときでも、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の全額を納付する義務を免れないものというべきであり、所論のように脱退した日までの分を日割計算によって納付すれば足りると解することはできない(最判昭50.11.28 国労広島地本事件)。
不当労働行為
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない(7条各号)。
① 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
② 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
③ 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
④ 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
不当労働行為は、労組法の山場の部分です。不当労働行為がされると、労働組合は救済を求めることができます。
1号ただし書きについて、採用後一定期間内に特定の労働組合に加入しない労動者及び脱退又は除名により組合員資格を失った労動者を使用者が解雇する旨を定める労使間の協定をユニオンショップ協定といいます。ユニオンショップ協定について、判例は次のように述べています。
「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(最判平元.12.14)。
2号の誠実交渉義務について、判例は、「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令〔使用者が誠実交渉義務に違反している場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令〕を発することができると解するのが相当である。」としています(令4.3.18)。
損害賠償
使用者は、同盟罷業(ストライキ)などの争議行為であって正当なものによって損害を受けたことを理由として労働組合や組合員に賠償を請求することはできません。もし、ストライキによって工場が停止し、その損害を労働組合や組合員に請求することができたら、労働組合はストライキなどをすることができないのを考えるとわかりやすいと思います。
第3章 労働協約
労働協約の効力の発生
労働基準法や労働契約法に出てきた労働協約についてです。労働協約は、労働組合と使用者等が書面に作成し、署名し、記名押印することによって効力を生じます。
基準の効力
労働協約は、労働契約より強い力があることがわかります。労働契約は労働者と使用者が締結するため、労働者の立場が弱くなりやすいですが、労働協約は組合と使用者が締結するため、労働者の立場が強くなります。
一般的拘束力
一般的拘束力について、選択式で出題された判例を確認しましょう。
最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の規範的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に、労働協約の規範的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。
しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である。」(最判平8.3.26)
第4章 労働委員会
労働委員会
労働基準法等に出てくる「労使委員会」と混同しないようにしましょう。
労使委員会:賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)
不当労働行為事件の審査の開始
7条の不当労働行為があったとき、労働組合は、労働委員会に申立てをすることができます。そして、労働委員会は、必要があると認めたときは、審問を行います。
第5章 罰則
本試験対策の点からすると、労働組合法の罰則は、優先度が低くなります。こういったものがあるといった程度で深追いはしないようにしましょう(他に覚えることがあるはずです)。
参考:労働組合 |厚生労働省