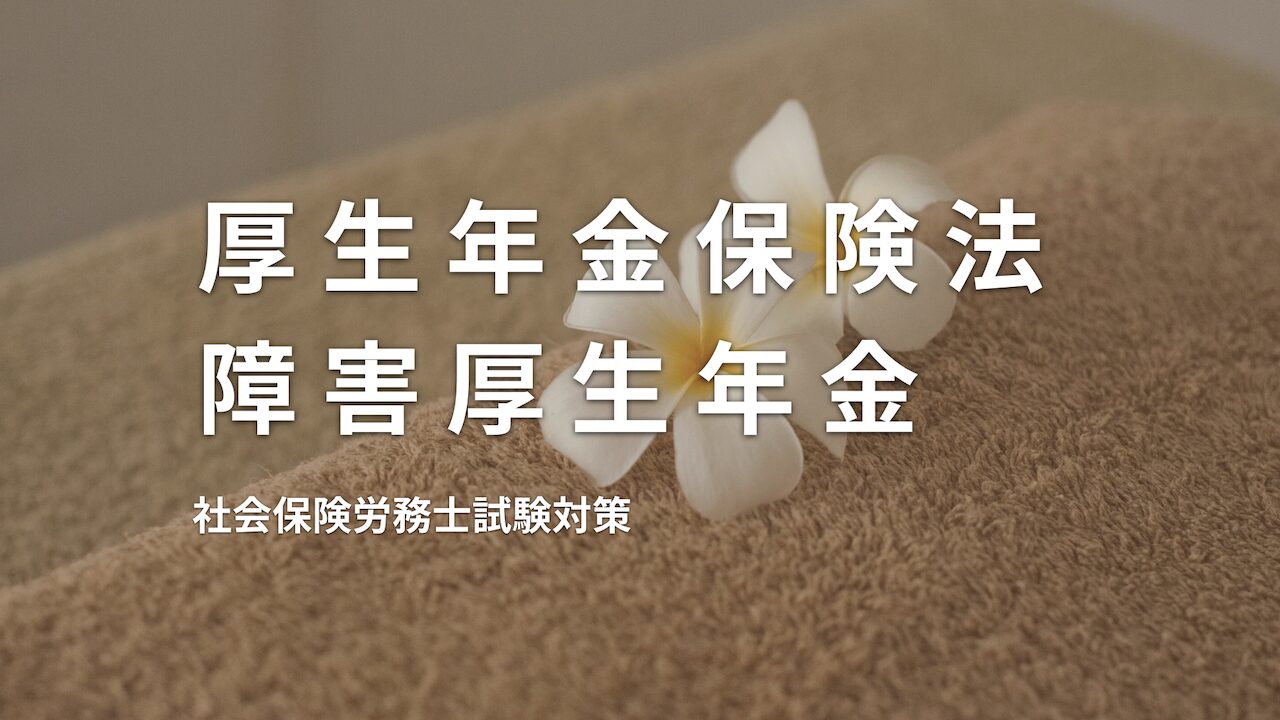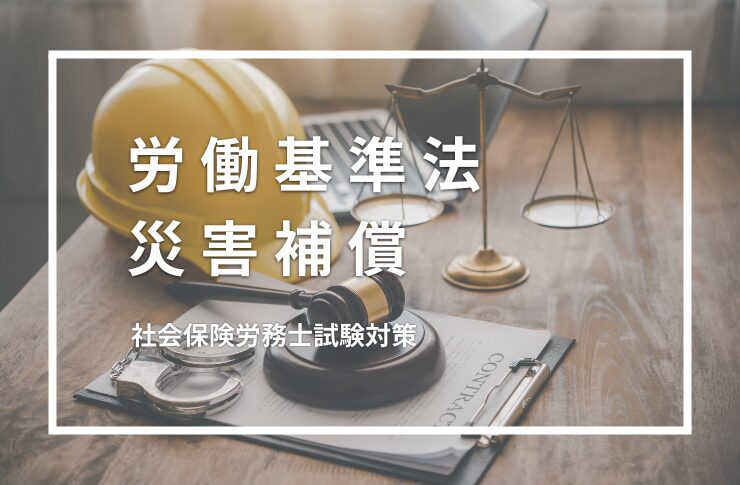国民年金法の給付から障害基礎年金について学習します。障害基礎年金においても、支給要件、年金額、失権を核におさえていきましょう。
支給要件
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない(30条1項)。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める(30条2項)。
障害基礎年金は、傷病について、初診日において、各号のいずれかに該当した者が、1年6月を経過した日または障害認定日において、1級、2級に該当する程度の障害にあるときに、支給されます。
1号について、被保険者であるのは、現在被保険者なのでわかりやすいと思います。
2号について、被保険者であった者というのは、以前は被保険者であった60歳以上65歳未満の者ということです。
ただし書きについて、前々月までに被保険者期間があり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2に満たないときは、この限りでない、つまり支給されません。「被保険者期間があり」というのは、20歳未満の場合や60歳以上の場合は、被保険者期間がないこともあるからです。また、「前々月まで」というのは、国民年金の納付期限は、翌月末日のため(前月の年金の納付期限は今月末日)、納付期限が来たものを対象にしているからです。これらは、初診日の前日において判定されます。仮に当日だと、午前中に病院に行って、午後に年金を納付するといったこともできてしまうからです。制度の濫用ができなくなっている点を意識すると理解記憶しやすいと思います。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる(30条の2第1項)。
前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する(30条の2第2項)。
第1項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金について、その額が改定されたときは、そのときに同項の請求があったものとみなす(30条の2第4項)。
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害のなかったものが、65歳に達する日の前日までの間において、1級または2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、障害基礎年金の支給を請求することができます。いわゆる事後重症と言われるものです。65歳に達する日の前日までとなっているのは、それ以降は老齢基礎年金でもカバーできるからです。
前条第1項ただし書の規定が準用されているため、3分の2要件を満たす必要があります。
4項について、厚生年金保険の障害厚生年金の額が改定されたときは、障害基礎年金も改定の請求があったものとみなされます。同じ手続を2回しなくてもよいということです。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する(30条の3第1項)。
第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する(30条の3第2項前段)。
第1項の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする(30条の3第3項)。
これは、前から傷病により障害の状態にある方の場合です。この方が、新たに負傷し(これを「基準傷病」といいます)、65歳に達する日の前日までの間において、基準障害と前からある他の障害とを併合して1級または2級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、障害基礎年金を支給します。
先程の事後重症も今回の基準障害も原則の支給要件を満たしていることが前提です。また、こちらも30条1項ただし書が準用されているので、3分の2要件を満たす必要があります。
本試験対策として、事後重症の場合は、「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは…障害基礎年金の支給を請求することができる。」(30条の2第1項)として、請求が受給権発生の要件とされています。一方、基準障害の場合は、「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは…障害基礎年金を支給する」(30条の3第1項)として、当然に受給権が発生します。もっとも、「第1項の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする」として、支給は、請求が必要になります(30条の3第3項)。
もう少し言うと、65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ればよく、請求は65歳に達した日以後に行うこともできます。本試験では、ここが頻出です。
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
(令6-問10-D)
正解:☓
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
(平29-問7-D)
正解:☓
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する(30条の4第1項)。
第1号被保険者と第3号被保険者は、20歳以上が対象のため、20歳未満で疾病や負傷をした場合、障害基礎年金の支給が受けられず、国民生活の安定をそこなってしまいます。そこで、20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金が規定されています。
初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したとき、たとえば、18歳で負傷し、19歳6か月のときに障害認定日があった場合、20歳に達した日において、障害基礎年金を支給します。19歳で負傷し、障害認定日が20歳6か月など20歳に達した日後であるときは、その障害認定日において、障害基礎年金を支給します。前段と後段の違いがイメージできれば問題ありません。
併給の調整
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する(31条1項)。
障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する(31条2項)。
期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する(32条1項)。
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金がその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する(32条2項)。
特に難しいところはないと思いますが、併給の調整が規定されています。
年金額
障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする(33条1項)。
障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、障害基礎年金の額の100分の125に相当する額とする(33条2項)。
障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額とします。老齢基礎年金と異なり、保険料納付済期間の月数は考慮されない点を比較しておきましょう。1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、障害基礎年金の額の100分の125に相当する額、つまり、1.25倍の金額になります。
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする(33条の2第1項)。
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至ったことにより、障害基礎年金の額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する(33条の2第2項)。
障害基礎年金は、生計を維持している子があるときは、1人につき74,800円に改定率を乗じて得た額を加算します。カッコ書きにあるように、2人までについては、224,700円を加算します。反対にいうと、3人目からは74,900円になるということです。覚え方は自由ですが、選択式などは条文の表現で出題されることが多いため、できるだけ原則がどちらかをおさえておくことを推奨します。
障害基礎年金の額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する(33条の2第3項)。
① 死亡したとき。
② 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
③ 婚姻をしたとき。
④ 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。
⑤ 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。
⑥ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
⑦ 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
⑧ 20歳に達したとき。
障害基礎年金の改定も、こちらを暗記すると大変なので、33条の2第1項の原則を理解記憶し、それらに当てはまらなくなったときに改定されるといった考え方をおすすめします。
障害の程度が変わった場合の年金額の改定
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる(34条1項)。
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる(34条2項)。
障害基礎年金の額の改定の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない(34条3項)。
障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる(34条4項)。
障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする(34条6項)。
厚生労働大臣は、障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができます。
また、受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができます。この改定の請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、障害基礎年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。
障害基礎年金の受給権者が、新たに疾病または負傷によりその他障害の状態にあり、併合した障害の程度が増進したときは、障害基礎年金の額の改定を請求することができます。基準障害のところで見たのは、「基準障害+他の障害」で、初めて、1級または2級に該当するに至った場合です。今回は、すでに障害基礎年金を受給している人が、さらに「その他障害」によって、障害の程度が増進した場合です。状況を混同しないように注意しましょう。
障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めます。
失権
障害基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する(35条)。
① 死亡したとき。
② 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
③ 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
2号と3号について、まだ学習していませんが、厚生年金保険法では、障害厚生年金は3級まで支給されます。これに該当しなくなったときというのが条件です。2号では、65歳に達したとき、3号では、3年を経過したときとされており、それぞれ、互い違いのただし書きがついています。まとめると、①厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者、②65歳に達した、③3年を経過した、この3点を満たしたときに消滅します。
支給停止
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する(36条1項)。
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する(36条2項本文)。
20歳前障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、その支給を停止する(36条の2第1項各号)。
① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
④ 日本国内に住所を有しないとき。
20歳前障害基礎年金は、年金を支払っていない20歳前に負傷した国民の生活を安定させるために支給されるものです。そのため、刑事施設等に拘禁されているときや日本国内に住所を有しないときなどは、支給されません。20歳前障害基礎年金は福祉的な意味合いが強いという点をおさえると、通常の障害基礎年金より支給停止事由が多くなるのが理解しやすいと思います。