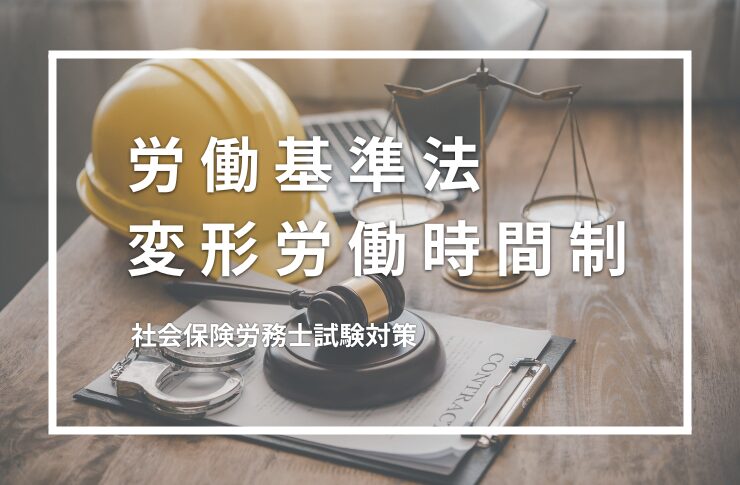ここでは、労働基準法の労働時間、休憩、休日について学習します。
労働基準法の第4章は、「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」と内容が多岐にわたり、さらに、この中に変形労働時間制やみなし労働時間制なども含まれます。これらを一度に理解しようとするのは大変なので、まず核となる労働時間、休憩、休日をみていきましょう。
- 32条:労働時間
- 32条の2:1箇月単位の変形労働時間制
- 32条の3:フレックスタイム制
- 32条の4:1年単位の変形労働時間制
- 32条の5:1週間単位の非定型的変形労働時間制
- 33条:災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
- 34条:休憩
- 35条:休日
- 36条:時間外及び休日の労働
- 37条:時間外、休日及び深夜の割増賃金
- 38条:時間計算
- 38条の2:事業場外労働
- 38条の3:専門業務型裁量労働制
- 38条の4:企画業務形裁量労働制
- 39条:年次有給休暇
- 40条:労働時間及び休憩の特例
- 41条:労働時間等に関する規定の適用除外
労働時間
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない(32条1項)。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない(32条2項)。
まず、1週間40時間、1日8時間までが原則です。この上で、社会生活上の理由から、さまざまな制度が加わることとなります。
労働時間について、通達を確認しましょう。
1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいう。1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする(昭63.1.1基発1号)。
出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間も労働時間である(昭33.10.11基収6286号)。
労動者が使用者の実施する時間外の教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば時間外労働にはならない(昭和26.1.20基収2875号)。
健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労動者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものである。特定の有害な業務に従事する労動者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない(昭47.9.18基発602号)。
労働時間について、選択式で出題された判例をみてみましょう。
最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」
最高裁判所は、マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである〔…(略)…〕。そして、不活動時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」。
(最判平19.10.19 大林ファシリティーズ事件)
休憩
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(34条1項)。
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労使協定があるときは、この限りでない(34条2項)。
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない(34条3項)。
労働時間の途中、一斉に、自由に利用は休憩の3原則と呼ばれることがありますが、条文を理解しておけば、賃金のときと同じように無理に用語を覚える必要はありません。
休憩時間について、通達と判例を確認しましょう。
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない(平11.3.31基発168号)。
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも本条3項に違反しない(昭23.10.30基発1575号)。
休憩時間中であっても、局所内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を行うことは、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあり、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げひいてはその後の作業能率を低下させるおそれがあり、その内容いかんによっては企業の運営に支障をきたし企業秩序を乱すおそれがあるから、休憩時間中にこれを行うについても局所の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定める日本電信電話公社の就業規則の規定は、休憩時間の自由利用に対する合理的な制約というべきである(最判昭52.12.13)。
休日
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない(35条1項)。
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない(35条2項)。
2項について、たとえば、1週目に1日、2週目に休日なし、3週目に2日、4週目に1日といったように、4週間を通じて4日以上の休日があれば、適用しない、つまり、毎週少なくとも1回の休日を与えなくてもよいことになります。
労働時間及び休憩の特例
4つの事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、特例として1週間について44時間まで労働させることが認められています。労働時間及び休憩の特例は、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要性から設けられているものです。この観点から、映画演劇業については、「映画の製作の事業」は除かれています(つまり、映画の製作の事業は40時間までということです)。
労働時間等に関する規定の適用除外
① 農業、水産、養蚕、畜産業に掲げる事業に従事する者
② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
1号について、農業や水産など自分の意思ではコントロールできないものが対象になります。そのため、林業は除外されています。
2号について、通達を確認しましょう。
機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう(昭22.9.13発基17号)。
3号について、「監視又は断続的労働」とは、宿直などの業務が該当します。
高度プロフェッショナル制度の対象者の適用除外
いわゆる「高度プロフェッショナル制度」と呼ばれるものです。高度プロフェッショナル制度の対象者は、金融商品の開発や資産運用など高度の専門的知識等を必要とするもので、従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められるものです。対象労働者の範囲としては、基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として定める額(1,075万円)以上であるとされています。
労使委員会とは、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会のことをいいます。
条件をまとめましょう。
- 労使委員会が設置された事業場
- 委員の5分の4以上による決議
- 行政官庁に届け出
- 対象労働者
- 書面等による同意
- 対象業務
これにより、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、適用しません。
先ほど、農業等の場合は労働時間、休憩、休日までだったのに対し、高度プロフェッショナル制度の場合は、深夜の割増賃金も適用されません。深夜も働くことがあるという前提で高い給与額が設定されていると考えると、理解記憶しやすいと思います。