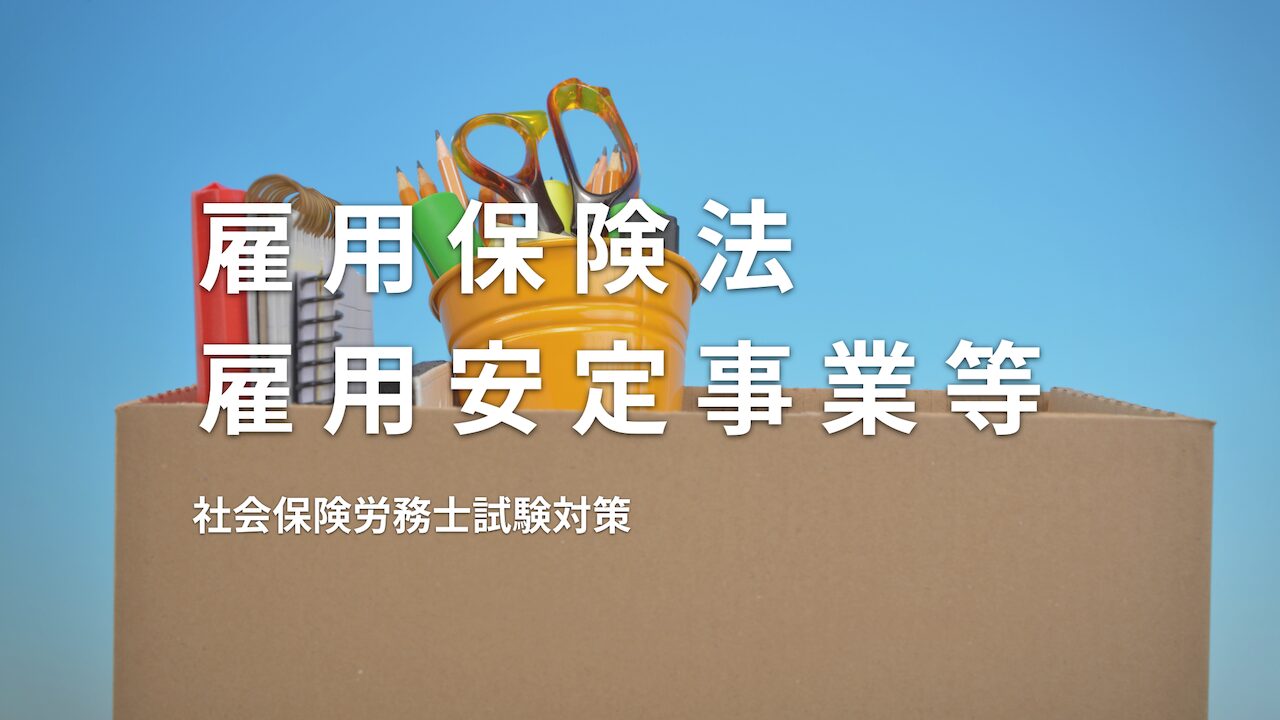※現在リライト中です。
雇用保険法の育児休業給付について解説します。育児休業給付は、第3章の2ということで、新しくできた給付であることがわかります。前回の介護休業給付と似ている点があるので、比較しながら見ていきましょう。
育児休業給付
ここで、育児休業給付は2種類あることがわかりました。
育児休業給付金
育児休業給付金は、被保険者が、1歳に満たない子を養育するための休業をした場合、育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給されます。被保険者期間は、介護休業給付と同じであることがわかります。
以下、条文を掘り下げていきましょう。
被保険者は、「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」となっています。このことから、高年齢被保険者は含まれることがわかります。さまざまな事情により、祖父母が育児をしていることを想像するとわかりやすいと思います。
子の年齢は、原則1歳に満たない子ですが、1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子となります。さらに、必要と認められる場合は、2歳に満たない子となります。
厚生労働省令で定める場合は、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳(または1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合などが規則で定められています(規則101条の25)。
育児休業期間中に受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合は、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば、当該育児休業が終了したものと取り扱わない(行政手引59503)。
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、産後8週間を経過した後から対象育児休業となる(行政手引59503)。
育児休業の申出に係る子が1歳に達した日後の期間について、児童福祉法第39条に規定する保育所等において保育を利用することができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる(行政手引59601)。
同一の子についての育児休業給付金は3回目以後はされません。介護休業給付金は4回目以後であったことと比較しておきましょう。
「みなし」については、これまでさまざまなところで解説してきているので、ここでは割愛します。
「支給単位期間」の概念については、介護休業給付のときと同様です。
育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の50(当該育児休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額とする。(61条の7第6項)。
① 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
② 育児休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該育児休業を開始した日又は休業開始応当日から当該育児休業を終了した日までの日数
育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額になります。ただ、休業日数が通算して180日に達するまでの間は、100分の67に相当する額に調整されています。100分の67は介護休業給付金の額と同様です。また、支給単位期間あたり30日、最後の支給単位期間(最終月)は、終了した日までの日数が支給される点も同じです。
育児休業をした被保険者に事業主から賃金が支払われた場合について、介護休業給付金のときと同様の規定がされています。
被保険者の配偶者(一般的には父)が子を養育するための休業をしている場合(パパ・ママ育休プラス制度)、1項の規定、つまり原則「1歳」までのところが「1歳2か月」までとなります。
育児休業給付金の支給申請手続についておさえておきましょう。
高年齢雇用継続給付や介護休業給付との違いをおさえておきましょう。特に、介護休業給付金は、「当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日まで」となっているのに対し、育児休業給付は「支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日まで」といったように起算点や期間も異なるので注意が必要です。
出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の休業をした場合に、支給されるものです。時系列としては、この出生時育児休業給付金のあとに先ほどの育児休業給付金になりますが、条文の順番通りに進めます。
読みにくいところを補則します。
最初の括弧書き「(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)」について、原則は、出生の日から起算して8週間を経過する日までです。
ただ、もし出産予定日前に出生した場合は、「出生の日から」「出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで」となります。つまり、原則より期間が少し長くなることがわかります。次に、出産予定日後に出生した場合は、「出産予定日から」「出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで」となります。こちらも、原則より期間が少し長くなることがわかります。いずれにせよ、原則より不利にならないように配慮されているという点をおさえておきましょう。
「出生時育児休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき」は育児休業給付金と同様です。
被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給しない(第61条の8第2項)。
① 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業
② 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業
1号について、育児休業給付金と同様のことが定められています。
2号について、出生時育児休業給付金は、出生の日から8週間のうち4週間が限度なので、28日に達した日後の出生時育児休業については、支給されません。
このあたりも、育児休業給付金と同様です。
育児休業給付金とほとんど同じことが規定されています。育児休業給付金は、180日までが100分の67でしたが、出生時育児休業給付金は28日までの全部が100分の67に相当する額とされています。
育児休業給付金と同様の規定がされています。
出生時育児休業給付金の支給申請手続についておさえておきましょう。
育児休業給付金と同じように考えることができます。一点、起算日は「子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から」、期限は「当該日(子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日)から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日まで」というように少し条文が読みにくいので注意しましょう。
また、育児休業給付金は、「支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日まで」となっていました。つまり、育児休業を開始した時点から起算されます。一方、出生時育児休業給付金は、「子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から」といったように、原則として出生時育児休業が終わったあとから起算するようになっています。これは、出産後は大変なので、申請などをする余裕がないと考えると理解しやすいと思います。
給付制限
偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる(61条の9第1項)。
前項の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となった場合には、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する(61条の9第2項)。
給付制限については、いつもと同じです。