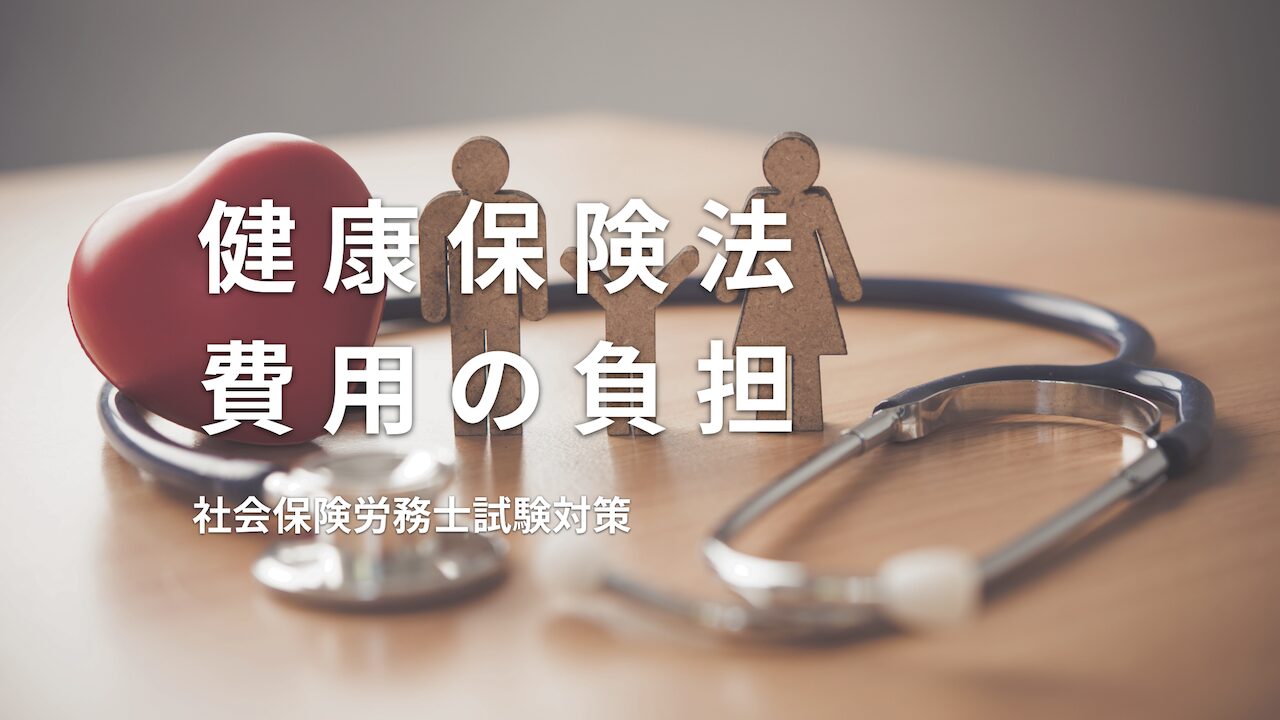健康保険法の被保険者から標準報酬月額及び標準賞与額について学習します。
標準報酬月額
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める(40条1項)。
※等級区分は省略
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。(40条2項)。
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする(40条3項)。
等級区分は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)まで定められています。
2項が読みにくいので補則します。毎年3月31日における最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるとき、つまり、50級の人が1.5%を超えて、今後もその状態が続くと認められるときは、その年の9月1日から、最高等級の上にさらに等級を加える等級区分の改定を行うことができます。つまり、51級をつくれるということです。ただし、改定後の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない、つまり、0.5%未満のごく一部の人だけ保険料が上がる、かんたんに言うと不利益を被るようにはなってはならないということです。
定時決定
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する(41条1項)。
標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする(41条2項)。
6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条[随時改定]、第43条の2[育児休業等をした際の改定]又は第43条の3[産前産後休業を終了した際の改定]の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない(41条3項)。
標準報酬月額の決定は、理解が難しい部分だと思うので補則します。保険料を決めるためには、被保険者が報酬月額をどのくらいもらっているかを決める必要があります。ただ、月によって報酬が異なる場合があるので、一定のタイミングで報酬月額を決めましょうというのが定時決定です。
そして、定時決定で決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までとしています。9月スタートというのは制度として決めている部分なので、そのまま飲み込んでしまうのをおすすめします。これを前提に読み進めていきましょう。
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。3月間に受けた報酬の総額(90万円)をその期間の月数である3で除して得た額(30万円)を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。報酬月額とは、等級区分で「◯円以上◯円未満」のように定められているものです。そして、この範囲にあるものを標準報酬月額としています。
カッコ書きとして、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を含めると報酬月額が少なくなってしまう、つまり健康保険料が不当に低くなってしまうため、その月を除いて1月、または2月で除して計算します。
さらに、厚生労働省令で定めるものにあっては、11日とする場合について、
週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者の場合、「17日未満」だと該当しなくなってしまうことが考えられるため、「11日未満」としています。
定時決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
3項が読みにくいので整理しましょう。6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者は、まだ報酬支払を受けていないことも考えられ、また受けていても1か月分のため、定時決定は適用しないとされています。また、育児休業等をした際の改定により7月から9月までに標準報酬月額が改定され、または改定される予定がある被保険者もその改定した標準報酬月額を使うため、定時決定は適用しません。
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする(平18.5.12庁保険発0512001号)。
被保険者の資格を取得した際の決定
保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する(42条1項各号)。
① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
③ 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
④ 前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(42条2項)。
保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定します。先ほど、6月1日から7月1日までに被保険者となった者も、この規定によって標準報酬月額を決定することになります。
1号について、これが一般的ですが、報酬の額を月や週など一定期間の総日数で除して得た額(1日分の報酬)の30倍に相当する額(1か月分の報酬)を標準報酬月額とします。
2号は、当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額、3号は、1号と2号で算定することが困難であるものは、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額といったように規定しています。できるだけ不公平にならないように周囲を参考にしながら決めているといったことをおさえておきましょう。
4号について、2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、算定した額を合算した額を標準報酬月額とします。
決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの標準報酬月額とします。9月以降は、先ほどの定時決定によって標準報酬月額が決まるからです。
括弧書きとして、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月までの標準報酬月額とします。定時決定は、「被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において」なので、それ以降に使用されるものは、定時決定の対象外となり、9月からの標準報酬月額が決まらないため、翌年の8月までとなります。また、同様に「6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者」も定時決定の対象外なので、翌年の8月までとなります。
初めて勉強するとき、定時決定がされる7月から9月までが空いているのが気になるかもしれませんが、保険者側の事務手続きに要する期間だと考えると、納得できると思います。
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる(昭50.3.29保険発25号)。
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができない(令5.6.27事務連絡)。
改定
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる(43条1項)。
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(43条2項)。
保険者は、継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定します。改定は、お給料が大きく変わったときに、実体に合わせて保険料を改定しようというものです。改定のポイントとして、「継続した3月間」であることがあげられます。定時改定の場合、17日未満であるときはその月を除きましたが、改定は、継続した3月間である必要があります。改定された標準報酬月額は、その年の8月まで、7月から12月までに改定されたものは翌年の8月までの標準報酬月額となります。
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当するため、標準報酬月額の随時改定の対象となる(令5.6.27事務連絡)。
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない(令5.6.27事務連絡)。
育児休業等を終了した際の改定
保険者等は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない(第43条の2第1項)。
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(第43条の2第2項)。
育児休業等を終了した際の改定と次の産前産後休業を終了した際の改定は、育児休業等をして職場復帰したあと、3歳に満たない子を養育する場合(つまり働く時間が短くなることが想定されます)、お給料が下がるなどの実体に合わせて、標準報酬月額を改定するものです。育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。たとえば、育児休業等終了日(4月15日)の翌日(4月16日)が属する月以後3月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額(60万円)をその期間の月数(3)で除して得た額(20万円)を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。
ただし書きとして、「育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない」としているのは、このあと学習しますが、産前産後休業をしている被保険者は、保険料が免除されるからです(159条の3)。
改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの標準報酬月額とします。条文が読みにくいので補則します。育児休業等終了日(4月15日)の翌日(4月16日)から起算して2月を経過した日(6/16)の属する月の翌月(7月)から改定するということです。つまり、先ほどの育児休業等終了日の翌日から3月分で標準報酬月額を計算して、その翌月から改定されることになります。選択式で問われたときも、意味を考えるようにすれば、間違えることはなくなるので、具体的な事例で考えるようにしましょう。
産前産後休業を終了した際の改定
保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない(第43条の3第1項)。
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(第43条の3第2項)。
基本的な考え方は、育児休業等を終了した際の改定と同じです。
ただし書きの「ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない」について、先ほどと同じく、育児休業中は保険料が免除されるからです(159条)。
詳しくは、費用負担のところで学習して、またここに戻ってきましょう。
報酬月額の算定の特例
保険者等は、被保険者の報酬月額が算定することが困難であるとき、又は算定した額が著しく不当であると認めるときは、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする(44条1項)。
前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない(44条2項)。
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、算定した額の合算額をその者の報酬月額とする(44条3項)。
被保険者の報酬月額が算定することが困難であるとき、または算定した額が著しく不当であると認めるときは、保険者が算定する額を被保険者の報酬月額とします。労働保険のときの認定決定と同じように考えて問題ありません。
標準賞与額の決定
先ほどは、毎月のお給料をもとに標準報酬月額を決めるものでした。今回は、賞与、いわゆるボーナスをもとに標準賞与額を決めるものです。細かいところですが、報酬月額に対しては「標準報酬月額」、賞与額に対しては、「標準賞与額」となっている点をおさえておきましょう。
標準賞与額の累計額が年間573万円を超えることとなる場合には、累計額が573万円となるように標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とします。つまり、最大で573万円までということです。ここは、このあと学習する厚生年金保険法と異なる部分なので、そのときに改めて比較しましょう。
現物給与の価額
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める(46条1項)。
健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる(46条2項)。
任意継続被保険者の標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする(47条1項)。
① 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
任意継続被保険者の標準報酬月額については、①被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、②全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額をその者の標準報酬月額とします。