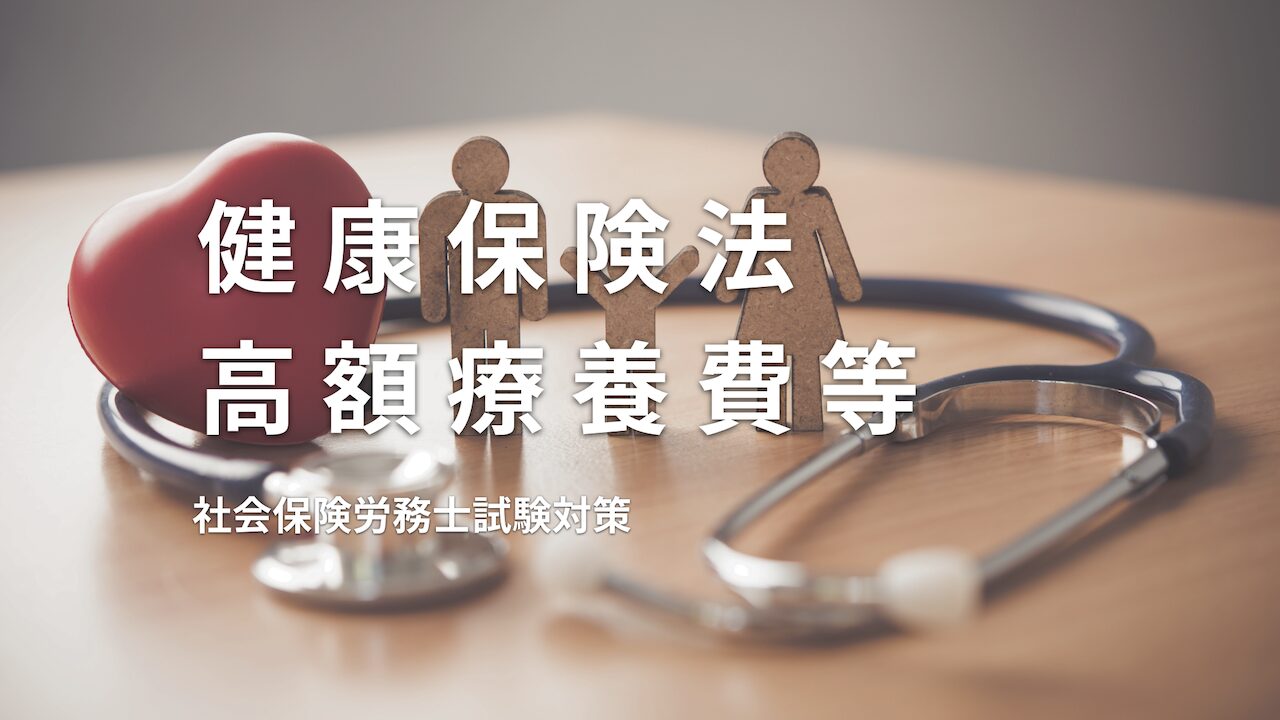※現在リライト中です。
健康保険法の保険給付から家族療養費等について学習します。
定義
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない(3条7項)。
① 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
② 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
③ 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
④ 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを要しない(昭15.6.26社発7号)。
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する(平5.3.5保発15号)。
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている(令2.4.10事務連絡)。
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする(令3.4.30保保発0430第2号)。
指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居と考えられるから、その他の要件を満たす限り、被扶養者として認定される(平11.3.19保険発24号)。
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する(令元.11.13保保発1113第1号。
配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくとも、被保険者と当該被害者が生計維持関係にないことを申し立てた申出書とともに、女性相談支援センター等が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより、被扶養者から外れることができる(令2.3.5保発0305第3号)。
家族療養費
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する(110条1項)。
家族療養費の額は、第1号に掲げる額とする(110条2項各号)。
① 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
② 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
③ 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
家族療養費は、基本的に被保険者に支給されるものと同様です。一点、家族療養費の額について、整理しておきましょう。イは、被扶養者が6歳に達する日以後70歳までが100分の70が支給される、つまり3割負担です。被保険者のときに6歳に関することが出てこなかったのは、被保険者が6歳で働いていることはないというのを考えればわかると思います。
ロは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合は100分の80(2割負担)です。
ハは、被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合は100分の80(2割負担)です。
ニは、第74条第1項第3号に掲げる場合(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、報酬の額が28万円以上であるとき)に該当する被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合は100分の70になります。
たとえば、被保険者(72歳)、被扶養者(68歳)は、イになるので、100分の70です。
また、被保険者(68歳)、被扶養者(72歳)は、ハになるので、100分の80です。
基本的に被扶養者の年齢で確認します。
ただ、被保険者(74歳)、被扶養者(72歳)のように、どちらも70歳以上であって、被保険者の報酬の額が28万円以上であるときは、ニになるので、100分の70になります。本試験でも出題されるので、整理しておきましょう。
以降、頭に「家族」がつくだけで大きな差はないので、ひととおり条文を確認しておきましょう。