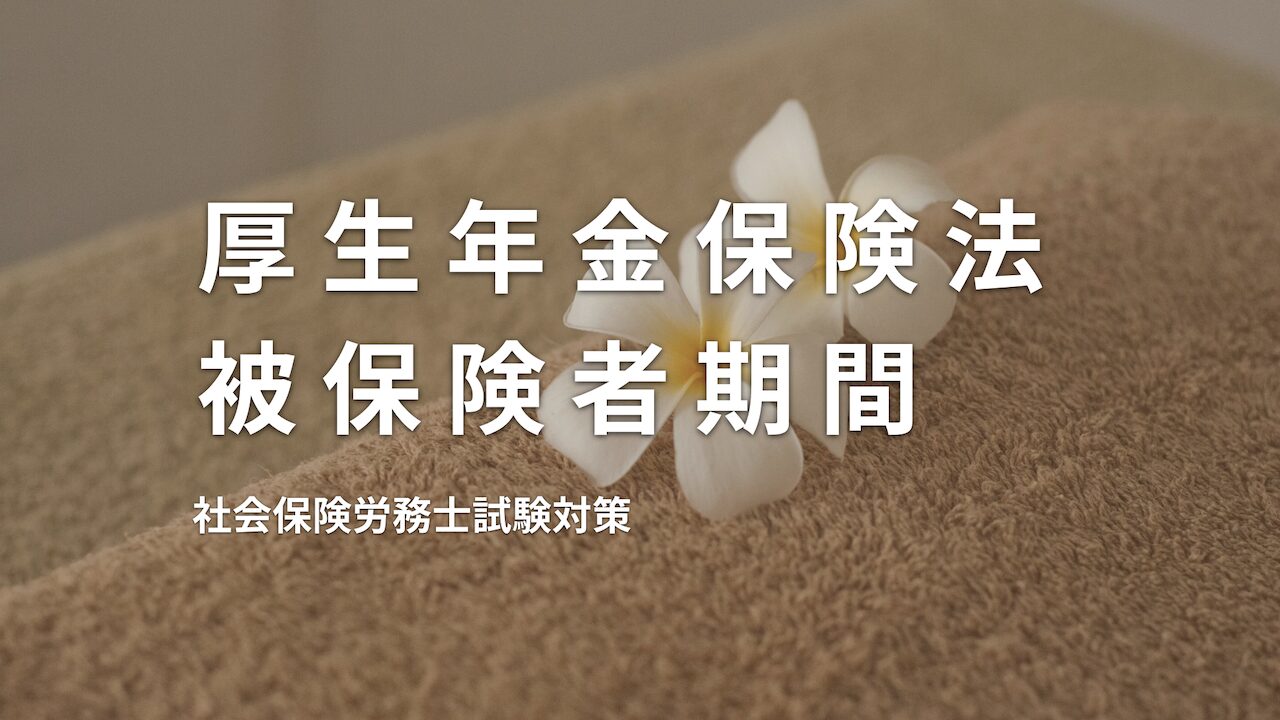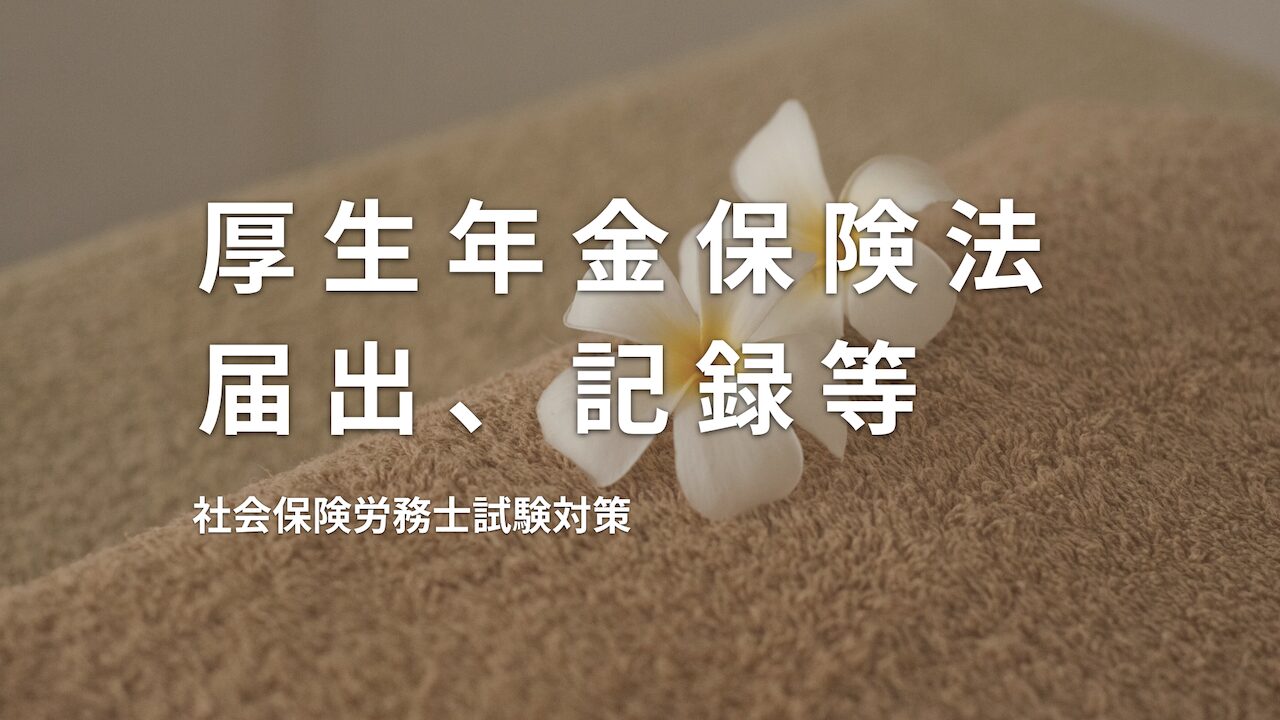厚生年金保険法の被保険者から標準報酬月額及び標準賞与額について学習します。多くは健康保険法と共通しているので、健康保険法との違いを意識しておさえていきましょう。
目次
標準報酬月額
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める(20条1項)。
(※表は省略)
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる(20条2項)。
厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級(88,000円)〜第32級(650,000円)まであります。
健康保険との違いを比較しておきましょう。
- 健保:1級(58,000円)〜50級(1,390,000円)
- 厚年:1級(88,000円)〜32級(650,000円)
2項について、健康保険と同様の規定が設けられています。以下、定時決定など健康保険と同様です。おさらいもかねて条文をみていきましょう。
定時決定
実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する(21条1項)。
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする(21条2項)。
定時決定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業終了時改定又は産前産後休業終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない(21条3項)。
定時決定は、健康保険法と同じことが規定されています。
被保険者の資格を取得した際の決定
実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する(22条1項)。
① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
③ 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
④ 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(22条2項)。
被保険者の資格を取得した際の決定も、健康保険法と同様です。
改定
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる(23条1項)。
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(23条2項)。
改定も健康保険法と同様です。
育児休業等を終了した際の改定
実施機関は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において子であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない(23条の2第1項)。
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(23条の2第2項)。
育児休業等を終了した際の改定も健康保険法と同様です。
産前産後休業を終了した際の改定
実施機関は、産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない(23条の3第1項)。
前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(23条の3第2項)。
産前産後休業を終了した際の改定も健康保険法と同様です。
報酬月額の算定の特例
被保険者の報酬月額が、算定することが困難であるとき、又は算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする(24条1項)。
同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、算定した額の合算額をその者の報酬月額とする(24条2項)。
報酬月額の算定の特例も健康保険法と同様です。
船員たる被保険者の標準報酬月額
船員保険法については、改めて学習しましょう。
標準賞与額の決定
標準賞与額の決定は、健康保険法と異なります。健康保険法では、「その年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。」とされています(健康保険法45条1項後段)。
一方、厚生年金保険法では、「その月の標準賞与額が150万円を超えるときは、150万円」とします。まず、金額が150万円となっています。また、健康保険法が年度であるのに対して、厚生年金保険法は月であることに注意しましょう。たとえば、年2回賞与があるうち、1回目が160万円、2回目が80万円の場合、1回目は150万円を超えるので、150万円とします。2回目は80万円とします。
現物給与の価額
現物給与の価額は、健康保険法と同様です。
3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例
3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす(26条1項)。
① 当該子が3歳に達したとき。
② 資格喪失の時期に至ったとき。
③ この条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったとき
④ 当該子が死亡したとき。
⑤ 育児休業等を開始したとき。
⑥ 産前産後休業を開始したとき。
育児休業等を終了した際の改定によって、標準報酬月額を改定することができます。健康保険の面から考えると、お給料に見合った保険料になることはよいことにみえます。一方、年金の面から考えると、保険料が下がるということは、将来もらえる年金額も下がるということになります。3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は、子どもを養育していたことによって標準報酬月額が下がり、それによって、将来受け取る年金が減少することを防止するための規定です。被保険者にとって有利な制度であるという意識を持ちましょう。
まず、対象は、3歳に満たない子を養育している、または養育していた者です。「養育していた」というのは、あとで申出をすることもできるからです。次に、期間は、養育することとなった日の属する月から子が3歳に達したときや資格喪失の時期に至ったときなどまでです。
そして、この期間については、子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額(これを「従前標準報酬月額」といいます)を下回る月については、従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなします。平均標準報酬額とは、このあと学習する年金額を計算するときに使うものです。かんたんにいうと、保険料額は子を養育することによって下がった標準報酬月額によって算定し、年金額は従前標準報酬月額によって算定されるということです。、
本試験でも、本特例について、年金額と保険料額のどちらに用いられるかが問われています。
本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。
(令5-1-B)
正誤:☓
本特例の趣旨である保険料額が下がっても年金額は従前のままということをおさえましょう。
カッコ書き「(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)」について、あとで申出をした場合は、申出が行われた日の属する月の前月までの2年間までが適用されるということです。