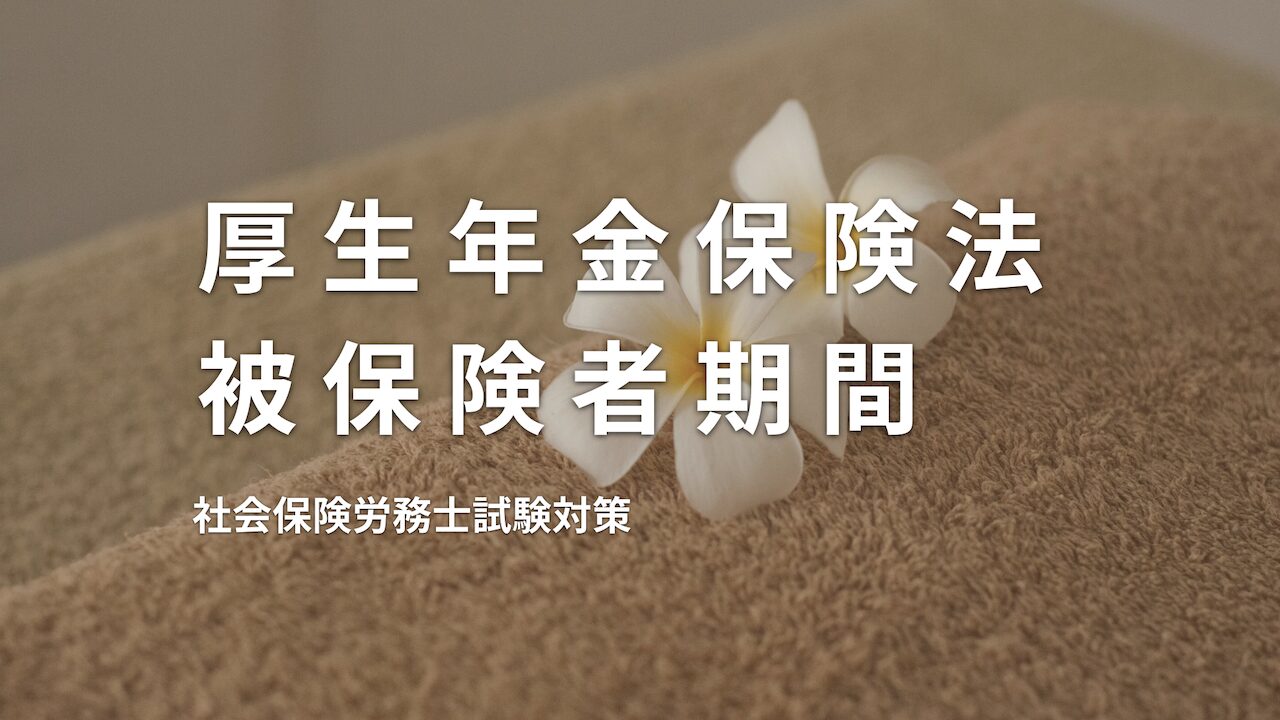厚生年金保険法の被保険者から資格について学習します。第2章「被保険者」は、全4節で構成されています。ひとつずつおさえていきましょう。
適用事業所
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする(6条1項)。
① 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
② 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの
③ 船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす(6条2項)。
第1項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる(6条3項)。
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条[適用除外]に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない(6条4項)。
1号について、「次に掲げる事業の事業所又は事務所」は、健康保険法が適用される業種と同じです。会社などで健康保険と厚生年金保険が(狭義の)「社会保険」とされているので、ここは、理解しやすいと思います。もっとも、イからレの17業種を覚えるのは大変なので、過去問で問われやすい一次産業、接客業、宗教業は含まれないという点をおさえておきましょう。そして、17業種の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するものが適用事業所となります。
2号について、国、地方公共団体、法人の事業所で、常時従業員を使用するものは、適用事業所になります。法人等で常時従業員を使用していれば、5人以上という条件はない点に注意しましょう。
3号について、船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶ということは、通常の会社員などの方と変わらないので、適用されると考えることができます。健康保険法において、船舶が適用事業所とされないのは、船員を対象とする船員保険法があるからです。もっとも、船員保険法には年金制度はないので、厚生年金保険法でカバーすることになっています。
適用事業所の考え方を整理しましょう。まず、法人等の場合、常時従業員を使用すれば、適用事業所となります。次に、個人の場合、17業種であって常時5人以上の従業員を使用するものは、適用事業所となります。これで適用事業所かどうかを判断できるようにしましょう。
ここまでで、適用事業所になるものがわかりました。
3項について、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができます。いわゆる任意適用事業所です。
認可を受けようとするときは、事業主は、事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請します。適用事業所になると、事業所に使用される者は、保険料を支払わなければならないからです。健康保険法のときも同じように考えましたが、すでに国民年金を払っているから不利益はない、会社が2分の1を負担してくれるから利益があると考えるのではなく、新たに厚生年金保険料を納付する義務が生じるため、同意が必要になると考えましょう。
健康保険法のときと同じように、適用事業所が該当しなくなったとき、たとえば、常時5人以上の従業員を使用しなくなったとき、その事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなされます。
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる(8条1項)。
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外の者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない(8条2項)。
任意適用事業所は、適用事業所でなくすることができます。このとき、事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請する必要があります。これまで会社が保険料の2分の1を負担してくれていたという利益がなくなるため、同意が必要になると考えることができます。
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる(8条の2)。
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする(8条の3)。
厚生年金保険は、事業所ごとに適用されますが、本店のほかにいくつも支店がある場合など、手続きが煩雑になってしまうため、全体としてひとつの適用事業所とすることができます。
船舶の場合は、厚生労働大臣の承認を受けることなく、一の適用事業所とされます。Aさんが、2つ以上の船舶を持っている場合、それぞれを事業所とするより、ひとつの適用事業所とした方が管理もしやすいというのを考えるとわかりやすいと思います。
被保険者
国民年金法の被保険者が60歳未満で、老齢基礎年金が支給されるのが65歳からというのと混同しないようにしましょう。厚生年金保険は、いわゆる会社勤めを前提にした仕組みです。現代社会においては、70歳までを対象にしていると考えましょう。
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる(10条1項)。
前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない(10条2項)。
適用事業所以外の事業所は、事業所としては厚生年金保険に入っていません。この場合、70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者になることができます。いわゆる、任意単独被保険者の制度です。もっとも、厚生年金保険の被保険者となるということは、事業主も保険料を負担することになるので、事業主の同意を得る必要があります。
任意で加入しているため、厚生労働大臣の認可を受けて脱退することができます。
適用除外
次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない(12条各号)。
① 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
② 所在地が一定しない事業所に使用される者
③ 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
④ 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
⑤ 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 報酬について、88,000円未満であること。
ハ 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
適用除外について整理しましょう。
1号について、臨時に使用される者は適用除外となります。ただし、日々雇い入れられる者でも1月を超えるに至った場合、2月以内の期間を定めて使用される者は期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、継続性が認められるため、適用除外ではなくなります。
2号について、所在地が一定しない事業所に使用される者は、事業所を定めることができないため、適用除外となります。
3号について、季節的業務に使用される者は適用除外となります。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない、つまり被保険者となります。気をつけたいのは、1号は、一定の期間を超えて使用されるに至った場合は、その時点から被保険者となりますが、3号は、「継続して4月を超えて使用されるべき場合」は、最初から被保険者となります。つまり、たとえば、5か月間使用されるときは、最初から被保険者になるということです。もっとも、たまたま継続して4月を超えた場合などは被保険者にはなりません。あくまで最初から4月を超えるときは最初から被保険者になるということです。
4号について、季節的業務の場合と同じく、6月を超えて使用されるべき場合は、最初から被保険者となります。
5号について、多くの受験生が詰まるところです。厚生年金保険としては、1週間の労働時間または1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である短時間であって、かつ、1週間の労働時間が20時間未満とさらに短かったり、報酬が88,000円未満と少なかったり、または学生であるなど本業ではない方は被保険者としないようにしています。
まず、「短時間である」と「いずれかの要件に該当する」が「かつ」で結ばれていることに注意しましょう。時間は週「または」月、要件は「いずれか」に当てはまれば問題ありません。
これらの上で暫定措置です。
当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く)に使用される短時間労働者であって適用除外事由のいずれにも該当しないものについては、被保険者とされない。特定適用事業所とは、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が50人を超えるものをいいます【改正】。
厚生年金保険料は、事業主も負担しなければならないので、中小企業にとっては、厚生年金保険料の負担が大きくなってしまうという事情があります。そこで、特定適用事業所以外の適用事業所、つまり、それほど大きくない事業所については、週または月の労働時間が短い短時間労働者であって、かつ、1週間20時間未満、報酬88,000円未満、学生等の適用除外事由に該当しないものについても、被保険者とされないとされています。
雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近2か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととされている(平28.5.13保保発0513第1号)。
参考「短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構」
資格取得の時期
第9条[被保険者]の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は前条の規定に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する(13条1項)。
第10条第1項[任意適用事業所]の規定による被保険者は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する(13条2項)。
被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日などに被保険者の資格を取得します。1項の「前条の規定に該当しなくなった日」というのは、被保険者の適用除外に該当しなくなった日という意味です。
資格喪失の時期
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに資格取得の時期に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する(14条各号)。
① 死亡したとき。
② その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
③ 第8条第1項[任意適用事業所でなくする]又は第11条[任意単独被保険者でなくする]の認可があったとき。
④ 適用除外に該当するに至ったとき。
⑤ 70歳に達したとき。
資格喪失について、それぞれ覚えるのは大変なので、「適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」(9条)という原則をおさえます。そして、これに該当しなくなった日の翌日に資格喪失をすると考えるようにしましょう。
健康保険法でも学習しましたが、その事実があった日にさらに前条に該当するに至ったときは、被保険者の期間が重複してしまうため、「その日」に資格喪失します。
- 原則:4月20日使用されなくなった→4月21日資格喪失
- 例外:4月20日使用されなくなり、新たに資格取得した→4月20日資格喪失・資格取得
それぞれ理屈を考えると、翌日に喪失かその日に喪失かわかると思います。
被保険者の種別の変更に係る資格の得喪
手続上、人ではなく、種別ごとに資格の得喪を判断します。
資格の得喪の確認
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項[任意単独被保険者]の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない(18条1項)。
確認は、届出若しくは請求により、又は職権で行うものとする(18条2項)。
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、資格の得喪の確認の規定は、適用しない(18条3項)。
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、効力を生じます。確認とは、行政上、すでに存在している事実関係や法律関係、たとえば具体的に「使用されるに至った」ということを確定することをいいます。ただし、10条1項(任意単独被保険者となる場合)、14条3号(任意適用事業所が適用事業所でなくす場合、任意単独被保険者の資格を喪失する場合)については、「厚生労働大臣の認可」が必要になるので、確認ではないということです。
3項について、第2号、第3号、第4号は、各公務員共済組合連合会等が実施するため、適用しません。
異なる被保険者の種別に係る資格の得喪
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない(18条の2第1項)。
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する(18条の2第2項)。
条文の表現だと難しく感じますが、2号、3号、4号の被保険者は、2号、3号、4号でいる間は、同時に1号になることはないということです。また、第1号の被保険者が、2号、3号、4号の資格を有するに至ったときは、1号の資格を喪失し、2号、3号、4号の被保険者になります。