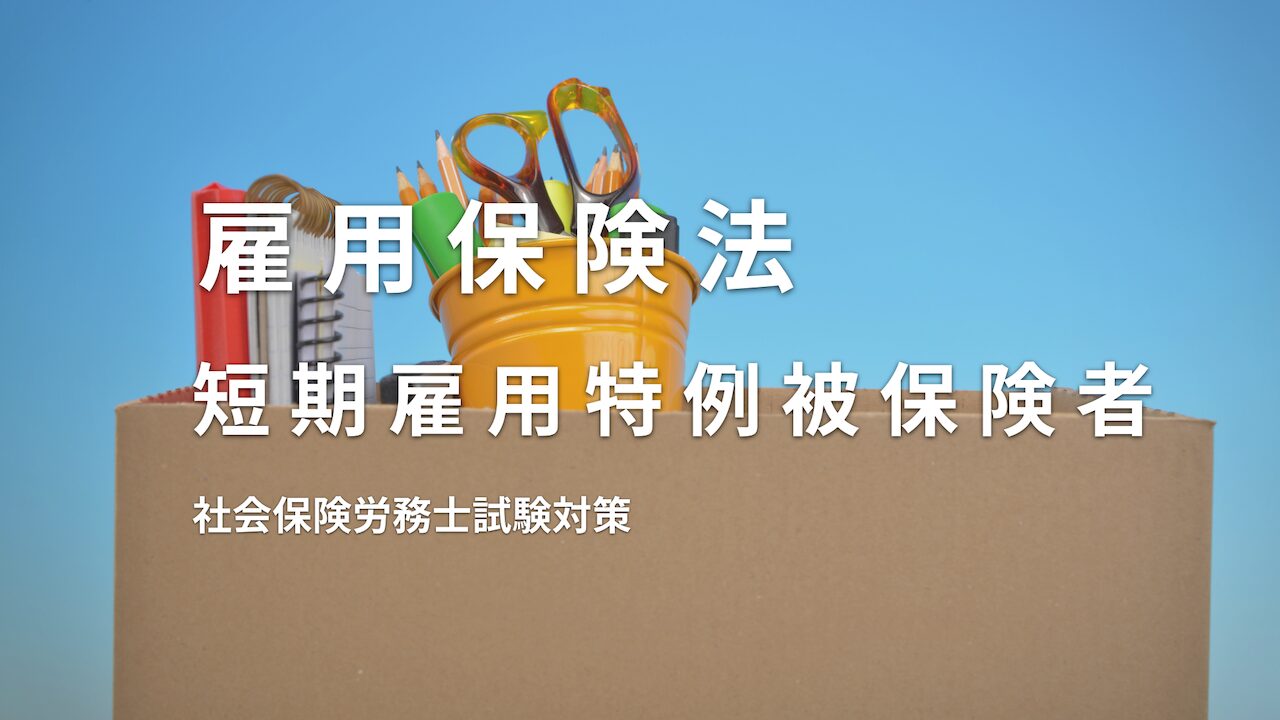※現在リライトです
雇用保険法の失業等給付から高年齢被保険者の求職者給付について解説します。前回は、失業等給付のもっとも重たい一般被保険者の求職者給付について見てきました。今回の高年齢被保険者の求職者給付は、37条の2から37条の6という枝番で定められていることから、新しくできた制度であることがわかります。どのような制度があるのか見ていきましょう。
高年齢被保険者
・65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する(37条の2第1項)。
→65歳以上の被保険者が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給します。
高年齢受給資格
・高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、支給する(37条の3第1項前段)。
→一般被保険者の基本手当の原則が、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったことと比較しておきましょう。
高年齢求職者給付金
・高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を受給資格者とみなしてその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(認定があった日から期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあった日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする(37条の4第1項)。
① 1年以上 50日
② 1年未満 30日
→読みにくいので補足します。まず、「受給資格者とみなして」という表現について、「受給資格者」というのは、一般被保険者に使う用語です(高年齢被保険者のときは「高年齢受給資格者」といいます)。そのため、ここでは「受給資格者とみなして」という表現を使っています。
そして、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に、算定基礎期間に応じ、定める日数を乗じて得た額とします。算定基礎期間が1年以上あれば50日、1年未満の場合は30日を乗じて得た額になります。括弧書きとして、認定があった日から後述する期間の最後の日までの日数が、50日や30日に満たない場合は、最後の日までの日数に相当する日数になります。たとえば、算定期間が1年以上あっても、最後の日までの日数が40日しかなければ、540日までとなるということです。
・算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を基準日とみなして算定されることとなる期間に相当する期間とする(37条の4第3項)。
→ここも一般被保険者のものを使っています。一般被保険者のときと同じ概念で計算すると考えれば問題ありません。なお、「基準日」というのは、「離職の日」のことをいいます(20条1項1号括弧書き)。
・高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない(37条の4第5項)。
→これが、先ほどの期限になります。高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、失業の認定を受ける必要があります。
失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。なお、高年齢受給資格者に対しては、基本手当、各種延長給付、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の支給がなされないのは当然であり、また、就業促進手当(常用就職支度手当は除く)も支給されない(行政手引54201)。
行政手引2270参照
高年齢被保険者の特例
・次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる(37条の5第1項、規則65条の7)。
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
② 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
③ 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数[5時間]以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
→この条文は、通常の定義だと高年齢被保険者に該当しない方を、特例として高年齢被保険者にしてあげるものです。まず、2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者です。次に、ひとつの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であることです。そして、2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であることです。
65歳以上になると、フルタイムで働く方はほとんどいません。そうすると、1週間の所定労働時間が20時間未満が多くなり、雇用保険の適用除外となってしまいます(6条1号)。しかし、それではかわいそうなので、2つの仕事を合わせて1週間の所定労働時間の合計が20時間以上あれば、厚生労働大臣に申し出ることによって、高年齢被保険者となる特例を定めています。
2号について、「一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること」となっているのは、20時間以上であれば、原則通り高年齢被保険者の対象となるからです。
なお、規則で定められていることなので優先度は下がりますが、特例の濫用を防ぐために、ひとつの事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限られます。たとえば、ひとつの職場が18時間、もうひとつの職場が2時間のようなものは認められないということです。
参考:離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>|厚生労働省
参考:高年齢被保険者に対する求職者給付|厚生労働省