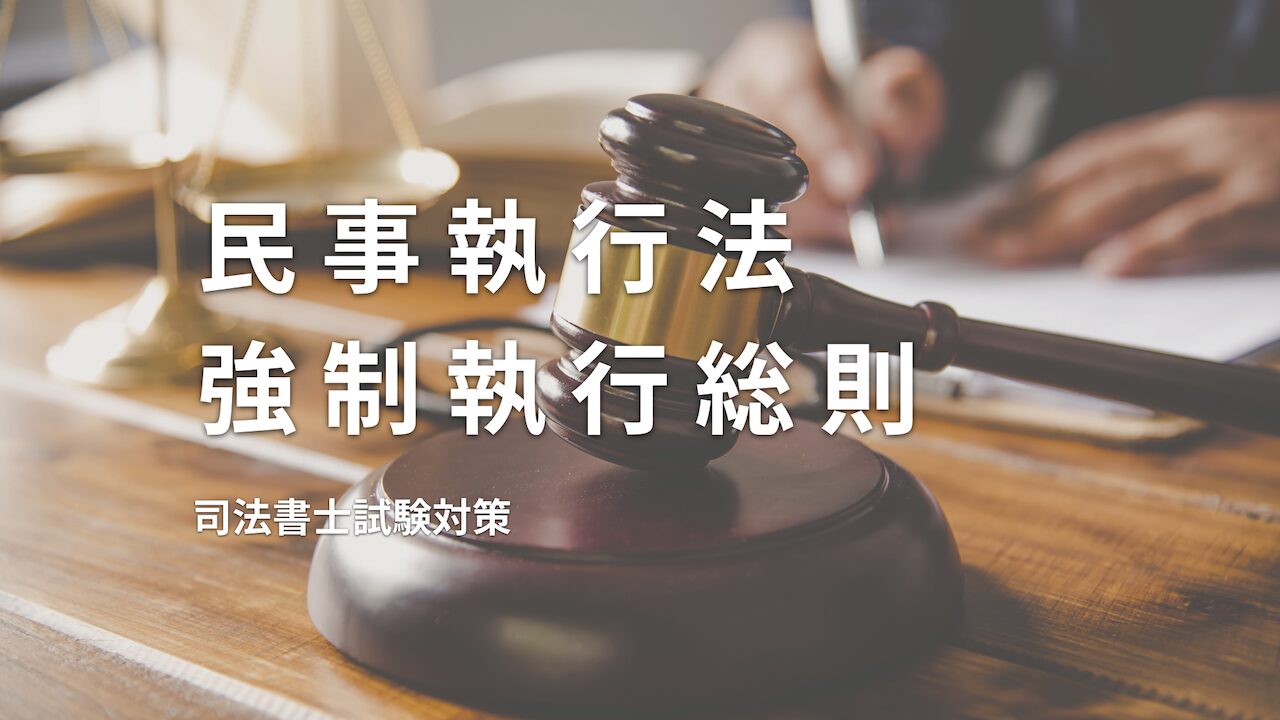民事執行法の総則について解説します。民事執行法は、全5章で構成されています。今回は、民事執行法の全体について定めている総則を見ていきましょう。
趣旨
民事執行法は、強制執行や担保権の実行など民事執行について定めている法律です。民事訴訟により、「被告は,原告に対し,100万円を支払え。」といった判決文が得られます。しかし、これは権利があるというだけで、被告に対して強制力があるわけではありません。つまり、被告が支払うとは限らないということです。そこで、民事執行法により、確定判決などをもとに、強制執行をすることができるようになっています。民事執行法では、この手続等について学んでいきます。
参考:民事執行手続 | 裁判所
執行機関
執行官とは、各地方裁判所に置かれ、裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う者です(裁判所法62条2項、3項)。執行官が具体的にどのようなことをするかは、条文を読み進める中で確認していきましょう。
執行裁判所
任意的口頭弁論
民事訴訟を想像するとわかりやすいですが、すでに口頭弁論をしてきているので、執行裁判所のする裁判では、口頭弁論を経ないですることができるとされています。
審尋
執行抗告
民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる(10条1項)。
執行抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない(10条2項)。
執行異議
民事執行法における不服申立てである執行抗告と執行異議について定められています。特別の定めがあるものに限り、執行抗告ができ、それ以外のものは、執行異議となっているのがわかります。
専属管轄
具体的に、専属がどのように定められているかは、学習を進める中で把握していきましょう。
民事訴訟法の準用
民事執行法を学習するとき、まったく別のものを学習すると考えると大変だと思います。条文でも民事訴訟法を準用するとあるので、あくまで民事訴訟の次の段階、つまり権利を実行するところの話なんだというくらいで捉えておくと、理解しやすいはずです。なお、民事訴訟法の第1編から第4編は、それぞれ、総則、第一審の訴訟手続、上訴、再審です。