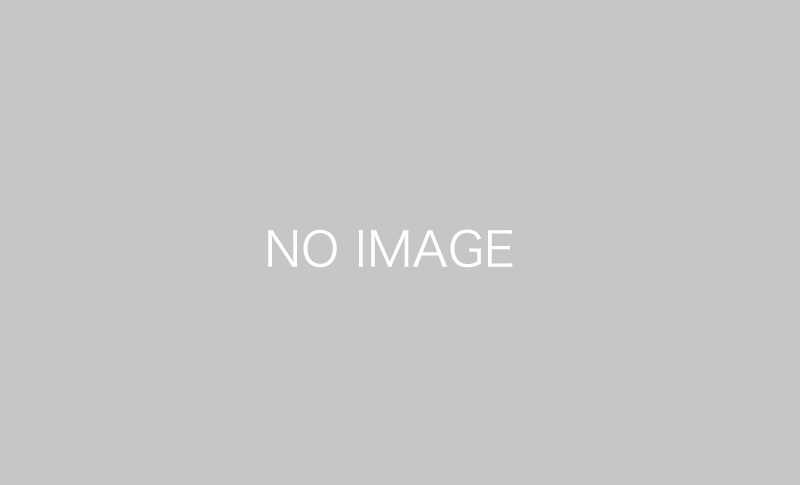不動産登記法の登記手続の権利に関する登記の用益権に関する登記から賃借権について学習します。
賃借権の登記の登記事項
賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号[権利に関する登記の登記事項]に掲げるもののほか、次のとおりとする(81条1項)。
① 賃料
② 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
③ 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
④ 敷金があるときは、その旨
⑤ 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
⑥ 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
⑦ 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物であるときは、その旨
⑧ 借地借家法第22条第1項前段、第23条第1項、第38条第1項前段若しくは第39条第1項、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条第1項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
1号:賃料
1号について、賃料を登記します。
民法を確認しておきましょう。
永小作権と同じように、賃料を支払うことが契約の内容のひとつとなっていることがわかります。
2号:存続期間又は賃料の支払時期の定め
2号について、賃貸借の存続期間は、50年を超えることができません(民法604条1項)。
3号:賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定め
3号について、これまで見てきた地上権、永小作権、地役権は物権ですが、賃借権は債権であり、賃貸借契約(民法601条)に基づく権利です。そのため、原則として賃借権の譲渡や転貸は認められず、貸主の承諾が必要になります(民法612条1項)。賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定めを登記します。
一方、永小作権は、物権であるため原則として譲渡や転貸が自由ですが(民法272条本文)、特約を設けることでこれを制限することも可能です(同但書)。賃借権と永小作権では、譲渡・転貸に関する原則と例外が逆になっている点に注意しましょう。
6号:建物の所有
6号について、土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨を登記します。
7号:事業用定期借地権
7号について、地上権のところで学習したように、借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物、つまり事業用定期借地権であるときは、その旨を登記します。
8号:定期借地権の特約等
8号について、同じく地上権のところで学習したように、借地借家法22条1項前段(定期借地権)、23条1項(存続期間30年以上50年未満の事業用定期借地権)の特約があるときは、その旨を登記します。
また、38条1項前段は、公正証書による等書面によって契約をするときは、契約の更新がないこととする旨を定めることができる定期建物貸借について定めたもの、39条1項は、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる取壊し予定の建物の賃貸借について定めたものです。
ほか、試験対策上、重要性は下がりますが、高齢者の居住の安定確保に関する法律52条1項は、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる終身建物賃貸借について定めたもの、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法7条1項は、大規模な災害により借地上の建物が滅失した場合、存続期間が5年以下、かつ、契約の更新がないなど被災地短期借地権について定めたものです。これらの条文を覚える必要はありませんが、賃借権について、特別の定めがあるときは、その旨を登記しておく必要がある点をおさえておきましょう。