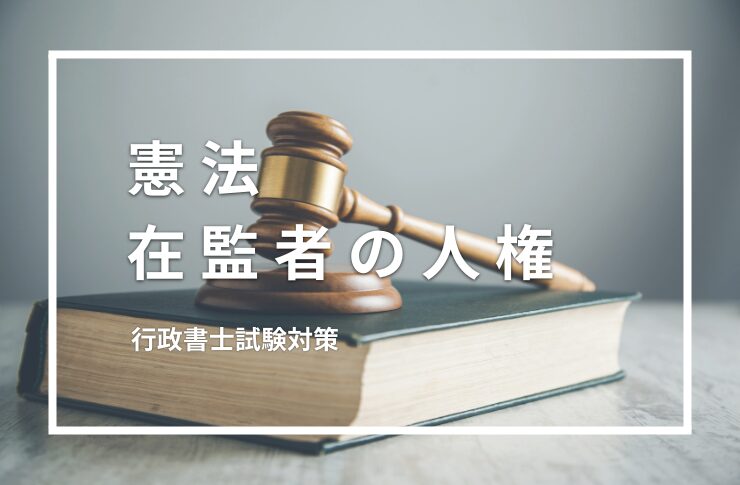ここでは、人権の限界から公務員の人権について学習します。前回、人権の限界のうち、公共の福祉についてみてきました。今回は、特別の制約から公務員の人権についてみていきましょう。
特別の制約
人権の限界は、大きく2つに分けられます。
- 公共の福祉
- 特別の制約(公務員の人権、在監者の人権)
公共の福祉については、前回学習しました。公務員や在監者(刑務所などに収容されている者)は、特別の制約が許されると解されています。どのようなことが問題となるのか、判例をみていきましょう。
猿払事件
国家公務員法102条1項は、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と規定しています。
北海道猿払村(さるふつむら)の郵便局に勤務する事務官が、選挙に際し、選挙ポスターを掲示・配布したことによって起訴されました。そこで、公務員の政治活動の自由が争われました。
判例は、次のように述べました。
行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。
国公法102条1項及び規則による公務員に対する政治的行為の禁止が右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の3点から検討することが必要である。
判例は、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならないとしています。そして、必要やむをえない限度にとどまるものかを判断するにあたっては、①禁止の目的、②この目的と禁止される政治的行為との関連性、③政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の3点から検討することが必要であるとしています。
堀越事件
社会保険庁に年金審査官として勤務していた被告人が、衆議院総選挙に際し、日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配布していた行為が、国家公務員法、人事院規則に違反するとして起訴されました。そこで、国家公務員法と人事院規則の罰則規定の合憲性が争われました。
なお、この事件は、被告人の名前から「堀越事件」、被告人が目黒社会保険事務所に勤務していたことから「目黒事件」と書かれていることがありますが、どちらも同じものです。
「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、同項(編注:国家公務員102条1項)はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。(中略)
本件罰則規定による政治的行為に対する規制が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかによることになるが、これは、本件罰則規定の目的のために規制が必要とされる程度と、規制される自由の内容及び性質、具体的な規制の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである。(中略)
公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為を禁止することは、国民全体の上記利益の保護のためであって、その規制の目的は合理的であり正当なものといえる。他方、本件罰則規定により禁止されるのは、民主主義社会において重要な意義を有する表現の自由としての政治活動の自由ではあるものの、禁止の対象とされるものは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為に限られ、このようなおそれが認められない政治的行為や本規則が規定する行為類型以外の政治的行為が禁止されるものではないから、その制限は必要やむを得ない限度にとどまり、前記の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲のものというべきである。(中略)。
公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当である。
本件配布行為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。
堀越事件を整理すると、被告人は、国家公務員法、人事院規則に違反するとして起訴されましたが、この国家公務員法、人事院規則の合憲性が争われました。
まず、判例は、「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指すとし、その具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当であるとしました。なお、人事院規則とは、国家公務員の任免や定年、身分保障、懲戒、勤務条件などについて定めた規則のことです。
そして、合憲性については、目的のために規制が必要とされる程度と、規制される自由の内容及び性質、具体的な規制の態様及び程度等を較量して決せられるべきとしました。そのうえで、本件罰則規定を合憲としました。ここまでがひとつの区切りになります。
次に、国家公務員法、人事院規則が合憲であるという前提で、被告人の行為が、「政治的行為」にあたるかを判断しました。判例は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であるとしました。
そのうえで、被告人は管理職的地位になく、裁量の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、行われたものであり、公務員による行為と認識できないことから、政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえないとしました。
行政書士試験向けの基本書では、堀越事件について、合憲性が争われたとしながら、その記述があいまいであるものや被告の行為を中心に書いているものがあり適当でないため、整理しました。