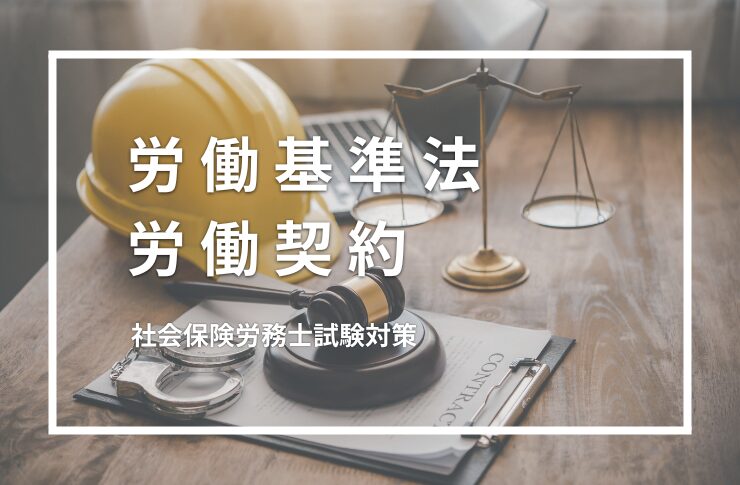(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)
労働基準法の災害補償について学習します。なお、「必要な療養」や「治った」など、ところどころ定義があいまいな用語があるかもしれませんが、労働基準法の時点では深く理解する必要はなく、労災法の学習をしたときに理解すれば十分です。ここでは、災害補償は、労災法によってカバーされるという大枠をつかんでおけば問題ありません。
労働基準法>災害補償
療養補償
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない(75条1項)。
休業補償
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない(76条1項)。
障害補償
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならない(77条)。

ここでは、労働者災害補償保険法の業務災害から業務上の負傷について学習します。
まず、労災法が保険給付の対象としているものを整理しましょ...
遺族補償
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない(79条)。
葬祭料
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない(80条)。
打切補償
補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後は補償を行わなくてもよい(81条)。
打切補償は、解雇制限のところに関連してきます。具体的には、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間解雇してはならない」(19条1項本文)となっていますが、「使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない」(19条1項但書)。として、打切補償を支払った場合の例外について定めています。
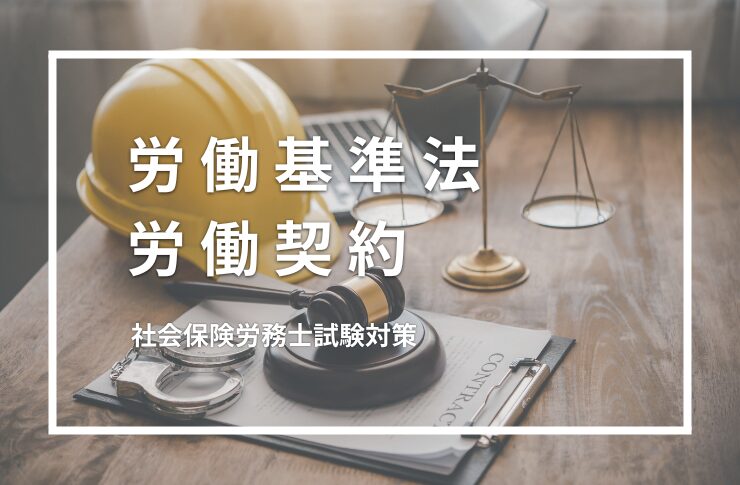
ここでは、労働基準法の労働契約について学習します。
労働基準法>労働契約
この法律違反の契約
この法律で定める基準に達しない労働条...
分割補償
使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、6年にわたり毎年補償することができる(82条)。
労働災害の補償額が高額であることから、6年間にわたり、分割して補償することができるようになっています。また、こうして労働災害の補償額が高額になってしまうことから、労災保険があるというのを考えると、労災法が理解しやすくなると思います。
他の法律との関係
労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる(84条1項)。
労働基準法では、災害補償について定められています。また、これを保険でさらに手厚く補償したものが労災法で規定されています。そこで、労災法に基づいて災害補償に相当する給付がされるときは、使用者は、労働基準法による補償の責を免れることになっています。使用者は、労働者に何かあったときに補償をしなくてはいけないので、労災法に入る義務があるということです。
「ウチの職場は労災に入っていないから…」と心配する声を聞いたことがある方もいると思いますが、その場合は労災法による補償ではなく、原則に戻って労働基準法によって補償が受けられることになります。つまり、いずれにせよ、労働者が業務上負傷した場合は、使用者は、使用者の費用で療養等を行わなければならないということです。
参考:労災保険と労基法上の災害補償の比較|厚生労働省

労働基準法の就業規則について学習します。
労働基準法>就業規則
作成及び届出の義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者...