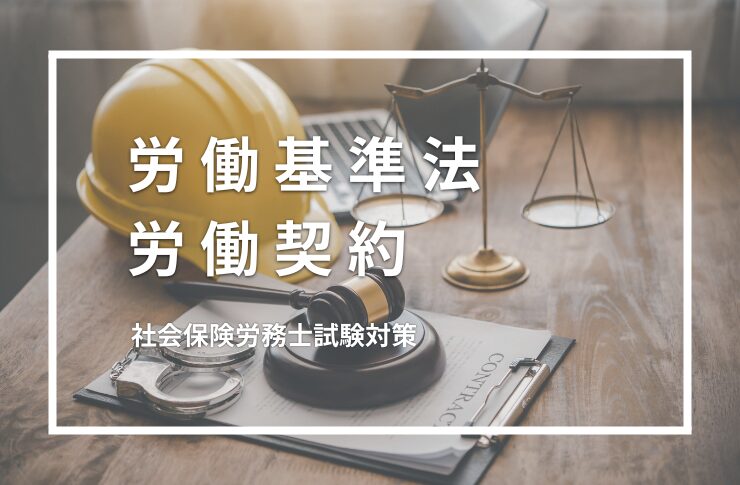労働基準法の就業規則について学習します。
作成及び届出の義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする(89条)。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
④退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑤臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
⑥労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
⑦安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑧職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑩表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑪前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
1〜4については、必ず定めておかなければならないことから、絶対的記載事項といいます。
5〜11については、「定めをする場合においては」記載することとなっていることから、相対的記載事項といいます。
通達を確認しましょう。
・就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労動者とそれ以外の労動者とを合わせて常時10人以上の労動者を使用している派遣元の使用者である(昭61.6.6基発333号)。
・同一事業場内の一部の労動者につき別の就業規則を作成することは差し支えないが、それも併せたものが法第89条の就業規則である(平11.3.31基発168号)。
・記載を要する事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、当該就業規則を作成し届出ても使用者の同条違反の責は免れない(平11.3.31基発168号)。
・法第41条第3号[監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの]の許可を受けた者についても本条は適用されるのであるから、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならない(昭23.12.25基収4281号)。
・労動者の請求により欠勤を年次有給休暇に振替えることは違法でないが、当該取扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である(昭63.3.14基発150号)。
作成の手続
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない(90条1項)。
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない(90条2項)。
通達を確認します。
・同一事業場に2種の就業規則がある場合それは単に一の就業規則を形式上分けたものに過ぎず、意見を聴くのは、全労動者の過半数代表者の意見を聴かなければならない(昭63.3.14基発150号)。
・労働組合が故意に意見を表明せず又は意見書の署名又は記名押印を拒否するような場合にも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り届出を受理する(昭23.5.11基発735号)。
制裁規定の制限
労働者の生活を保障するために、減給の制裁について制限されています。まず、制裁1回の額は、平均賃金の1日分の半額までとされています。たとえば、1日12,000円なら最大6,000円ということです。次に、減給の総額は、1賃金支払期における賃金の総額、つまり1か月分のお給料の10分の1までとされています。たとえば、月のお給料が30万円なら、3万円までということです。この例だと、5回分までは減給できますが(3万円)、6回目以降は減給できないことになります。この場合、翌月以降に減給することになります。
通達を確認しましょう。
・就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労動者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する本条の規定とは関係がない(昭23.7.3基収2177号)。
・就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給せしめないという欠格条件を定めても、本条には触れない(昭26.3.31基収938号)。
・平均賃金については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算定すべき事由の日とする(昭30.7.19 29基収5875号)。
法令及び労働協約との関係
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない(92条1項)。
行政官庁[所轄労働基準監督所長]は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる(92条2項、規則50条)。
労働契約との関係
これで、各関係がそろいました。まず①法令(強行法規)、次に②労働協約があります。そして、労働契約法第12条は、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と規定しています。ここから、③就業規則、④労働契約の順に優先されることがわかります。