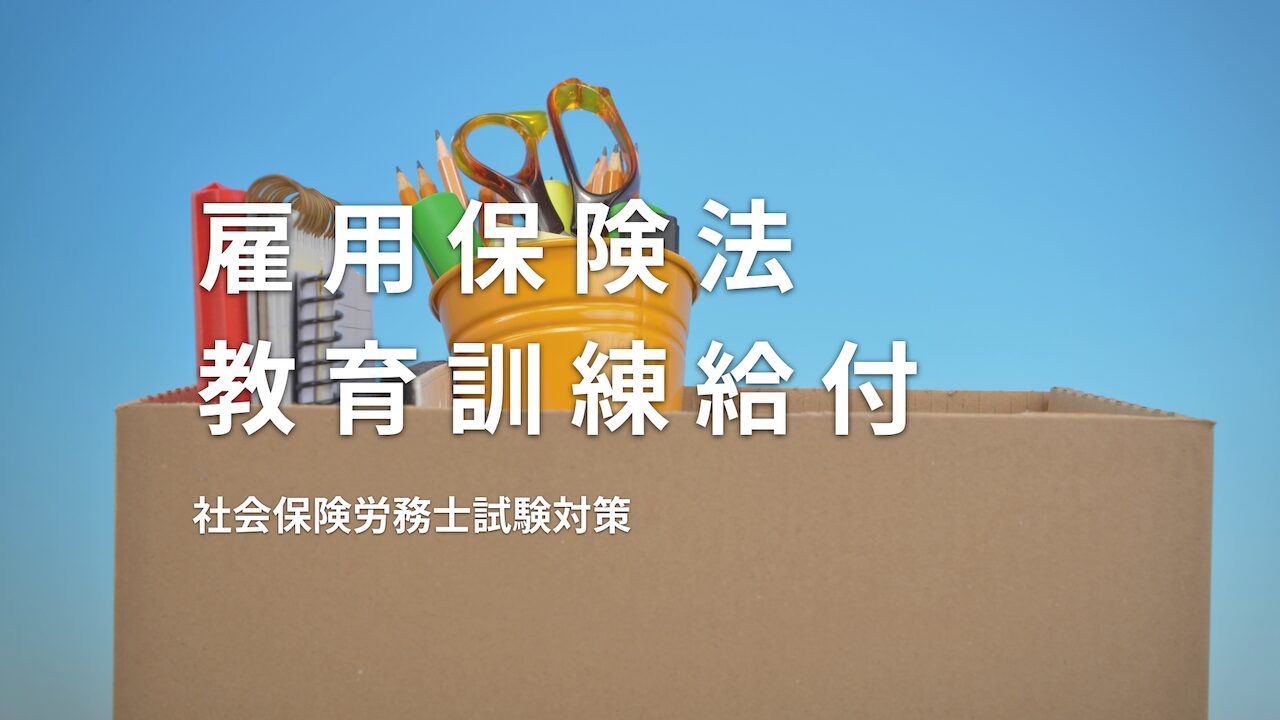※現在リライト中です
雇用保険法の失業等給付から就職促進給付について解説します。これまでは、被保険者が失業した場合に給付されるものについて見てきましたが、今回は就職を促進する給付についてです。どのような種類があるか、ひとつずつ押さえていきましょう。
就業促進手当
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する(56条の3第1項、規則82条の3第2項)。【改正】
① 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
② 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの[45歳以上の受給資格者等]
1号は、基本手当の支給残日数を3分の1以上残して職業に就いているので、手当をあげましょうというものです。手当を支給することによって、早期の就業を促進するのが目的です。
また、就業促進手当は、不正を防止するために、厚生労働省令で定める基準があります。
厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする(規則82条1項)。
(1) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(2) 待機期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
(3) 受給資格に係る離職について法第33条第1項[給付制限]の規定の適用を受けた場合において、法第21条[待機]の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
(4) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
離職前の事業主に再び雇用されたり、雇入れをすることを約束した事業主に雇用されたりすると、就業促進手当が不正に支給されてしまうため、基準が設けられています。3号について、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより給付制限の規定を受けた場合において、待機期間の満了後1箇月の期間内は、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたことが要件とされています。これもまた、無制限に認めることによって、通謀して就業促進手当が支給されてしまわないようにしています。
2号は、安定した職業に就いた受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものです。また、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限られています。1号とは異なり、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であるのがポイントです。1号は、早く仕事に就いたから手当を支給するのに対して、2号は、新しい仕事に就く際の金銭的な負担を軽減するために設けられています。新しい仕事に就く際に必要となるものに手当を支給することで、結果的に就業を促進するのが目的となります。
2号についても、不正を防止するために、厚生労働省令で定める基準が定められていますが、本試験対策上、ここは割愛します。
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(「受給資格者等」という。)が、職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内[3年]の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当は、支給しない(56条の3第2項、規則82条の4)。
就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする(56条の3第3項、規則83条の2、規則83条の3)。
① 第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額
② 第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下この号において「早期再就職者」という。)にあっては、10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)【改正】
③ 第1項第2号に該当する者 基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
1号イについて、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額となります。
1号ロについて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となります。1号ロは、括弧書きが多いので整理しましょう。まず、基本は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た数です。この時点でややこしいので、具体的に見てみましょう。支給残日数に相当する日数が100日の場合、「基本手当日額」に「支給残日数に相当する日数」(100日)に「10分の6」を乗じて得た数(60)を乗じて得た額です。
括弧書きとして、所定給付日数の3分の2以上である「早期再就職者」の場合は、10分の6ではなく、10分の7をかけます。より多くの所定給付日数を残した状態で再就職したので、通常より1割分多く支給してもらえるということです。
さらに、もうひとつ括弧書きがあります。この括弧書きは、再就職した職場の賃金が、前の職場の賃金より低い場合に埋め合わせるものです。このイメージを持って読み進めましょう。
「同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額」とされています。
厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた法第17条[賃金日額]に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回った者とする(規則83条の2)。
厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じて得た額とする(規則83条の3)。
算定基礎賃金日額(前の職場の賃金)からみなし賃金日額(今の職場の賃金)を減じて得た額に支払の基礎となった日数(180日など)を乗じて得た額を加えます。そうすると、差額分を埋め合わせることができるのがわかります。もっとも、この加える額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の2を乗じて得た数を乗じて得た額が限度となります。
限度と言われてもピンとこないと思うのでおさらいしましょう。1号ロの方は、10分の6、または早期再就職者は10分の7の就業促進手当がもらえるのでした。ここにお給料が前の職場と比べて下がってしまった方は、10分の2を限度として加算されるということです。つまり、10分の8、または早期再就職者は10分の9もらえることになります。
試験対策として、規則の細かい部分まで問われることは少ないので、まずは法律の範囲でおさえて、余裕があったら規則の部分にも目を通すといった具合に学習を進めましょう。
2号について、基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額となります。本試験対策として、厚生労働省令で定める額については割愛します。
第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(56条の3第4項)。
第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(56条の3第5項)。
→1号イの場合は、支給した日数に相当する日数分、1号ロの場合は、基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされます。難しく考えてしまいがちですが、就業促進手当が支給されたら、その分、基本手当が支給されたものとみなされるということです。
移転費
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する(58条1項)。
移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める(58条2項)。
求職活動支援費
求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する(59条1項、規則95条の2)。
① 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動[広域求職活動費]
② 公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動[短期訓練受講費]
③ 求職活動を容易にするための役務の利用[求職活動関係役務利用費]
給付制限
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる(60条1項)。
→基本手当のときと同じように、不正をしたなどのときは、就職促進給付を支給しません。
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者が、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する(60条2項)。
→基本手当のときと同じように、給付制限をされるのは、あくまでその受給資格についてなので、新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を支給します。