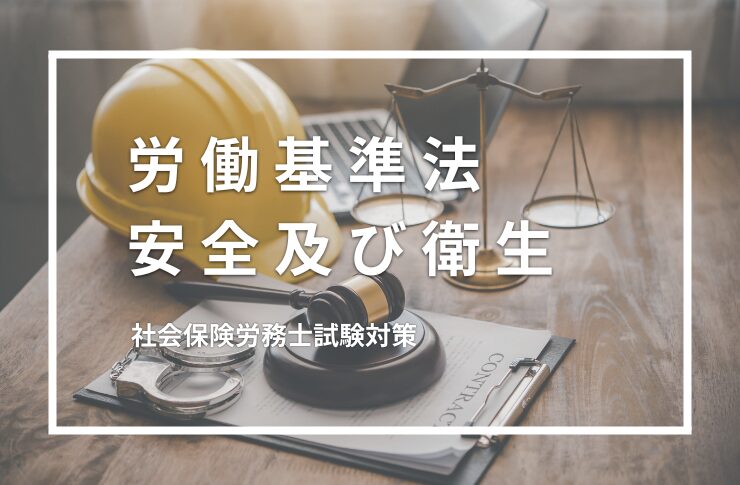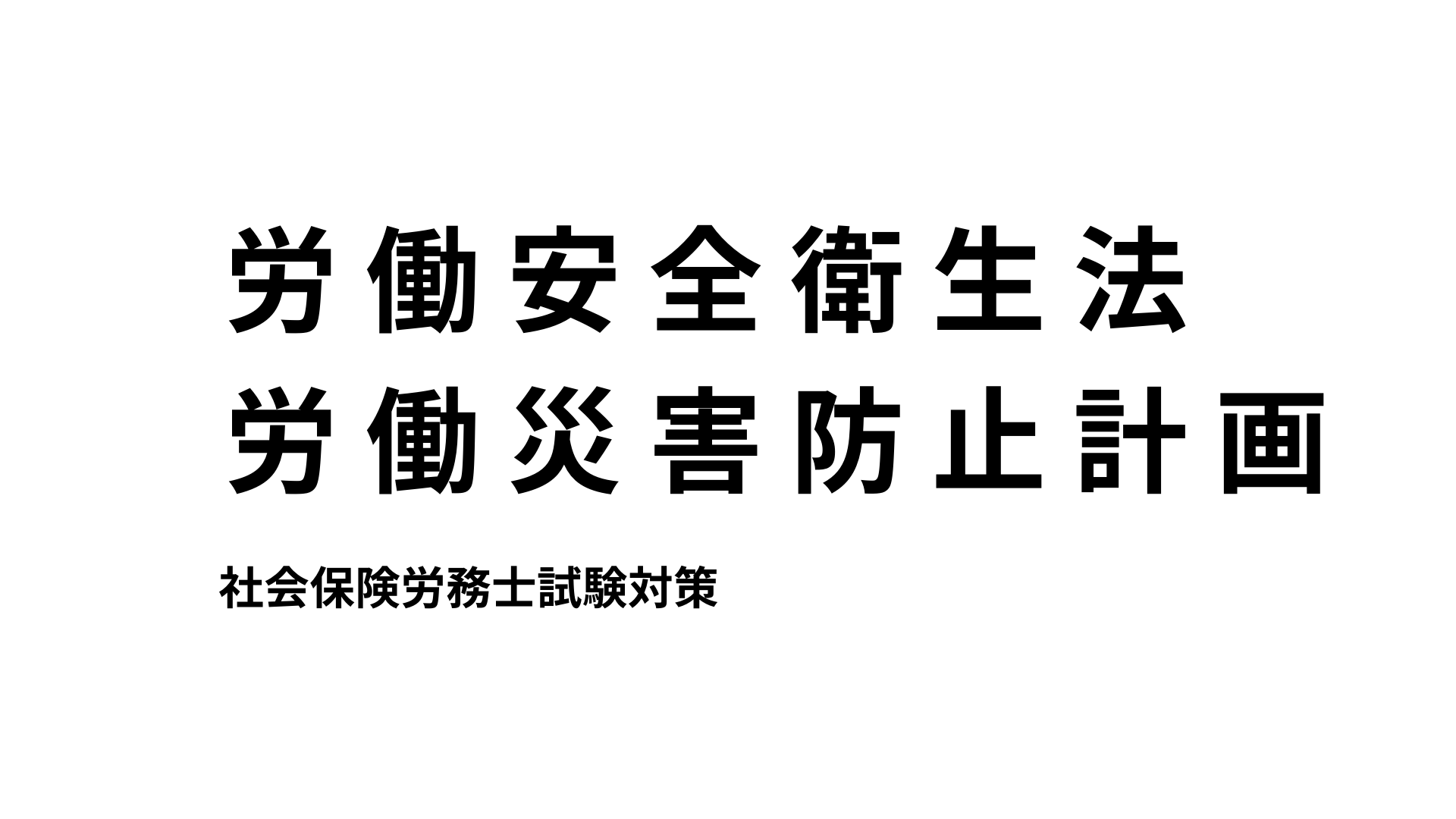労働安全衛生法の総則について学習します。今回から労働安全衛生法に入ります。労働の安全と衛生については、もともと労働基準法の第5章「安全及び衛生」に規定されていましたが、労働安全衛生法が昭和47年に制定され、労働基準法の条文は削除されました。つまり、労働安全衛生法は、労働基準法の兄弟のように考えることができます。
本試験の択一式問題では、労働基準法から7問、労働安全衛生法から3問出題されます。労働安全衛生法を完璧に覚えようとするのは難しいので、重要な条文を学習し、3問中2問正解できるくらいの気持ちで臨みましょう。
目的
参考:安全・衛生 |厚生労働省
定義
① 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
② 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者をいう。
③ 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
③の2 化学物質 元素及び化合物をいう。
④ 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
「労働者」の定義は、労働基準法と同じです。労働安全衛生法は、労働基準法から分化してできたイメージを持つと理解しやすいと思います。
労働基準法に出てきた「使用者」の定義「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と混同しないように気をつけましょう。
事業者等の責務
事業者や労働者などそれぞれについての責務が定められています。
事業者に関する規定の適用
いわゆるジョイントベンチャーについて定めた条文です。仕事を共同連帯して請け負った場合は、責任の所在が曖昧になってしまうため、そのうちの1人を代表者として定め、都道府県労働局長に届け出ることとされています。
条文の理解がしにくいので補足します。前述のように、仕事を共同連帯して請け負った場合は、責任の所在が曖昧になってしまうため、そのうちの1人を代表者として定める必要がありました。その結果について、定めています。
①当該事業、つまり共同連帯して請け負った事業の仕事を「代表者のみの事業」とみなします。共同連帯して請け負っているにもかかわらず、代表者として定めた者の事業とします。
②当該代表者、つまり代表者として定めた者のみ「当該事業の事業者」とみなします。
③当該事業の仕事に従事する労働者は、当該代表者、つまり代表者として定めた者が使用する労働者とみなします。
条文だけ読むととてもややこしく見えますが、労働安全衛生法としては、誰が代表者なのかはっきりしない状態を避けたいのです。つまり、労働災害が起きたときに誰が責任をとるべきなのかを決めておきたいということです。
- 当該事業を代表者のみの事業とみなす
- 当該代表者のみを当該事業の事業者とみなす
- 当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とみなす
こうすると、条文が読みやすくなります。