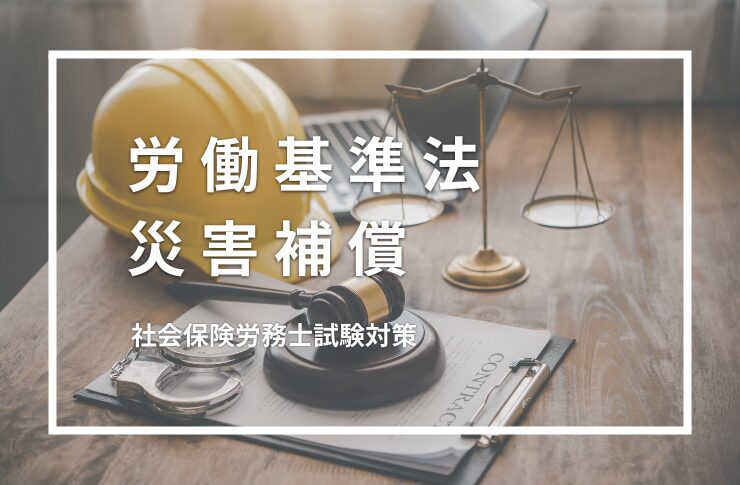労働基準法の雑則について学習します。雑則とは、細かい事項についての規則です。本試験対策としては、周知義務や労働者名簿、賃金台帳、時効をおさえておきましょう。
法令等の周知義務
労働者名簿
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない(107条1項)。
記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない(107条2項)。
労働者名簿の作成が義務付けられています。
賃金台帳
賃金台帳の作成が義務付けられています。細かい項目についておさえる必要はありませんが、名簿については日日雇い入れられる者は除かれていましたが、賃金台帳は日日雇い入れられる者も含まれる点はおさえておきましょう。金銭の管理というのを考えれば腑に落ちると思います。
記録の保存
付加金の支払
たとえば、100万円の未払金がある場合、同一額の付加金つまり、もう100万円、合計200万円の支払を命ずることができるということです。
時効
時効についてです。本則で定められた部分と附則で定められた部分が混ざっているので整理します。
- 賃金の請求権:5年間
- 災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。):2年間
まず、賃金に関しては保護性が高いため5年間だとおさえましょう。そして、それ以外の請求権は2年間となります。これが原則です。「その他の請求権」で賃金の請求権を除くものには、たとえば、退職時の証明や金品の返還、年次有給休暇請求権などがあります。
次に、附則部分です。
- 退職手当の請求権:5年間
- 賃金(退職手当を除く。)の請求権:3年間
- 災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。):2年間
賃金のうち、退職手当の請求権については5年間で同じです。これは、退職手当は紛争が生じやすいことや退職労働者の権利行使は必ずしも容易であるとはいえないことが理由としてあげられます。
(退職手当を除く)賃金の請求権については、2020年に民法が改正される前までは2年間でした。つまりその他の請求権と同じということです。そして、改正民法では、契約に基づく債権の消滅時効期間は原則5年間とされました。そこで、賃金の請求権も5年間とされました。しかし、これまで2年だったものが、いきなり5年になると使用者側にとっても酷であるということから、当面の間は3年間とされています。
本試験対策としては、ここまでの理解で問題ありません。
参考「厚生労働省:賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」
適用除外
労働基準法は、労働者について定めているので、同居の親族のみを使用する事業と家事使用人については、適用されません。