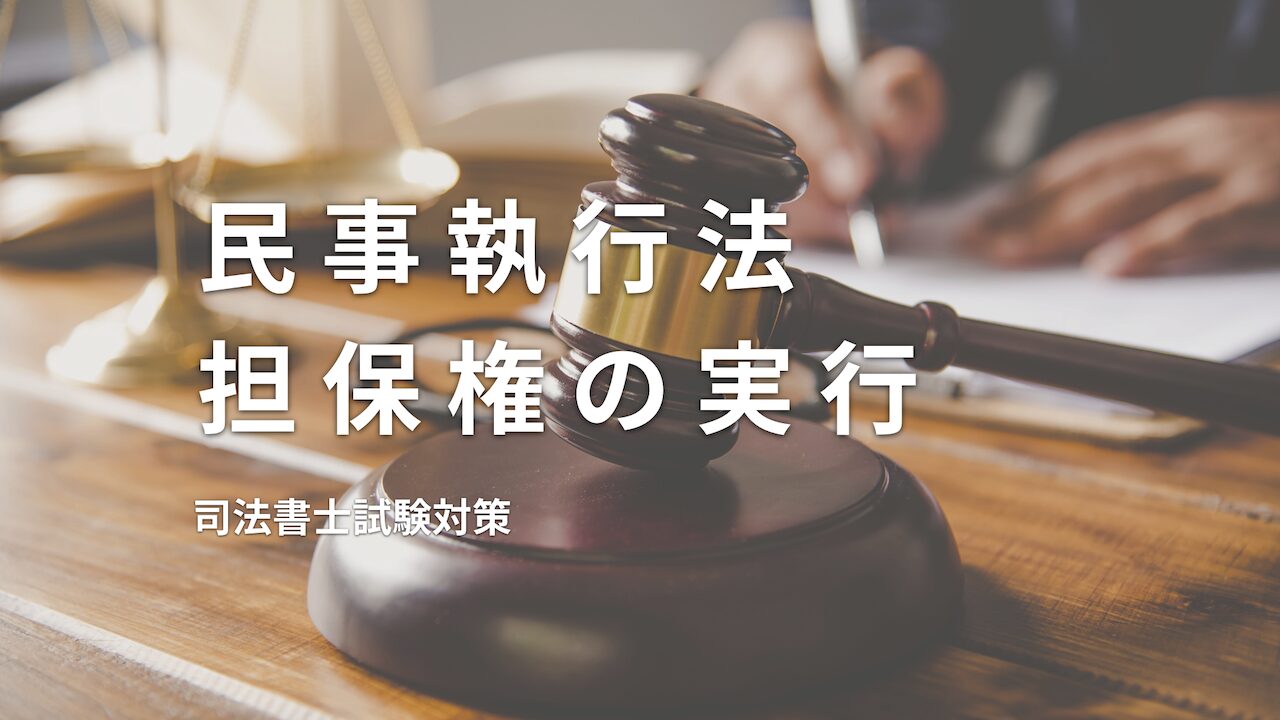民事執行法の金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行について解説します。前回まで、民事執行法の中心となる金銭の支払を目的とする債権についての強制執行でした。今回は、金銭の支払を目的としない請求権についてです。どのようなものがあるか、条文を読みながら具体的にイメージしていくようにしましょう。
不動産の引渡し等の強制執行
動産の引渡しの強制執行
不動産の引き渡し等の場合は、執行官が債務者の不動産等の占有を解いて債権者にわたす、動産の引き渡しの場合は、執行官が債務者から取り上げて債権者に引き渡す方法で行われます。これで、金銭の支払を目的としない請求権がどのようなものかわかります。
代替執行
次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う(171条1項)。
①作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
②不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
代替執行とは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者が第三者に債務の内容を実施させることです。作為とは、人の積極的な行動です。たとえば、建物を取り壊して明け渡さなければならないのに、債務者が債務を履行しない場合、第三者に取り壊させます。不作為とは、人が積極的な行動をしないことです。かんたんにいうと、何かをしないことです。ここでは、何かをしないことを目的とする債務、たとえば、日照を妨害する建物を建てないことを目的とする債務がされない場合、つまり、日照を妨害する建物を立ててしまった場合、債務者がした行為の結果を除去、建物を除去します。
間接強制
作為又は不作為を目的とする債務で前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う(172条1項)。
一旦、解説、その後2項以下
事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる(172条2項)。
執行裁判所は、前2項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない(172条3項)。
第1項の規定により命じられた金銭の支払があった場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない(172条4項)。
第1項の強制執行の申立て又は第2項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる(172条5項)。
間接強制は、扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例のところに出てきました。強制執行ができないものについての強制執行は、債務の履行がされないとき、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行います。これにより、債務者に対して心理的圧迫を加えることができます。
間接強制については、細かく問われることがあるので、余裕があったら2項以下も押さえておきましょう。内容については理解が難しいところはないと思うので、条文を読んでおきましょう。
子の引渡しの強制執行
子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う(174条1項)。
①執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法
②第172条第1項[間接強制]に規定する方法
執行裁判所及び執行官の責務
子の引き渡しの強制執行については、子の引き渡し、間接強制に規定する方法により行います。ただし、子の引き渡しについては、無理やり子を引き渡すのですから、子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければなりません。子は動産とは違うということです。