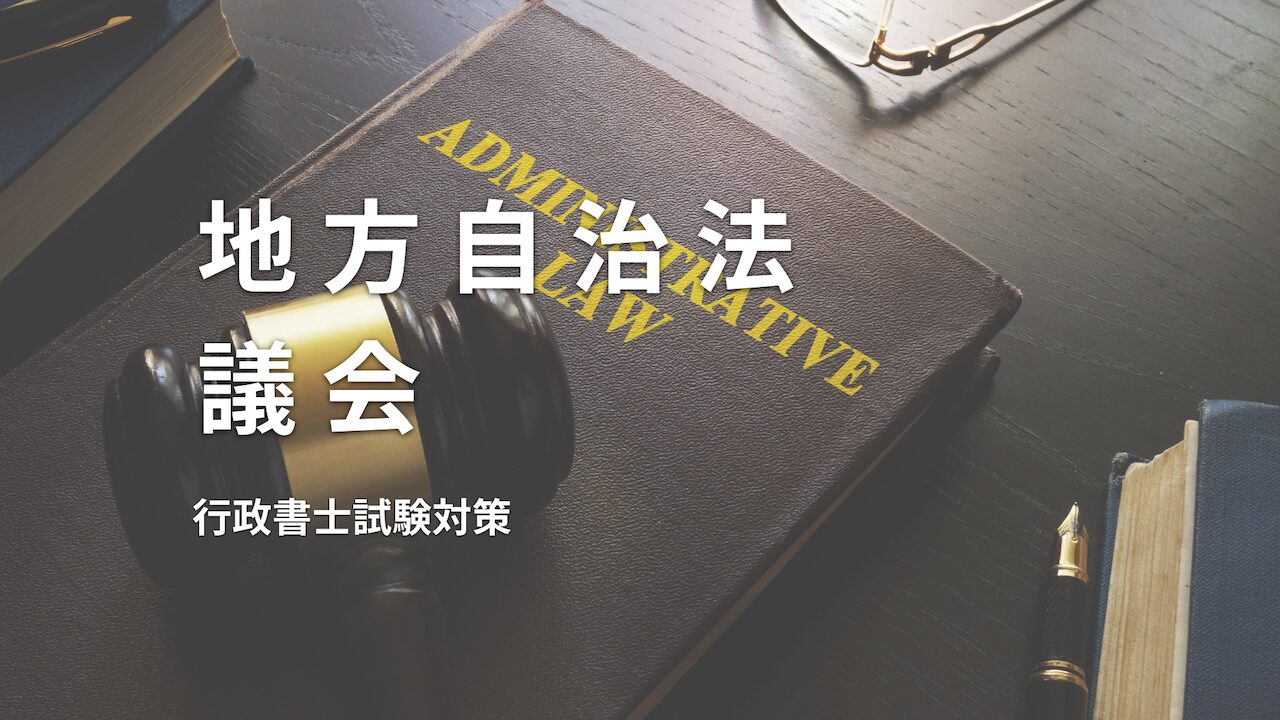行政書士試験の試験科目は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」(法令等科目)と「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」(基礎知識科目)の大きく2つに分けられます。このうち、基礎知識科目は、さらに4つに分けられます。
- 一般知識
- 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
- 情報通信・個人情報保護
- 文章理解
令和6年度の基礎知識の内容
まず、令和6年度の基礎知識の出題内容をおさらいしましょう。
- 問題47:政治(一般知識)
- 問題48:中東やパレスチナ(一般知識)
- 問題49:日本円の外国為替(一般知識)
- 問題50:日本における外国人(一般知識)
- 問題51:ジェンダー(一般知識)
- 問題52:行政書士法(行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令)
- 問題53:住民基本台帳法(行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令)
- 問題54:デジタル環境での情報流通(情報通信・個人情報保護)
- 問題55:欧米の情報通信法制(情報通信・個人情報保護)
- 問題56:デジタル庁(情報通信・個人情報保護)
- 問題57:個人情報保護法(情報通信・個人情報保護)
- 問題58:※省略(文章理解)
- 問題59:※省略(文章理解)
- 問題60:※省略(文章理解)
一般知識が5問、行政書士法等が2問、情報通信・個人情報保護が4問、文章理解が3問出題されています。
次に、問題ごとの出題内容をみていきましょう。
問題47:政治(一般知識)
政治に関する問題は、いわゆる一般常識です。「メディア・リテラシー」や「ポピュリズム」などの用語の意味がわかれば解ける問題でした。
問題48:中東やパレスチナ(一般知識)
中東やパレスチナに関する問題は、2023年パレスチナ・イスラエル戦争(2023年10月7日-)がはじまったことから、歴史を題材にしています。
問題49:日本円の外国為替(一般知識)
日本円の外国為替に関する問題は、2022年からはじまった円安を背景に、「ニクソン・ショック」や「プラザ合意」などこちらも歴史を題材にしています。高校の「公共」の教科書レベルの知識があれば解ける問題です。
問題50:日本における外国人(一般知識)
日本における外国人に関する問題は、憲法の「外国人の人権」の知識があれば、正解を導き出せるようになっていました。「特定技能」は、行政書士として外国人雇用を扱う方にとっては重要ですが、受験生のタイミングとしては、わからなくても問題ありません。
問題51:ジェンダー(一般知識)
ジェンダーに関する問題は、「ジェンダーキャップ指数」「レインボーフラッグ」「マタニティ・ハラスメント」、医学部の入学試験で女性が不当に減点されていたというニュースを知っていれば、解ける問題でした。
問題52:行政書士法(行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令)
行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令は、令和6年度から出題が始まったものです。予想されていた通り、行政書士法から出題されました。隣接資格の試験を考えると、来年度以降も1問は行政書士法から出題されることが予想されるので、行政書士法はひととおり学習しておきましょう。
問題53:住民基本台帳法(行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令)
もう1問は住民基本台帳法からの出題です。これを学習していた方は少ないと思うので、大人の受験生の方は、日常生活から予想したのではないかと思います。
問題54:デジタル環境での情報流通(情報通信・個人情報保護)
デジタル環境での情報流通に関する問題は、近年の用語から出題されました。毎年1問、いわゆる「バズワード」から出題されることが多いので、新しいデジタル関連の用語は調べるようにしましょう。
問題55:欧米の情報通信法制(情報通信・個人情報保護)
欧米の情報通信法制は難しかったと思います。
問題56:デジタル庁(情報通信・個人情報保護)
デジタル庁に関する問題、意外と難しい気がします…。
問題57:個人情報保護法(情報通信・個人情報保護)
個人情報保護法は、例年通りの出題です。
問題58-60:※省略(文章理解)
文章理解は省略します。
令和7年度に出題されそうな題材まとめ
令和6年度の問題をみてもわかるように、全体の傾向として、本試験の前年度(4月から3月)にあったことに関連して出題されることが多くあります。そこで、令和7年度の本試験に出題されそうな題材をいくつか選んでみたいと思います。もちろん、あくまで予想なので、正攻法の学習を進めましょう。
また、みなさんが考えた題材があれば、ぜひ教えてください。
能登半島
2024年(令和6年)1月1日に能登半島地震がありました。その後、9月には能登半島豪雨がありました。その地方特有のことが出題されると、住んでいる場所によって不平等が生まれるので、出題されるとしたら自然災害に関することではないかと思います。
百条委員会
兵庫県庁内部告発文書問題は、2024年3月頃に起きました。このとき話題になったのが、いわゆる「百条委員会」や「出直し選挙」です。基礎知識だけでなく、行政法の地方自治法としても出題される可能性があるため、地方議会について、どのようになっているか改めて整理しておきましょう。
パリオリンピック
2024年7月26日にパリオリンピックが開催されました。前回の東京オリンピック(2021年開催)のときは、「近代オリンピックと政治」の題材で出題されています。
再審
袴田事件について、2024年9月26日に再審無罪判決が言い渡され、10月9日に確定しました。行政書士が総務省管轄ということを考えると、再審について問うのは難しいかもしれませんが、基礎法学において裁判制度として出題されることも考えられます。
衆議院選挙
2024年10月27日に衆議院選挙がありました。選挙制度に関しては、憲法の統治でも重要な部分なので、日本の選挙制度、世界の選挙制度について整理しておきましょう。
アメリカ大統領選挙
2024年11月5日にアメリカ大統領選挙がありました。深く調べる必要はありませんが、歴代の大統領や「選挙人」など一般常識の範囲でおさえておきましょう。
大阪・関西万博
2025年4月13日から大阪・関西万博が開催されました。区分はいろいろありますが、大阪万博(1970年)、沖縄海洋博(1975年)、愛・地球博(2005年)など意識するのも面白そうです(『20世紀少年』の読みすぎかもしれませんが)。
基礎知識の対策
基礎知識の問題を見ると、「このくらいだったら解けそうだな」と思いませんか? 対策しやすいのは、文章理解の3問、行政書士法、個人情報保護あたりです。もっとも、人によって、得意・不得意分野は異なるので、自分にとってハードルが低そうなところを得点源にしていけるようにしましょう。
私も、文章理解や情報通信(IT)はある程度自信はありましたが(当時は行政書士法はない)、一般知識は幅広く、最後の最後まで脚切りにならないか不安でした。
全体の傾向として、本試験の前年度(4月から3月)にあったことに関連した出題が多いので、一般知識(政治・経済・社会)や情報通信などは、前年度に何があったか、どのような用語を聞くようになったかを考えながら目星を立てるのがおすすめです。
その際、基本書にあるロック、モンテスキュー、ルソーなどから学習するのも良いですが、高校の公共の知識がある程度身についている方は、就職活動をする方が読むニュースや時事用語の本(池上彰さんが解説するような本)を読んでおくとよいでしょう。
次回の本試験、基礎知識対策をして臨みましょう。