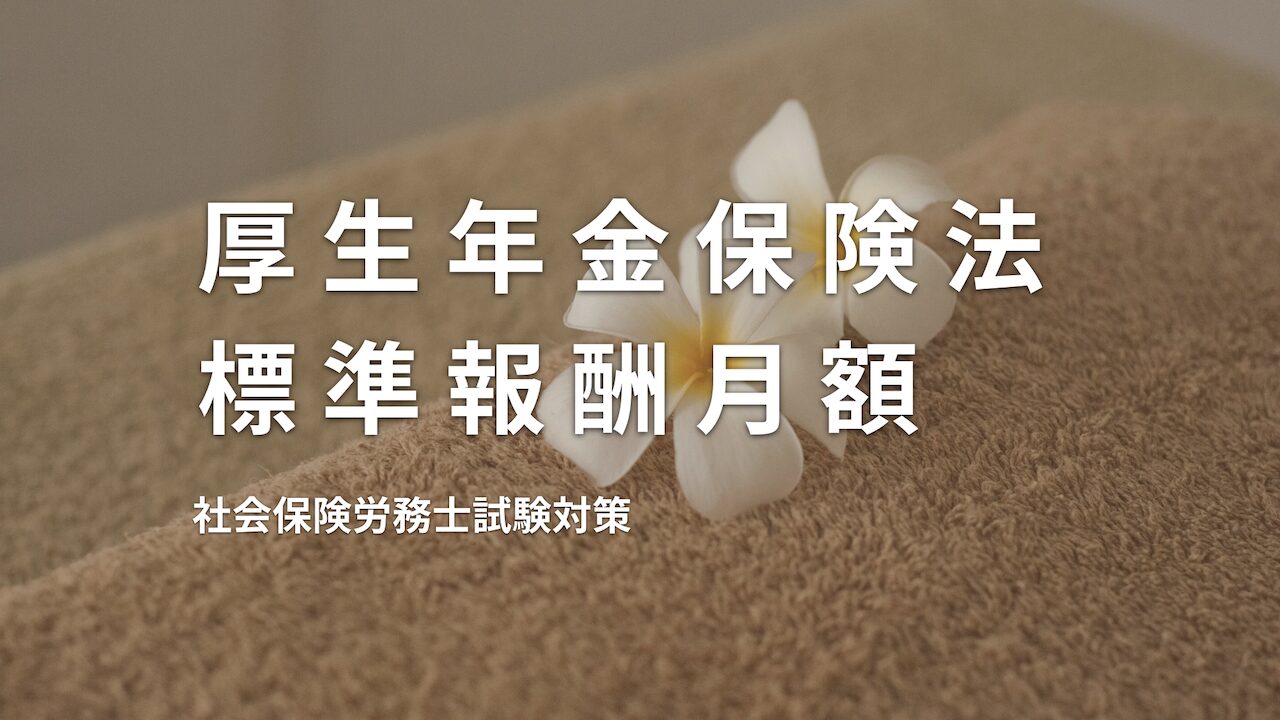厚生年金保険法の保険給付から通則について学習します。第3章「保険給付」は、全5節で構成されています。特に老齢厚生年金に関しては、法附則に振り回されることが多いところなので、まずは本則がどのようになっているか基本をきちんとさえるところからはじめましょう。
目次
保険給付の種類
この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関が行う(32条)。
① 老齢厚生年金
② 障害厚生年金及び障害手当金
③ 遺族厚生年金
まずは、本則で定められている保険給付の種類をおさえておきましょう。
裁定
裁定とは、年金等の給付を受ける権利を実施機関等が確認する行為をいいます。
端数処理
年金の支給期間及び支払期月
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする(36条1項)。
年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない(36条2項)。
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする(36条3項)。
2月期支払の年金の加算
支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする(36条の2第1項)。
毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする(36条の2第2項)。
未支給の保険給付
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる(37条1項)。
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす(37条5項)。
このあたりは、国民年金法と共通しています。
併給の調整
障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする(38条1項)。
前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない(38条2項)。
第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があったものとみなす(38条3項)。
第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があったものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かって撤回することができる(38条4項)。
国民年金法にも出てきた併給の調整についてまとめます。
障害厚生年金
まず、障害厚生年金は、受給権者が他の年金を受けることができるときは、その間、支給を停止します。カッコ書きにあるように、障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除くので、障害基礎年金と障害厚生年金は同時に受給できます。
老齢厚生年金
次に、老齢厚生年金は、受給権者が他の年金を受けることができるときも、同様とする、つまり、その間、支給を停止します。老齢厚生年金のひとつめのカッコ書きにあるように、遺族厚生年金は除きます。もっとも、あとで学習しますが、遺族厚生年金は、受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます。つまり、差額分が支給されるということです。条文では「遺族厚生年金を除く」とありますが、実質的、老齢厚生年金または遺族厚生年金のいずれかひとつが支給されると考えることができます。
また、老齢厚生年金のふたつめのカッコ書きにあるように、老齢基礎年金と障害基礎年金を除くので、これらと、老齢厚生年金は同時に受給できます。なお、付加年金については、老齢基礎年金に付いてくるものなので、ここでは言及しません。
遺族厚生年金
最後に、遺族厚生年金は、受給権者が他の年金を受けることができるときも、同様とする、つまり、その間、支給を停止します。遺族厚生年金のひとつめのカッコ書きにあるように、老齢厚生年金は除きます。もっとも、先ほど言及したように、老齢厚生年金と遺族厚生年金は支給の調整がされます。
また、遺族厚生年金のふたつめのカッコ書きにあるように、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を除くので、これらと、遺族厚生年金は同時に受給できます。
併給の調整のまとめ
併給の調整は、条文で理解するのは難しいので、図や表で理解するのをおすすめします。以下の表では、下段に基礎年金、上段に厚生年金を記載しています。これは、国民全員が受けられる1階部分の基礎年金と会社員等が受けられる2階部分の厚生年金を表しています。また、年金の順番は、保険給付の種類に併せて、老齢、障害、遺族の順番で解説します。
併給の基本
| 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 |
| 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
まず、原則として、1段目の基礎年金から1つ、2段目の厚生年金から1つ受給できます。各法律から1つずつ受給できると考えるとわかりやすいと思います。先ほど、老齢厚生年金と遺族厚生年金が互いに併給の調整から除かれていましたが、これらも老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止され、差額が支給されることになるので、実質的には1つと考えることができます。
次に、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金といったように、縦に同じ種類の年金は併給することができます。
これを前提に、老齢、障害、遺族の併給についてみていきましょう。
- 老齢年金は、1階、2階
- 障害年金は、1階
- 遺族年金は、2階
老齢年金
老齢年金は、1階と2階の両方に位置することができます。
| 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金(△) | |
| 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 |
組み合わせとしては、3つあります。
- 老齢基礎、老齢厚生
- 老齢基礎、遺族厚生
- 障害基礎、老齢厚生
障害年金
障害年金は、1階に位置することができます。
| 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 |
| 障害基礎年金 |
組み合わせとしては、3つあります。
- 障害基礎、老齢厚生
- 障害基礎、障害厚生
- 障害基礎、遺族厚生
遺族年金
遺族年金は、2階に位置することができます。
| 老齢厚生年金(△) | 遺族厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
組み合わせとしては、3つあります。
- 遺族基礎、遺族厚生
- 老齢基礎、遺族厚生
- 障害基礎、遺族厚生
もう一度まとめると次のようになります。
- 老齢・障害・遺族の同じ種類の年金は、基礎と厚生で併給できる
- 異なる場合、老齢は、1階・2階部分になれる(老齢基礎・遺族厚生)(障害基礎・老齢厚生)
- 異なる場合、障害は、1階部分になれる(障害基礎・老齢厚生)(障害基礎・遺族厚生)
- 異なる場合、遺族は、2階部分になれる(老齢基礎・遺族厚生)(障害基礎・遺族厚生)
私も、ここばかりは表を見ながら理屈抜きで暗記しました。もし、よりわかりやすい覚え方をしている方がいたら、ぜひお教えください。
受給権者の申出による支給停止
年金たる保険給付は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する(38条の2第1項本文)。
支給停止の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる(38条の2第3項)。
支給停止の申出により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす(38条の2第4項)。
このあたりは、国民年金法と同じです。
年金の支払の調整
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす(39条1項)。
(以下省略)
内払と充当についても、国民年金法と同じです(条文は省略します)。
損害賠償請求権
政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(40条1項)。
前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
不正利得の徴収
受給権の保護及び公課の禁止
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない(41条1項)。
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない(41条2項)。
このあたりも、国民年金法と同じように考えることができます。