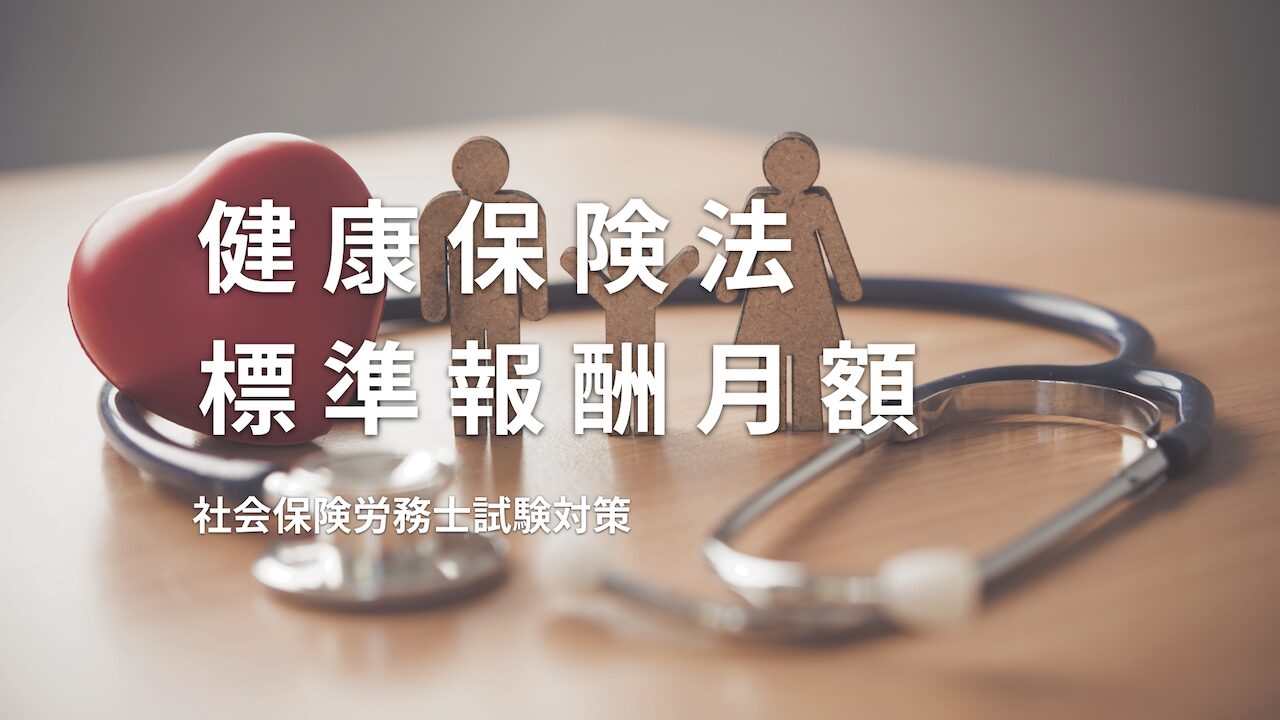健康保険法の被保険者から資格について学習します。第2章が「保険者」側であったのに対し、第3章は「被保険者」側について規定しています。
適用事業所
この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう(3条3項)。
① 適用業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉事業及び更生保護事業
レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
② 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
①適用業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、②国、地方公共団体または法人の事業所であって常時従業員を使用するものを適用事業所といいます。
まず、国や地方公共団体、法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは適用事業所になります。そして、もしそうでなくても、適用事業で常時5人以上の従業員を使用しているものも適用事業になります。このように2号、1号の順番だと記憶しやすいと思います。
事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる(昭18.4.5保発905号)。
適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる(31条1項)。
適用事業所の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない(31条2項)。
適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることができます。ただ、適用事業所になると、被保険者となるべき者は、保険料を負担することになるので、2分の1以上の同意が必要になります。国保は全額負担だから社会保険の方がお得なのではといったことは考えず、被保険者として費用負担をすることになるため同意が必要と考えるようにしましょう。
労働保険のところでも出てきましたが、適用事業所に該当しなくなったときは、保険関係が消滅するのではなく、認可を受けて適用事業所となったものとみなします。
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる(33条1項)。
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない(33条2項)。
今度は、適用事業所でなくす場合です。適用事業所でない場合、適用事業所となるかは任意です。そこで、被保険者の4分の3以上の同意を得て、申請することで、適用事業所でなくすことができます。同意が必要なのは、これまで事業主が半額費用負担してくれていたという利益がなくなるからです。
参考:適用事業所とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
資格取得の時期
「使用されるに至った日」とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係の発生した日である(昭53.11.6保規522号)。
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する(昭50.3.29保険発25号)。
資格喪失の時期
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する(36条)。
① 死亡したとき。
② その事業所に使用されなくなったとき。
③ 適用除外の規定に該当するに至ったとき。
④ 任意適用事業所の取消しの認可があったとき。
原則として、①号から④号は、少なくともその日の途中までは被保険者であったと考えることができるため、たとえば、死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。ただ、その事実があった日にさらに前条(資格取得の時期)に該当するに至ったときは、被保険者の期間が重複してしまうため、たとえば、A事業所に使用されなくなった日と同じ日にB事業所に使用されたときは、その日に被保険者の資格を喪失します(同時にB事業所で資格取得します)。
任意継続被保険者
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる(37条1項)。
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない(37条2項)。
これまでしばしば出てきた任意継続被保険者についてです。任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければなりません。また、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。ただし、いずれの場合も正当な理由があるときは認められることがあります。
参考:任意継続とは | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する(38条)。
① 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
② 死亡したとき。
③ 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
④ 被保険者となったとき。
⑤ 船員保険の被保険者となったとき。
⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
1号について、任意継続被保険者は2年までなので、2年を経過すると資格喪失します。3号について、「初めて納付すべき保険料を除く。」となっているのは、初めて納付すべき保険料を納付しない場合は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされるからです。
4号から6号については、被保険者の資格喪失の時期と同じように考えることができます。
7号は、任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合です。この場合、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときの翌日に資格喪失します。
資格の得喪の確認
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号[適用事業所でなくする認可があったとき]に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない(39条1項)。
確認は、届出若しくは請求により、又は職権で行うものとする(39条2項)。