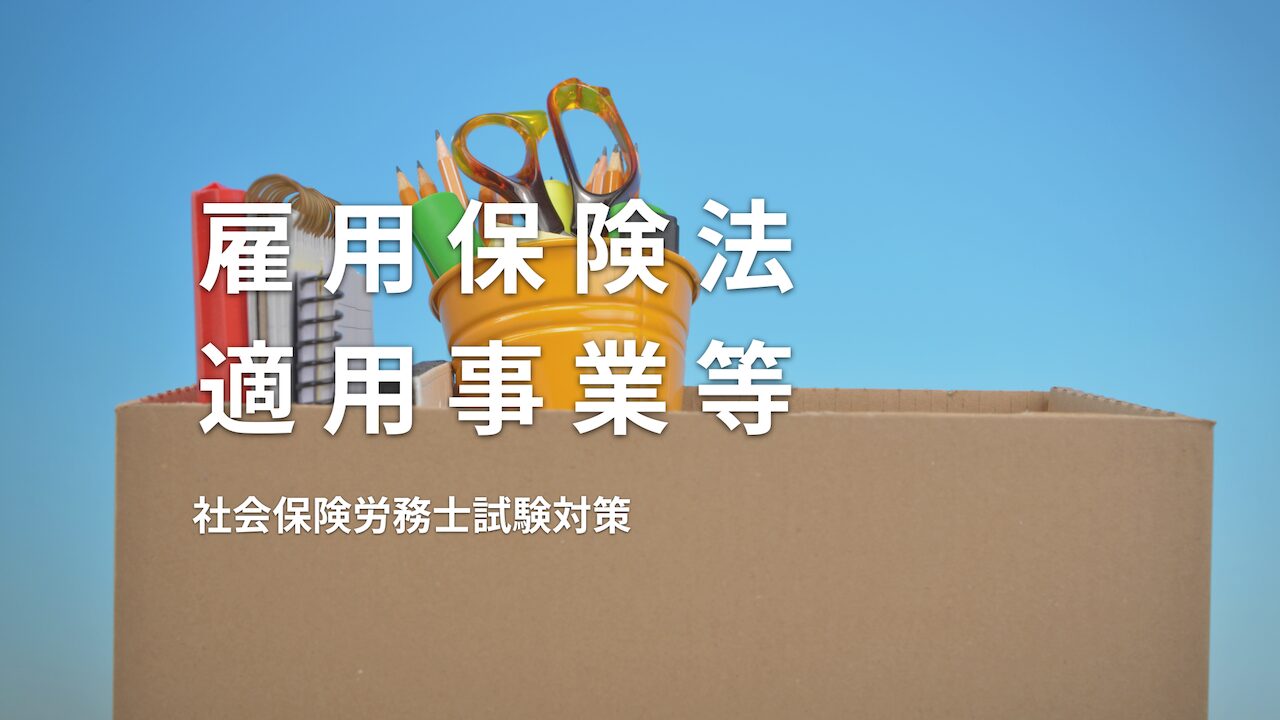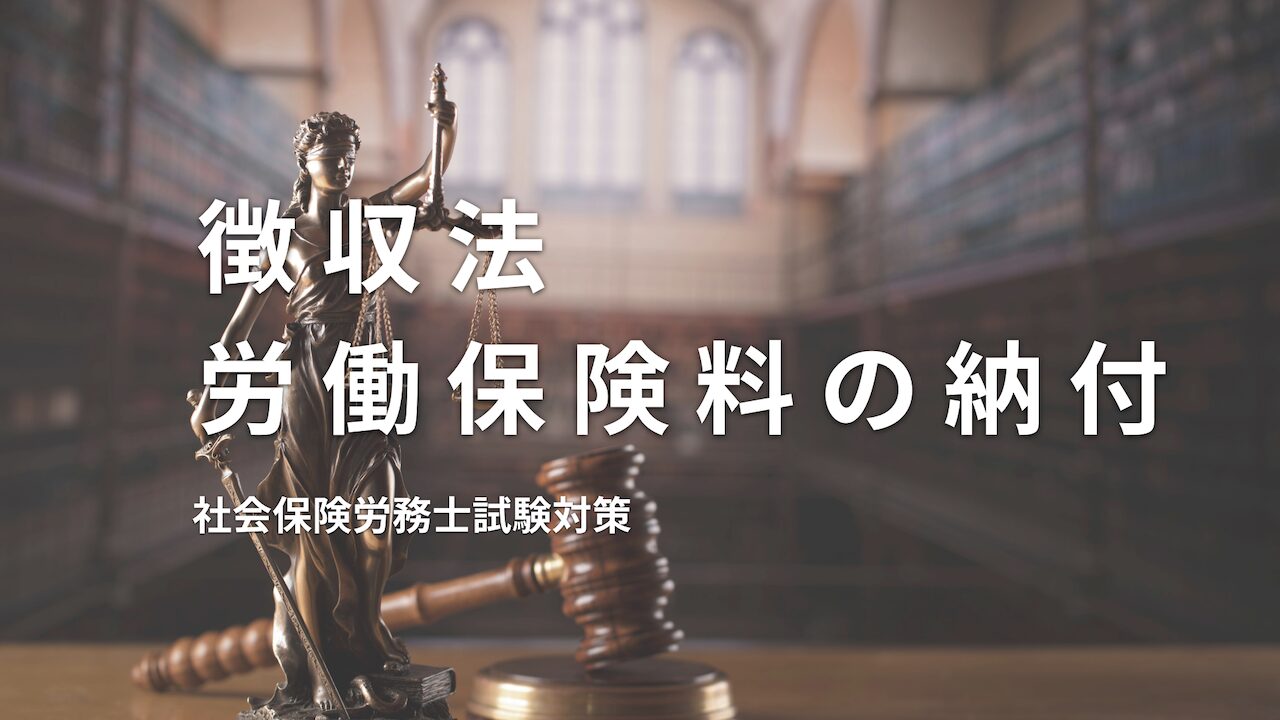※現在、リライト中です。
徴収法の保険関係の成立及び消滅について学習します。
目次
保険関係の成立
労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき保険関係が成立する(3条)。
雇用保険法適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(4条)。
どちらも、「その事業が開始された日に」保険関係が成立します。本試験対策として、届出をした日に成立するわけではない点に注意しましょう。
労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する(整備法5条1項)。
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない(同条2項)。
労災保険法の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があったものとみなす(同条3項)。
労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置
労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条[事業の廃止等]の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する(整備法8条1項)。
前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない(同条2項)。
① 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
② 労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
労災保険の暫定任意適用事業は、成立と消滅はそれぞれ過半数の同意が必要になります。
雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置
雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(附則2条1項)。
前項の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない(同条2項)。
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない(同条3項)。
雇用保険法の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす(同条4項)。
雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置
雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第5条[事業の廃止等]の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する(附則4条1項)。
前項の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない(同条2項)。
雇用保険法の暫定任意適用事業については、成立は半数以上、廃止は4分の3以上というように、労災保険法と比較して成立しやすく廃止されにくくなっているのをおさえておきましょう。労働災害については、仮に保険関係が成立していなかったとしても労働基準法の規定によって使用者から補償を受けることができます。一方、雇用保険は、そのような代替するものがないため、労災保険よりも成立しやすく消滅しにくくなっていると考えると、労動者の同意要件が理解記憶しやすいと思います。
暫定任意適用事業については、以下をご参照ください。
保険関係の成立の届出等
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない(4条の2第1項)。
保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない(4条の2第2項)。
届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない(規則4条2項)。
事業主は、事業が成立した日から10日以内に政府に届け出る必要がありますが、提出先は、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長になっている点をおさえておきましょう。
労働保険に関する事務は、官署支出官が行う還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う(規則1条1項)。
① 労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く。) 所轄都道府県労働局長
② 前号の事務であって、第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 所轄労働基準監督署長
③ 第1号の事務であって、第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 所轄公共職業安定所長
労働保険関係事務のうち、法第33条第2項、第3項及び第4項の規定による事務[労働保険事務組合が行う労働保険事務]は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う(規則1条2項)。
労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う(規則1条3項)。
① 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39第1項の規定に係る事業[都道府県及び市町村の行う事業等]についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料並びに第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
② 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業[都道府県及び市町村の行う事業等]についての一般保険料、一元適用事業についての第1種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
保険関係の消滅
有期事業の一括
2以上の事業が次の要件に該当する場合には、その全部を一の事業とみなす(7条各号)。
① 事業主が同一人であること。
② それぞれの事業が、有期事業であること。
③ それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
④ それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
保険関係は、その事業が開始された日に、その事業につき成立するのが原則です(3条)。しかし、事業の期間が予定される事業(有期事業)の場合、同じ会社が複数の有期事業を行っていることは珍しくなく、有期事業ごとに保険関係を成立させると事業の効率的な運営が図れなくなってしまいます。そこで、要件に該当する場合には、全部を一の事業とみなしています。
1号、2号は、有期事業の一括をする趣旨から理解できると思います。
3号について、
厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする(規則6条1項)。
① 当該事業について労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。
② 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満であること。
「それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。」とは、つまり、規模が小さいので一括してよいということです。もう少しいうと、規模が小さいものについていちいち保険関係を成立させるのは煩雑である、規模が大きいものはそれぞれ保険関係を成立させようということです。
5号について、
厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする(規則6条2項)。
①それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
②それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
③それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
有期事業の一括は、建設の事業、または立木(りゅうぼく)の伐採の事業が対象です。また、徴収法は、事業の種類ごとに保険料が定められており、この事業の種類を同じくしているものが対象になります。そして、労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要となります。
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合でも、有期事業の一括の対象事業とされない(昭40.7.31基発901号)。
一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う(昭40.7.31基発901号)。
一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている(昭40.7.31基発901号)。
請負事業の一括
厚生労働省令で定める事業[建設の事業]が数次の請負によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする(8条1項、規則7条)。
前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する(8条2項)。
建設業が数次の請負によって行われる場合は、その事業をひとつの事業とみなし、元請負人のみを事業主とします。
2項がわかりにくいと思うので、補則します。1項のとおり、基本的に建設業が数次の請負によって行われる場合には、元請負人のみを事業主とします。ただ、元請負人と下請負人が、下請負人の請負に係る事業に関して適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、その下請負人を元請負人とみなして、つまり下請負人も適用事業となるということです。
ただ、徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るためという趣旨があるため、認可の要件が規定されています。
規則6条1項各号とは、「当該事業について労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。」「請負金額が1億8000万円未満であること。」です。6条1項各号に該当する事業以外なので、160万円以上、かつ、1億8000万円以上ということになります。
継続事業の一括
今度は、継続事業でも、一定の要件を満たすものについては、厚生労働大臣の認可があったとき、一括になるというものです。条文の表現通りに解釈すると、AとBの事業があるうち、いずれか一の事業(例:事業A)に使用される労働者とみなして、指定された一の事業以外の事業(例:事業B)に係る保険関係は、消滅することになります。
要件については、事業主が同一人である2以上の事業であることです。カッコ書きで「(有期事業以外の事業に限る。)」とあるのは、有期事業は、一定の規模以下なら当然に一括事業となるからです。
次に、厚生労働省令で定める要件について、
厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする(規則10条1項)。
① それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
ハ 一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
② それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
「一元適用事業」と「二元適用事業」について、ここで補則します。
一元適用事業とは、「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業以外の事業」をいいます(1条3項1号)。
二元適用事業とは、「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業」をいいます。正確には、より細かいものも含まれますが、社労士の試験対策として必要十分なものに限定します。
また、「その他厚生労働省令で定める事業」には、都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業、建設の事業などが含まれます(規則70条)。
ここで、なぜ「一元適用事業」というのかというと、労災保険と雇用保険に関する事務を一元的に処理するからです。一元適用事業が、「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業以外の事業」となっているのは、これらの事業以外は一元的に処理するからです。
一方、「二元適用事業」は、「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業」です。これらの事業は、労災保険に係る保険関係、雇用保険に係る保険関係といったように、ひとつの事業でも二元的に処理します。もう少し言うと、都道府県や市町村などが行う事業は、労災保険と雇用保険を二元的に処理しているとなります。
継続事業の一括の「厚生労働省令で定める要件」に戻ると、まず、1号のイロハのいずれかひとつに当てはまるものが対象となります。また、事業の種類が同じであることも必要です。
① 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
② 申請年月日
③ 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
④ 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
記載事項を覚える必要はありませんが、指定される事業は当該事業主の希望する事業と必ずしも一致しない場合があるという点はおさえておきましょう。
まとめ
ここでは、保険関係の成立と消滅、そして一括について見てきました。一括は、有期事業の一括、請負事業の一括、継続事業の一括がありました。
有期事業の一括は、同一の事業主による一定規模以下の有期事業が一括されるものです。請負事業の一括は、建設業において元請負人のみが事業主となるものです。これには、下請負人も事業主となる例外が定められていました。継続事業の一括は、一定の継続事業が認可を受けることによって一括されるものです。それぞれの要件について、復習や過去問演習を通して知識を定着させるようにしましょう。
参考:用語の解説|厚生労働省