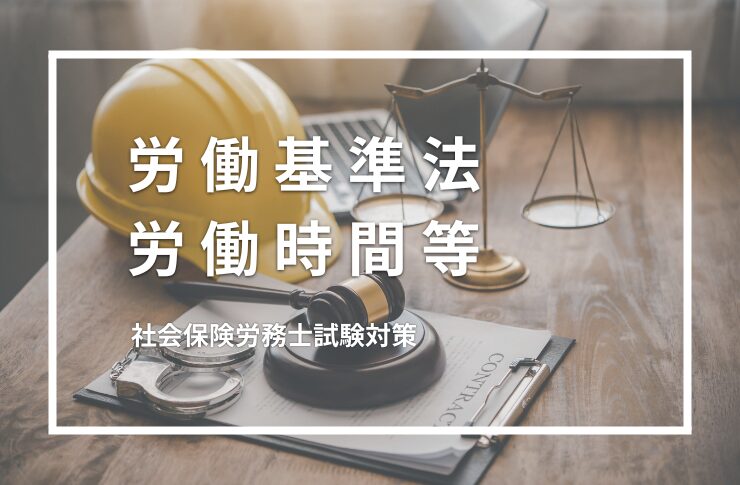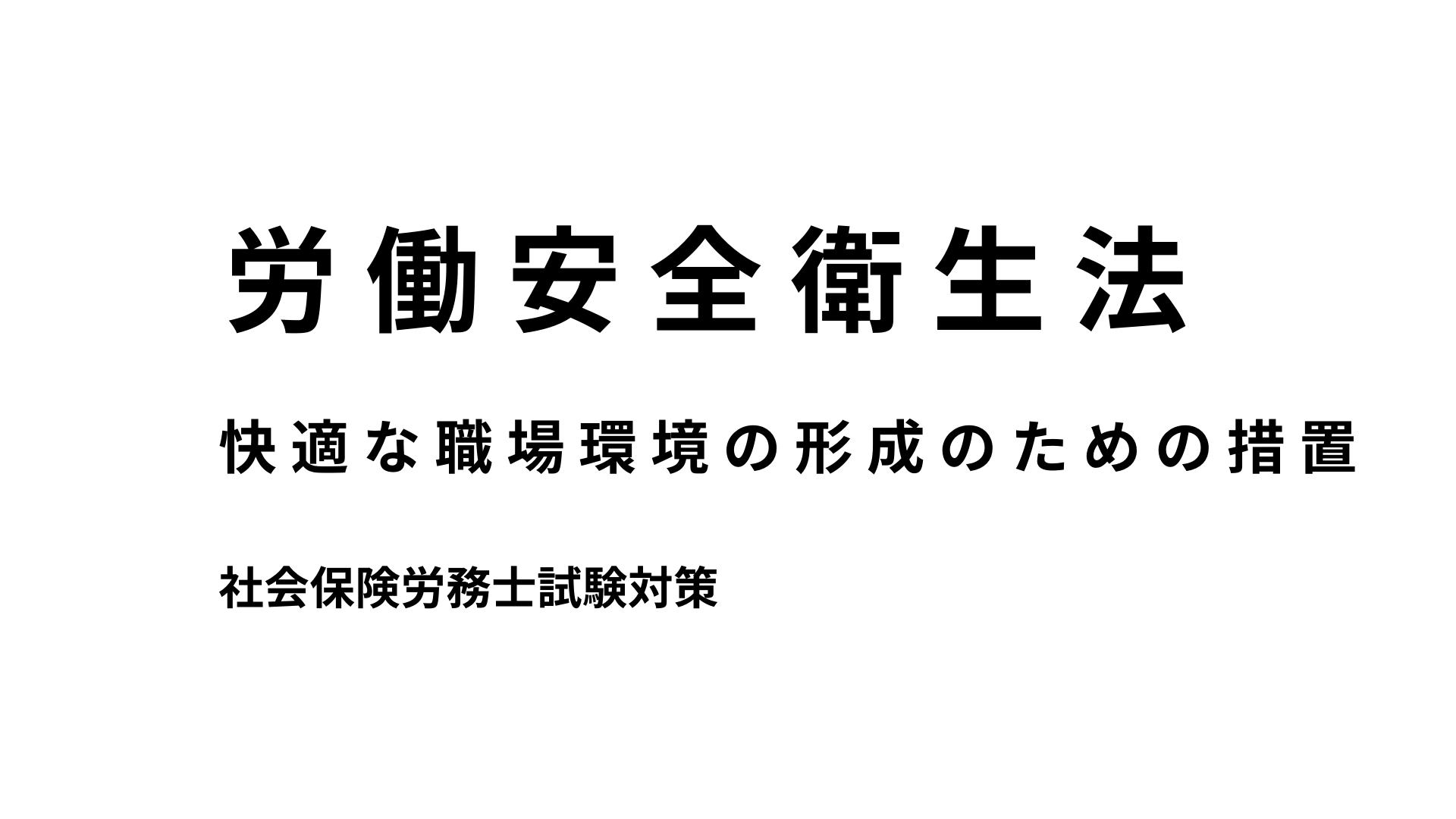労働安全衛生法の健康の保持増進のための措置について解説します。
※リライト中です。
目次
作業環境測定
・事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない(65条1項)。
作業環境測定の結果の評価等
・事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない(65条の2第1項)。
・事業者は、評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない(65条の2第2項)。
・事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない(65条の2第3項)。
→結果の記録については、少し細かいので省略します。結果を記録しておかなければならないというところまで押さえておきましょう。
作業の管理
・事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない(65条の3)。
健康診断
・事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない(66条1項)。
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている(昭47.9.18基発602号)。
→健康診断については、規則で定められていますが、頻出なので押さえておきましょう。
雇入時の健康診断
・事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない(規則43条1項)。
→労働者が、3か月以内に健康診断を受けた場合で、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、事業者は、健康診断を行わなくてもよいということです。
定期健康診断
・事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない(規則44条1項)。
特定業務従事者の健康診断
・事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない(規則45条1項)。
→特定業務とは、有害放射線にさらされる業務や粉末を著しく飛散する場所における業務、身体に著しい振動を与える業務、坑内における業務、深夜業を含む業務などが規則で指定されています。
・事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする(66条2項)。
→有害な業務とは、高圧室内作業、放射線業務、特定化学物質を製造し若しくは取り扱う業務などが政令で指定されています(政令22条1項、政令6条)。
特定業務や有害な業務に関しては、すべて覚えようとするとパンクしてしまうので、深追いせず、特別の健康診断が必要である程度にとどめておきましょう。
海外派遣労働者の健康診断
・事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない(規則45条の2第1項)。
・事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない(規則45条の2第3項)。
→海外に行くときと帰ってきたときは健康診断が必要ということです。
給食従業員の検便
・事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない(規則47条)。
以下、法律に戻ります。
・事業者は、有害な業務で、政令で定めるもの[塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務]に従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより[その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に]、歯科医師による健康診断を行なわなければならない(66条3項、政令22条3項、規則48条)。
→政令で定める業務をひとつずつ覚える必要はありませんが、歯などに影響がありそうな業務に従事する場合は、6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行う必要があるということを押さえておきましょう。
・都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる(66条4項)。
・労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない(66条5項)。
自発的健康診断の結果の提出
・深夜業に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの[常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したこと]は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる(66条の2、規則50条の2)。
健康診断の結果の記録
・事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断の結果を記録しておかなければならない(66条の3)。
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
・事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない(66条の4)。
健康診断実施後の措置
・事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない(66条の5)。
→労働者のことを考えて、就業場所の変更等をする必要があるということです。
健康診断の結果の通知
・事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより[遅滞なく]、当該健康診断の結果を通知しなければならない(66条の6、規則51条の4)。
保健指導等
・事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない(66条の7第1項)。
・労働者は、通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする(66条の7第2項)。
面接指導等
・事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者[休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者]に対し、厚生労働省令で定めるところにより[労働者の申出により]、医師による面接指導を行わなければならない(66条の8第1項、規則52条の2第1項、規則52条の3第1項)。
・事業者は、面接指導の結果を記録して5年間保存しなければならない(66条の8第3項、規則52条の6第1項)。
・事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない(66条の8第4項)。
・事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない(66条の8第5項)。
・事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間[休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間]を超える労働者(労働基準法第36条第11項[新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務]に従事する者に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない(66条の8の2第1項、規則52条の7の2第1項)。
→整理しましょう。まず、労働基準法36条は、「三六協定」によって、「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」としています(36条1項)。そして、3項から5項、6項では限度時間等について定めています。さらに、11項では、「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」については、この限度時間が適用されないとしていました。ここまでが労働基準法における規定です。
ただ、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に就いている人には限度時間が適用されないといっても、同じ人間であることには変わりません。そこで、労働安全衛生法によって、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月あたり100時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないとしています。先ほどの、通常の労働者が「80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」であったことと比較しておきましょう。
・事業者は、面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない(66条の8の3)。
・事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者[高度プロフェッショナル制度の対象労働者]であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間[1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間]を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない(66条の8の4)。
→ここも整理しましょう。労働基準法41条の2第1項は、高度プロフェッショナル制度について定めています。対象者は、金融商品の開発や資産運用など高度の専門的知識等を必要とするもので、従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められるものです。
ただ、彼らもまた同じように人間です。そこで、労働安全衛生法によって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月あたり100時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないとしています。
ここで「健康管理時間」という言葉が出てきました。高度プロフェッショナル制度の場合、さまざまな場所で業務をすることが考えられるため、当該対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間を健康管理時間としています。ただ、健康管理時間そのものについて聞かれることは少ないと思うので、前述の「新たな技術」と今回の「高プロ」に関しては、「100時間を超える労働者」という言葉をキーワードに反応できれば十分です。
心理的な負担の程度を把握するための検査等
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
→いわゆる「ストレスチェック」と呼ばれるものです。
・検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより[遅滞なく]、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない(66条の10第2項、規則52条の12)。
→ストレスチェックは、労働者の職場における心理的な負担の原因などについて検査をするものです。そのため、検査の結果は、医師等から直接労働者に対し、通知されるようにしなければなりません。労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならないというのがポイントです。
・事業者は、通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの[検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたもの]が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより[遅滞なく]、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない(66条の10第3項、規則52条の15、52条の16第2項)。
・事業者は、面接指導の結果を記録して5年間保存しなければならない(66条の10第4項、規則52条の18第1項)。
・事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない(66条の10第5項)。
・事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない(66条の10第6項)。
・厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(66条の10第7項)。
・厚生労働大臣は、指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる(66条の10第8項)。
健康管理手帳
・都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。(67条1項本文)。
→政令で定めるものは、ベンジジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務や粉じん作業に係る業務などがあります(政令23条)。厚生労働省令で定める要件は、期間や病名などが細かく規定されていますが、本試験対策上、ここは割愛します。「がんなどの健康障害を生ずるおそれのある業務についていた者に、健康管理手帳を交付する」と覚えておきましょう。
・政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう(67条2項)。
病者の就業禁止
・事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない(68条)。
受動喫煙の防止
・事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする(68条の2)。
健康教育等
・事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(69条1項)。