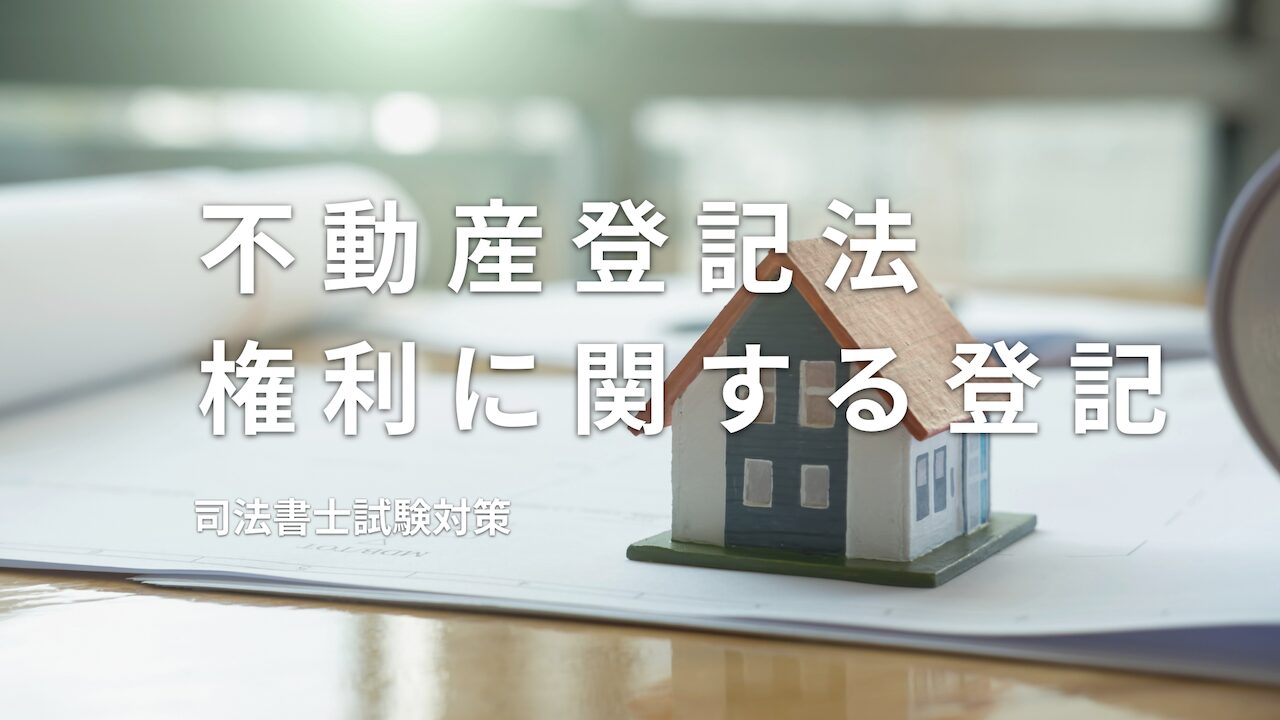不動産登記法の登記手続の権利に関する登記の担保権等に関する登記から買戻しの特約の登記について学習します。第4款が担保権等になっているのは、担保権ではない買戻しの特約が含まれているからです。
買戻しの特約の登記の登記事項
買戻しについて、民法をみてみましょう。
売主は、買戻権を行使することにより、売買の解除をすることができます。これにより、資金が必要になったとき、一時的に不動産を売却し、後で買い戻すといったことができるようになります。
買戻しの特約の登記は、あくまで特約なので、売買契約に「特約」として登記する形になります。担保権のような意味合いがあるけれど、担保権ではないという感覚がわかると思います。
そして、買戻しの特約の登記は、買主が支払った代金、契約の費用、買戻しの期間の定めがあるときはその定めを登記します。カッコ書きとして、合意により定めた金額を登記するときは、「合意金額」として登記をします(通常は「売買代金」として登記をします)。
買戻しの期間について、民法をみてみましょう。
買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする(民法580条1項)。
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない(580条2項)。
買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない(580条3項)。
買戻しの期間は、10年を超えることができません。これより長い期間を定めたときは、10年になります。また、買戻しの期間を定めなかったときは、5年になります。
ここで、権利に関する登記の通則の内容をおさらいしましょう。
買戻しの期間は最長10年のため、10年を経過したときは、権利者(不動産の元の売主)は、単独で登記の抹消を申請することができます。