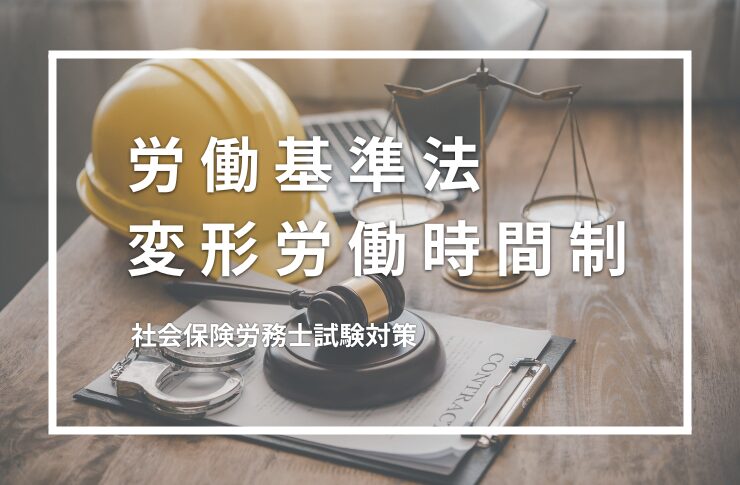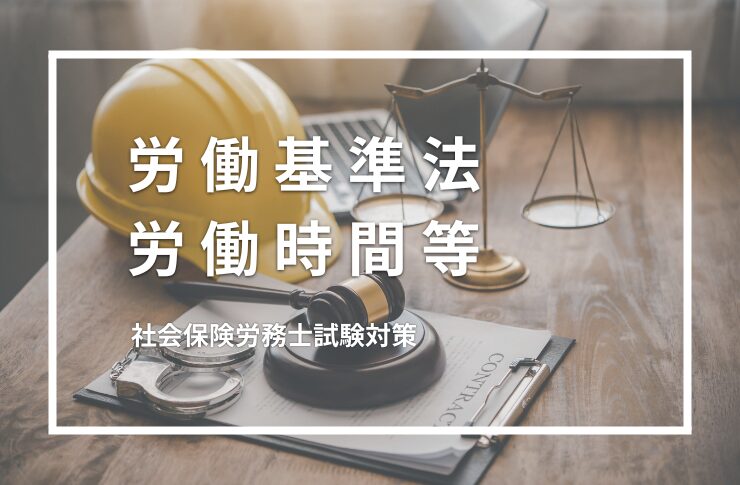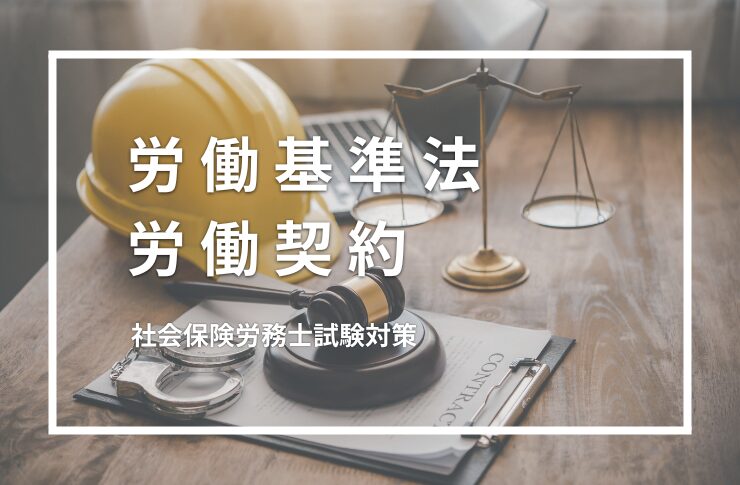労働基準法の年少者について学習します。年少者については、特に丸暗記になりやすい部分なので、条文から具体的にどのようなことなのか、原則と例外を分けておさえるようにしましょう。
最低年齢
まず、原則として、満15歳に達した以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならないということをおさえましょう。つまり、中学生であるまでの間ということです。ここに例外が加わります。
今回、イメージしやすいように条文の表現をそのまま使いました。それでは、別表1第1号から第5号までを見てみましょう。
2 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
表を見ると、製造業や鉱業、建設業などちょっと大人ではないと危なそうな事業であることがわかります。大切なのはこのあとです。これらの事業以外で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けた上で、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができます。使用できるのは、満13歳以上です。そして、次に、映画の製作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、使用することができます。
整理しましょう。
- 原則:満15歳以後の最初の3月31日まで禁止
- 例外1:有害でない、労働が軽易、行政官庁の許可、修学時間外→満13歳以上の使用できる
- 例外2:映画の製作、演劇の事業→満13歳未満の使用できる
以上の3段階になっていることをおさえましょう。
選択式問題の対策上、条文の表現をおさえておきたいところですが、便宜上、噛み砕いていうと、例外1は中学生以上なら働ける、例外2は中学生未満でも働けるということです。後者は、子役の俳優さんなどを想像すると理解しやすいと思います。
年少者の証明書
たとえば、15歳以上で働く場合や13歳以上で働く場合、戸籍証明書が必要になります。
児童については、義務教育のときに働くことになるので、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親権者又は後見人の同意書が必要になります。
- 学校長の証明書
- 親権者又は後見人の同意書
必要なものの「及び」と「又は」に注意しましょう。
未成年者の労働契約
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない(58条1項)。
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる(58条2項)。
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない(59条)。
これらは未成年者を保護するために設けられた規定です。
労働時間及び休日
整理しておきましょう。変形労働時間制とは、月単位や年単位に区切って、所定の労働時間を超えて労働させることができるものでした。三六協定は、労使協定の定めるところによって、労働時間を延長しまたは休日に労働させることができるものでした。労働時間の特例は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間まで労働させることができるものでした。高度プロフェッショナル制度は、労使委員会の決議があり、金融商品の開発や資産運用など高度の専門的知識等を必要とする業務に就いているものは、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定が適用されなくなるものでした。
かんたんにいうと、労働時間を長くするようなものは、満18歳未満の者には適用されないということです。条文をそのまま読むとややこしく感じますが、適用除外が適用されないということは、原則通り、してはいけないということです。
なお、応用論点ですが、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」(33条)や「労働時間等に関する規定の適用除外」(41条)は、60条1項が準用していないので適用されます。といっても、準用していないから適用されるだと丸暗記になってしまうので、補足します。
まず、33条1項本文は、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と定めています。これは、災害などで臨時の必要がある場合なので、年少者であっても適用されると考えましょう。
次に、41条は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号に該当する労働者については適用しない」と定めています。
- 農業、水産、養蚕、畜産業に掲げる事業に従事する者
- 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
1号について、農業や水産など自分の意志だけではコントロールできないものが対象になっています。2号について、年少者自身が監督・管理の地位にある者なので適用されません。同様に、3号も、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されません。
以上は、応用論点ですが、繰り返し本試験で問われているので、おさえておきましょう。
児童は、学校があるので、1週間と1日についての労働時間が制限されています。
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる(60条3項)。
① 1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
② 1週間について48時間以下、1日について8時間を超えない範囲内において、変形労働時間制により労働させること。
これまで、満15歳で3月31日までの間の者は、さまざまな規制がされていました。それが少し緩和されています。イメージでいうと、高校生です。
原則は、1日について7時間が限度でしたが、例外として、1週間のうちの1日を4時間以内にすることで、他の日の労働時間を10時間に延長することができるようになっています。また、1週間について48時間以下、1日について8時間を超えない範囲内において、1箇月単位、1年単位の変形労働時間制が適用できるようになります。
深夜業
18歳未満の者は、原則として、深夜業が禁止されています。ただし、例外として、交替制によって使用する16歳以上の男性は、深夜業もできます。男女差別という意味ではなく、深夜の時間帯の防犯も考慮して男性に限定されています。
ここでいう児童は、前半に出てきた児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて労働する満13歳以上の児童、映画の製作又は演劇の事業について労働する満13歳に満たない児童のことです(56条2項)。18歳未満が午後10時から午前5時まで7時間確保されているのに対し、児童は午後8時から午前5時まで9時間確保されている点に注意しましょう。
なお、通達は、「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合に、午後9時から午前6時までとすることができる」としています。これは、音楽テレビ番組に出演する必要があるアイドルグループなどを想像するとわかりやすいと思います。
参考「厚生労働省:労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間について」
坑内労働の禁止
基本的に、坑内労働は危険であるという価値判断を持っておくと理解しやすくなります。
帰郷旅費
通常の労働者の即時解雇のときと同じように、14日以内に帰郷する場合は、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。ただし、その者の責めに帰すべき事由のときは、必要な旅費を負担する必要はありません。もっとも、責めに帰すべき事由の判断は難しいので、行政官庁の認定が必要になります。これも通常の労働者のときと同じです。