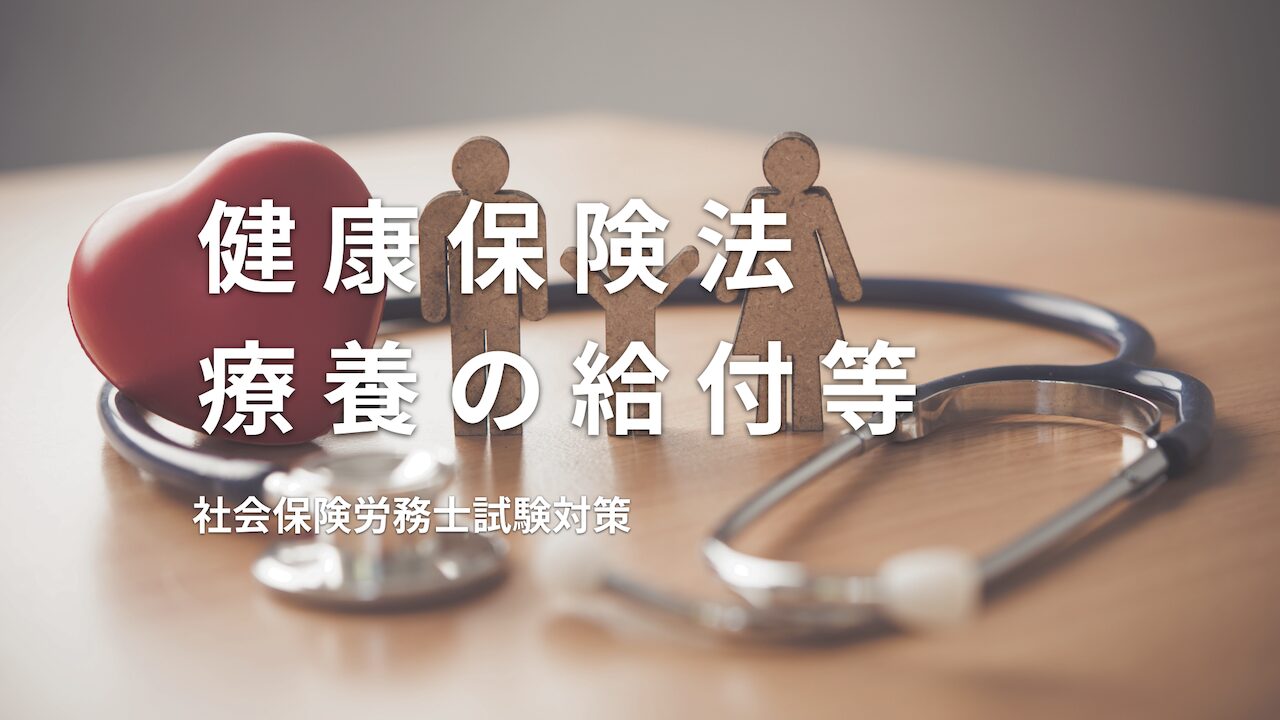健康保険法の保険給付から通則について学習します。
いよいよ保険給付です。第4章「保険給付」は全6節で構成されています。
- 第1節:通則
- 第2節:療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
- 第3節:傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
- 第4節:家族療養費等の支給
- 第5節:高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
- 第6節:保険給付の制限
今回は、保険給付の全体について定めている通則を見ていきましょう。
目次
保険給付の種類
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする(52条)。
① 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
② 傷病手当金の支給
③ 埋葬料の支給
④ 出産育児一時金の支給
⑤ 出産手当金の支給
⑥ 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
⑦ 家族埋葬料の支給
⑧ 家族出産育児一時金の支給
⑨ 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
これらはいきなり覚えられることではないので、ひとつずつ学習し、ひととおり学習したら、改めて全体像を見て現在位置を把握するなどしましょう。
健康保険組合の付加給付
健康保険組合は、規約で定めるところにより、その他の給付も行うことができます。
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例
健康保険法は、労働者とその被扶養者の疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うので、法人の役員については、保険給付は、行いません。もっとも、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものについては、労働者と変わらないので、保険給付を行います。小さな企業で、社長さんも従業員と同じように働いている職場を想像するとわかりやすいと思います。
日雇特例被保険者に係る保険給付との調整
日雇特例被保険者に関する特例により、保険給付が行われたときは、その限度において、行われません。条文だと難しく感じますが、重複して保険給付が行われないということです。
他の法令による保険給付との調整
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない(55条1項)。
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない(55条3項)。
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない(55条4項)。
労災法や介護保険法などによって健康保険の保険給付に相当する給付を受けることができる場合には、保険給付は行われないということです。
労働者災害補償保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険により給付する。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われない(昭48.12.1保険発105号)。
保険給付の方法
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする(56条1項)。
傷病手当金及び出産手当金の支給は、毎月一定の期日に行うことができる(56条2項)。
療養費等の支給は、その都度、行われます。条文が長くて驚いてしまいますが、病院に行ったとき、その都度、3割負担などで保険給付が受けられるということです。
また、傷病手当金と出産手当金の支給は、毎月一定の期日に行われます。反対にいうと、その都度、毎日支給されるわけではないということです。
損害賠償請求権
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(57条1項)。
前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる(57条2項)。
労災保険に出てきたものと同じです。
不正利得の徴収等
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる(58条1項)。
前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる(58条2項)。
保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる(58条3項)。
「全部又は一部」という意味は、詐欺その他の不正行為によって受けた分はすべてという趣旨である(昭32.9.2保発123号)。
文書の提出等
診療録の提示等
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる(60条1項)。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
受給権の保護
租税その他の公課の禁止
このあたりは、他の保険と同じです。