「新・担い手3法」の内容のひとつとして,経営事項審査のその他審査項目(W点)に「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」(W10※)の項目が新設されました。
建設業法において,「建設工事に従事する者は,建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない」と定められおり,継続的な教育意欲を促進させていく観点から,建設業者による技術や技能の向上の取組の状況を評価することになりました。
※W10とは,W点の10個目の審査項目という意味です。
技術者点と技能者点の評価の概要
「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」は,「技術者点」と「技能者点」で評価されます。しかし,建設業者ごとに技術者と技能者の割合は異なるため,そのままでは,きちんと取り組んでいるにもかかわらず正当な評価が得られないという結果が生じてしまいます。
そこで,全体を10点とした上で,技術者と技能者の比率に応じて計算します。
W10点=(技術者の比率)×(技術者点)+(技能者の比率)×(技能者点)
技術者点について

背景と評価内容
i-Constructionなどの施工のICT化が進展し,新たな技術の活用がより一層重要となる中,技術者は常に最新の技術を習得するため,継続的な技術研鑽が必要となっています。しかし,監理技術者資格者証の取得に5年ごとの講習受講が必要とされているものの,施工管理技士が永久資格となっていることから,技術研鑽は個人の自主性に委ねられている現状があります。
そこで,学会・業界団体等において認定されているCPDプログラムにおいて,建設業者に属する技術者1人当たりが1年間に取得したCPDの単位の平均値を評価します。
i-Construction(アイ・コンストラクション):国土交通省が進めている,ICTの全面的な活用等の施策を建設現場に導入することによって,建設生産システム全体の生産性向上を図り,魅力ある建設現場を目指す取組のこと。
CPD:技術者の継続教育/Continuing Professional Development
評価の詳細
W10点=(技術者の比率)×(技術者点)+(技能者の比率)×(技能者点)
W10点のうち,「(技術者の比率)×(技術者点)」の部分の詳細です。
1:技術者数とは
技術者数は,監理技術者になる資格を有する者,主任技術者になる資格を有する者,一級技士補,二級技士補の数の合計です。
2:CPD単位取得数
CPD単位取得数は,技術者が基準日前1年間に取得したCPD単位の合計数です。単位に含まれるのは,あくまで1年間に取得した単位です。「継続的な教育意欲を促進させていく」という観点から,「昔学んだことがある」というものは含まれません。
3:CPD単位
各技術者のCPD単位は,以下の式で計算します。
CPD単位:審査対象年に認定された単位数÷表の数値×30
| 付与団体 | 数値 |
| 公益社団法人空気調和・衛生工学会 | 50 |
| 一般財団法人建設業振興基金 | 12 |
| 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 | 50 |
| 一般社団法人交通工学研究会 | 50 |
| 公益社団法人地盤工学会 | 50 |
| 公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター | 50 |
| 公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 | 50 |
| 一般社団法人全国測量設計業協会連合会 | 20 |
| 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 | 20 |
| 一般社団法人全日本建設技術協会 | 25 |
| 土質・地質技術者生涯学習協議会 | 50 |
| 公益社団法人土木学会 | 50 |
| 一般社団法人日本環境アセスメント協会 | 50 |
| 公益社団法人日本技術士会 | 50 |
| 公益社団法人日本建築士会連合会 | 12 |
| 公益社団法人日本造園学会 | 50 |
| 公益社団法人日本都市計画学会 | 50 |
| 公益社団法人農業農村工学会 | 50 |
| 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | 12 |
| 公益社団法人日本建築家協会 | 12 |
| 一般社団法人日本建設業連合会 | 12 |
| 一般社団法人日本建築学会 | 12 |
| 一般社団法人建築設備技術者協会 | 12 |
| 一般社団法人電気設備学会 | 12 |
| 一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 | 12 |
| 公益財団法人建築技術教育普及センター | 12 |
| 一般社団法人日本建築構造技術者協会 | 12 |
数値に差があるのは,1人が認定を受けたときに「30点満点」に調整するためです。たとえば,表のいちばん上の「公益社団法人空気調和・衛生工学会」は50なので,「50(単位数)÷50(表の数値)×30=30点」で最高30点となります。CPD認定団体ごとの優劣はありません。
各技術者のCPD単位数に小数点以下の端数がある場合は,切り捨てます。
また,各技術者のCPD単位の上限は30です。たとえば,1人の技術者が1年間に複数団体でCPD認定を受けた場合は,1人が3団体で認定を受けても90にはならず,1団体のみを選択して最大30になるということです(複数団体分を合算することはできません)。
4:技術者点
技術者点は,以下の式で計算します。
技術者点:CPD単位取得数÷技術者数
これで,1人あたりのCPD取得単位数がわかります。表にしてみましょう。
| 技術者1人あたりのCPD取得単位数 | 評点 |
| 30 | 10 |
| 27以上30未満 | 9 |
| 24以上27未満 | 8 |
| 21以上24未満 | 7 |
| 18以上21未満 | 6 |
| 15以上18未満 | 5 |
| 12以上15未満 | 4 |
| 9以上12未満 | 3 |
| 6以上9未満 | 2 |
| 3以上6未満 | 1 |
| 3未満 | 0 |
たとえば,CPD単位取得数が230,技術者数が9人の場合,「230÷9=25.5」で技術者は8点となります。このあと,技術者数と技能者数の比率に応じて割り振られます(後述)。
技能者点について

「建設キャリアアップシステム」ウェブサイト
背景と評価内容
個々の技能者がその技能を磨き,それにふさわしい処遇を受けることが,施工能力の向上だけでなく,担い手の確保にもつながります。また,建設キャリアアップシステム(CCUS/Construction Career Up System)に蓄積される就業履歴や保有資格を活用した技能者の能力評価基準に基づき,4段階のレベルで技能者の技能が客観的に評価できるようになりました。
そこで,建設業者に所属する技能者のうち,認定能力評価基準により受けた評価が,基準日前3年間にレベル1以上向上した建設技能者の割合により評価します。
評価の詳細
W10点=(技術者の比率)×(技術者点)+(技能者の比率)×(技能者点)
W10点のうち,「(技能者の比率)×(技能者点)」の部分の詳細です。
1:技能者数とは
技能者数は、審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者の数です。ただし,建設工事の施工の管理のみに従事する者(監理技術者や主任技術者など)は除きます。
2:技能レベル向上者数
技能レベル向上者数は、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2に上がったなど)した者の数です。認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル1として審査します。
3:技能者点
技能者点は,以下の式で計算します。
技能者点:技能レベル向上者数÷(技能者数-控除対象者数)
控除対象者数は,審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者の数です。
これで,1人あたりのCPD取得単位数がわかります。表にしてみましょう。
| 1以上レベルアップした技能者の雇用状況 | 評点 |
| 15%以上 | 10 |
| 13.5%以上15%未満 | 9 |
| 12.0%以上13.5%未満 | 8 |
| 10.5%以上12.0%未満 | 7 |
| 9.0%以上10.5%未満 | 6 |
| 7.5%以上9.0%未満 | 5 |
| 6.0%以上7.5%未満 | 4 |
| 4.5%以上6.0%未満 | 3 |
| 3.0%以上4.5%未満 | 2 |
| 1.5%以上3.0%未満 | 1 |
| 1.5%未満 | 0 |
たとえば,技能レベル向上者数が3人,技能者が25人,控除対象者1人の場合,「3÷(25-1)=0.125(12.5%)」で技能者点は8点となります。このあと,技術者数と技能者数の比率に応じて割り振られます。
W10の計算
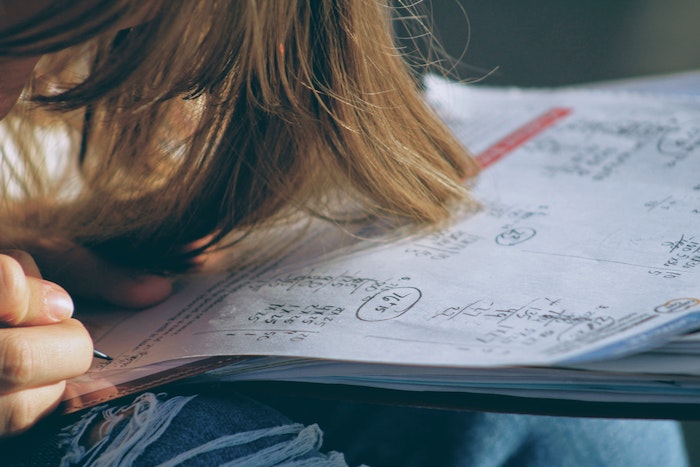
W10点=(技術者の比率)×(技術者点)+(技能者の比率)×(技能者点)
いよいよ,W10点を計算してみましょう。
技術者点の割合
A:技術者数÷(技術者数+技能者数)×技術者点
難しくみえますが,全人数(技能者と技能者を足したもの)のうち,技術者が占める割合を計算します。たとえば,技術者が20人,技能者が15人の場合,「20÷(20+15)」になります。
ここに先ほどの技術者点をかけます。
技能者点の割合
B:技能者数÷(技術者数+技能者数)×技能者点
同じように,技能者点を求めます。
合計する
W10:A(技術者点の割合)+B(技能者点の割合)
これでW10が計算できました。
下表にあてはめてみましょう。
| 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | W10 | P点換算 |
| 10 | 10 | 14.25 |
| 9以上10未満 | 9 | 12.83 |
| 8以上9未満 | 8 | 11.40 |
| 7以上8未満 | 7 | 9.98 |
| 6以上7未満 | 6 | 8.55 |
| 5以上6未満 | 5 | 7.13 |
| 4以上5未満 | 4 | 5.70 |
| 3以上4未満 | 3 | 4.28 |
| 2以上3未満 | 2 | 2.85 |
| 1以上2未満 | 1 | 1.43 |
| 1未満 | 0 | 0 |
いちばん右の列は,W10の点数をP点(経営事項審査の総合評点)に換算したものです。たとえば,W10が10点だと,P点が14.25点加算されることになります。





